アンディの有名曲の一つ「Super’70s」についての制作秘話です。
アンディのオンラインレッスンサイトの動画の中で、この曲の制作時の解説がされています。
その一部を抜粋して翻訳しました。
レッスンサイトはこちら(有料)
⇒ https://guitarxperience.net/
オンラインレッスンサイトでは、TAB譜や制作の解説、弾き方の細かい解説があります。
一部、ヤングギターやギターマガジンでのインタビュー記事から抜粋して補足しています。
▼以下、AIによる翻訳です。
さあ、タイムマシンに乗って今日は2001年まで戻ってみようと思うんだ。“Super 70s”っていう曲で、『That Was Then, This Is Now』っていうCDに入ってたやつなんだよね。これは、スティーヴ・ヴァイのレーベル“Favorite Nations”から出した、僕たちにとって最初のリリースだったんだ。
【補足】ギターマガジンのインタビューより———
スティーヴ・ヴァイより自分のレコード会社を設立するからアンディのレコードもリリースしたいという話になった。
アメリカではEarX-tasy1と2正式にはリリースされていなかったから、ヴァイは2枚組のCDとしてリリースする予定だった。最終的には、この2枚からベストな曲を選んで、それに最新5曲を加えたのが『That Was Then, This Is Now』
———
実は、“Falling Down”とか“Pink Champagne Sparkle”、“Beautiful Strange”も、このリリースのために録音した曲なんだ。スティーヴ(・ヴァイ)のアイデアとしては、僕の“Ear X-tacy”と“Ear X-tacy 2”をまとめたベスト盤を出して、そこに数曲新しいのをプラスしようってことだったんだよね。で、この“Super 70s”は、そのとき用に書いた曲なんだ。
【補足】ヤングギターのインタビューより———
Super 70sというタイトルは、アイバニーズが70年代に作ったギターについているピックアップ。
アンディが所有しているIbanezのギターの中に、Super’70というステッカーが貼られて、なんてクールなんだと思った。
———
【補足】Ibanez Super’70sというピックアップについて———
1970年代にIbanezが開発した、個性的なサウンドで知られるピックアップです。
当時、ギタリストたちはよりパワフルでサスティンの長いサウンドを求めており、 Super 70’s はそのニーズに応えるべく開発された。
エディヴァンヘイレンの1stアルバムでは、Ibanezのデストロイヤーを使っておりこのギターにSuper 70’sのピックアップが搭載されていた。
———
正直、当時の作曲プロセスはもう覚えてないんだけど、とにかくメジャーセブンス・コードへの愛がすごく表れてる曲なんだよ。
あちこちにメジャーセブンスの響きが散りばめられてるんだ。構成のことはまたあとで話すとして、“Super 70s”っていうタイトルは曲ができあがったあとに付けたものなんだよね。70年代のポップス、僕が大好きなトッド・ラングレンとかユートピアとか、あとはAMラジオで流れてたような音楽からの影響があって、そういう雰囲気のサウンドを意識したんだ。でも実際にはもっとヘヴィーなロックの曲になってて、7/8とか7/4(数え方次第だけど)の変拍子のパートも入ってるんだよね。これはうちのトリオが持ってるラッシュ(Rush)っぽい要素が出たって感じ。たぶん、7拍子のリフはミッチとマイクが考えたんだと思う。あの2人は僕より変拍子が好きだからさ(笑)。
まあそんな感じで、バリー・マニロウからラッシュまで、わりとバラバラな70年代の影響をミックスしたトリビュートみたいな曲なんだ。で、録音の話をすると、ベスト盤用のこの新曲4つはテキサス州パルマーにあるパルマイラ・スタジオで録ったんだよ。実はそこって、次の『Resolution』ってアルバムの基本トラック全部を録ったスタジオでもあるんだ。だから音の方向性的にも『Resolution』のサウンドに近づいていってるんだよね。メンバーは、ドラムがミッチ・マリーン、ベースがマイク・デインのいつもの“アンディ・ティモンズ・バンド”のトリオ編成なんだ。
▼Resolutionのレコーディングが起こん割れたスタジオでの一枚かと思われる写真

引用元:アンディのレコーディングエンジニア RobWechsler
https://www.facebook.com/rob.wechsler/posts/pfbid02B5ZaEWnwi39MmF52V66V151zR6MpjAkmAmNYacnUzsjNo6VodEhYcEKAAmCLs8SJl
▼機材に関して
機材に関しては、スタジオで録った基本トラックのギターは全部ボツにしちゃって、家のスタジオでオーバーダブを録り直したと思う。VHTのピットブル・アンプを使ったんだけど、今はちょっと故障中なんだ。で、今日はMesa Boogieのトリプルクラウン100Wヘッドを使うよ。いい音がするんだよね。あと、ギターに関して言うと、これはオリジナルのAT300のプロトタイプで、アイバニーズが僕に“SAシリーズをベースにしたシグネチャー・ギターを作らないか”って声をかけてくれたんだ。
▼レコーディングに使用されたモデルと同じVHTのピットブル。Electric Gypsyのレコーディングでも使用された。

AT-100じゃなくて、マホガニー・ボディにローズウッド・ネックを組み合わせたギターを開発し始めたんだ。それまで作ってきたのは、アルダー・ボディ+メイプル・ネックばっかりだったから、新しい方向を試したかったんだよ。
そしたら、明らかにもっと太くて“ガツン”としたトーンになったんだ。この初期のプロトタイプはボディの厚みが最終的に市販されたAT-300よりちょっと厚いんだよね。そんで、めちゃめちゃ重いんだ(笑)。マホガニーのかたまりって感じ。
ピックアップはどっちもボディに直付けしてあって、そのおかげで独特のパンチがあるんだ。とはいえ、中身はいつものDiMarzio AT-1とCruiserで、僕が長年使ってるやつと同じなんだけどね。
こうして改めて触ってみると、やっぱりいいなって思うんだ。動画撮るときは、なるべく当時の機材で当時の音を再現しようと思ってるから、このギターを引っぱり出してみたんだよ。ネックの幅は普段よりちょい広めだから、ちょっと珍しい感じなんだ。
▼このギターがプロトタイプ

だから独特でかっこいいフィーリングがあるんだよね。後ろにあるのは、その次のプロトタイプなんだ。これはインレイが入る前の段階で、最終的には“フル・ド・リ”っぽい綺麗なインレイが入ったんだけど。こっちが市販されたモデルの厚みに近いんだよ。
▼このギターが次のプロトタイプ(サスティナー搭載モデル)

だからこっちのほうがちょっと軽いんだ。後になってフェルナンデスのサスティナーも入れたから、たまに使ってるよ。こうやって昔のギターをいじるのって、やっぱり楽しいんだよね。このギターには、僕がすごく気に入ってる独特な雰囲気とサウンドがあるんだ。
当時の録音では、ペダルは使ってなかったと思う。VHTピットブルに直挿しだったんだよね。でも今日は、その音を再現するためにトリプルクラウンのクリーン・チャンネルに、メインはJHSのATプラスをつないでるんだ。
ブレイクダウンのパートでは、いつもの信頼してるエキゾチックBBプリの僕のシグネチャーバージョンを使ってる。あともうひとつ話しておきたいのが、オリジナル音源で流れるちょっとしたクリップについてなんだ。
あの短い演奏が入ってるだろ? 実はあれ、僕が自分の部屋で練習してたときの本物のテープなんだよ。たぶん1979年か1980年くらいだから、本当に“スーパー70s”って感じなんだ(笑)。で、この曲を作って録音したあとに、そのカセットを見つけたんだけど、よく聴いたら内容がほとんど同じ曲みたいでさ。
ちょうど僕がトッド・ラングレンの影響をめちゃくちゃ受けてたころで、彼は“別のルート音にメジャーコードを乗せる”っていうのをよくやってたんだ。例えばDの上にAメジャーを乗せると、Dmaj7(9)みたいな響きになるでしょ?
【補足】ギターマガジンのインタビューより———
Super’70sの利府を作ったあとで、このカセットテープを発見して両方聞いてみたら
コードの構成がかなり似ていたからイントロに使えると思ったんだ。
———
それで次のパートに行くんだけど、要はベース音に違うトライアドを重ねるっていう展開なんだ。で、曲の中にそのフレーズが流れてて、僕が部屋で練習してたら母親が“アンドリュー、ご飯よ”って声かける声が入ってるんだ。それがなんだかんだ、僕が母親の家で育って、母が“食事できたよ”って言いに来る瞬間が記録されてるのが面白くてさ(笑)。
でも、この曲を聴いてもらうとわかるけど、その“メジャー7”っぽいサウンドがそのまま使われてるんだよね。で、母はもう亡くなっちゃったんだけど、アルバムを完成させてマスタリングが終わったときにCDを送ったんだ。母が“レコードデビュー”ってわけ。僕は“わあ、母さんの声が入ってる、最高だ”ってすごく盛り上がったんだけど、1週間くらい経っても連絡がなくて、こっちから電話してみたら、「ああ、CDね、受け取ったわよ」って言って、「母さんの声入ってるけどどうよ?」って聞いたら、「全然聞こえないじゃない」とか文句言っててさ(笑)。もう最高だよね。
▼CDのブックレットにはしっかりと母が参加しているクレジットが笑

でもまあ、そんなふうに僕が練習してた瞬間がちょっとだけ“永遠に”残ったのは嬉しいよ。当時はエレクトラのレスポール・コピー(ボルトオンのメイプルネック)を、パイオニアのセンテレックスってステレオに繋いで、インディアナ州エバンズビルの僕の部屋で弾いてたんだ。
さて、そんな昔話は置いといて、“Super 70s”のメインリフを見ていこうと思う。さっきも言ったように、メインリフもBセクションも、基本的にメジャー7のコード進行が土台になってる。ヘヴィ・ロックとしてはけっこう珍しいんだけどさ。
▼アンディが当時使用していたエレクトラのギター。30分車に放置していたら盗難にあってしまい今でも探しているとのこと。

※このサイトは、アンディ・ティモンズのファンサイトです。公式ではありませんが、アンディはこの存在を知っています笑
このサイトは収益化などは一切していなく、純粋にアンディ・ティモンズを応援し、アンディの良さを多くの人と共感したいという目的で運営しています。
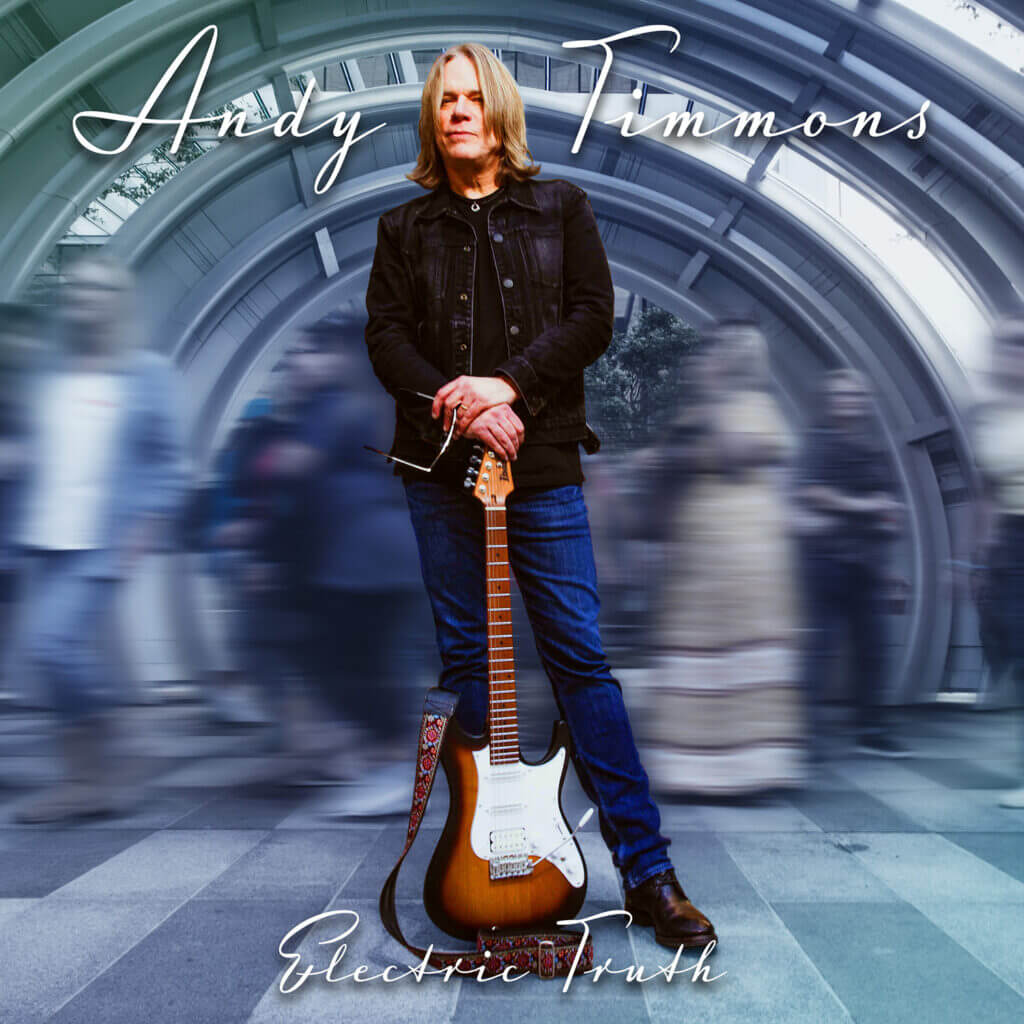

コメント