2025/05/03にYoutubeにアップロードされた
アンディのインタビューを翻訳しました。
Samo:
みなさんこんにちは。
これは Doctor Jazz Talks のサモ・シャラモンです。
今日は――
素晴らしいゲストを迎えています。
ギタリスト、そして僕自身が長年の大ファンである…
アンディ・ティモンズです!
Andy(アンディ):
ありがとう!呼んでくれてうれしいよ。
Samo:
本当にありがとう、アンディ。
出演してくれて光栄だよ。
Andy:
いやいや、こちらこそ光栄だよ。ありがとう。
Samo:
まず最初に言っておきたいんだけど、
僕は本当に、昔からずっと君の音楽のファンなんだ。
Andy:
それは本当にうれしいな。ありがとう。
Samo:
初めてあなたの音を聴いた時から、
ずっと聴き続けてきた。
だからこうして話せるなんて、とても特別なんだ。
Andy:
そう言ってくれるなんて、信じられないよ。ありがとう。
僕にとっても意味のあることだよ。
Samo:
最近、あなたはサイモン・フィリップスと一緒にやっていたよね?
そのことについて少し話してくれる?
Andy:
彼はNAMMのショーに来ててね。で、僕はCasioのブースで演っていたスティーヴ・ワインガートを観に行ったんだ。スティーヴと僕は、一緒に行ったんだよ。というのも、僕とサイモンはTamaのブースで会うことになっていたから。みんなで一緒に行って、たくさん笑って、いい再会になったんだ。
Samo:
いい思い出だね。
Andy:
本当に楽しかった。あの時一緒に過ごした時間はとても楽しい思い出だよ。これからもまた何か一緒にやるだろうね、間違いなく。
Samo:
ぜひやってほしいよ。
Andy:
あのバンド、大好きなんだ。そういう文脈で聴けるのもすごくいいんだよね。バンドリーダーとして自分が演るのとは違う音楽だし、それがいいんだ。自分はあのスタイルの曲を書くことは滅多にないけど、演るのは楽しめる。
Andy:
話は戻るけど、サイモンと最初に一緒に仕事しはじめたのは1997年ごろだよ。誰か他の人のレコード(※別のプロジェクト)が出て、そのギタリストのレイ・ラッセルがツアーに出られなくなったんだ。そこでバンドが組まれて、僕が参加し始めたんだ。
Andy:
それから僕はソロ・レコード『The Spoken and the Unspoken』ってのを作って、サイモンに曲を書いてくれないか頼んだんだ。トラックのひとつに“Astral Fishing”って曲があるんだけど、ただ「君が書くような感じで何か書いてくれ」って頼んだんだよ。
Andy:
どうなるかは分からない。Protocolみたいな形で一緒にやるのか、それとも一緒にコラボする別のソロ盤になるのか。まだ分からないけど、いいものになるだろうし、僕もたくさん学べると思ってる。あの人はスタジオでの経験が本当に豊富だからね。
Andy:
それと、サイモンには色んな話があってさ、ジェフ・ベックとかあの辺の話をたくさん持ってるんだ。君、彼にそういうこと聞いた?
Samo:
もちろんだよ。
Andy:
彼はジェフのことを延々と話すのが大好きだった。ピートのこともね。そうだ、サイモンは偉大なギタリストたちと一緒に演ってきたんだ。彼が関わってきたギター史の話は膨大だよ。今はルカサーとも親しい友人だし、僕もルカサーとは本当に仲がいいんだ。サイモンとジェフの仕事の話を聞くのはいつも楽しかった。ジェフがアンプに繋がずにエレキで遊んでるだけで、音色がもうすごくて、それだけで感動するって彼は言ってたよ。
Andy:
だから、サイモンが僕を選んでくれたってことを軽くは受け止めていない。彼が一緒に仕事してきた面々を思うと自分には大きな責任があるし、ある意味高いハードルがあるって分かっている。もちろん僕は彼らにはなれないけど、自分なりのベストでいるしかない。それをサイモンから学んだことも多い。彼の仕事ぶり、スタジオやライブでの立ち振る舞い、物事を方法論的に進めるやり方──ただしそれは命令的ではなく、「仕事がある、さあやろう」というタイプなんだ。そういう点を見て学べたのは、自分がバンドリーダーとして、どんなスタジオの状況でもより良くやる助けになった。
Samo:
なるほど。
Andy:
最初にサイモンと仕事したのは1993年、NAMMショーのときだよ。話はかなり遡るね。Ibanezが自社の著名なロック・ギタリストたちを集めて一晩のショーをやろうと計画していて、それが“Axe Attack”というイベントだった。
Andy:
出演者はすごかった。スティーヴ・ヴァイ、ジョー・サトリアーニ、ポール・ギルバート、レブ・ビーチ、アレックス・スコルニック、ショーン・レーン(彼は短期間Ibanezのエンドーサーだった)など。で、全員を支えるハウスバンドが必要だったんだ。
Andy:
最初に声がかかったのはサイモン・フィリップスで、彼は参加に同意した。ベーシストにはGerald Veasley(ウェザー・リポートのプレイヤー)に声がかかっていた。そして当時Ibanezで僕と関わっていた男、Bill Kaminskyって人が僕の名前も挙げてくれたんだ。僕はまだDanger Dangerにいたけど、ソロの素材──一枚目のレコード──が出ていて、彼らは僕がどう弾くかを知っていたし、フュージョン的なこともできるって分かっていたんだ。
Andy:
サイモンは参加を承諾したんだけどただし条件があってね。つまり、ハウスバンドとして他のギタリストたちの演奏をバックアップするけれど、合間にはサイモン自身のフュージョンの曲も演奏する、というアイデアだった。だから僕は多くのギタリストと一緒に演奏できただけでなく、その合間に彼のフュージョン的な曲──後のProtocolのような曲──も弾いたんだ。彼は僕が非常に準備して来て、他の誰の楽曲でも弾けることを見て取ったんだよ。
Andy:
たとえばサトリアーニはバンドでリハできないことがあったけど、僕は「曲は全部分かってるよ」と言えた。1993年のその夜は大成功だった。もし人々が僕をDanger Dangerでしか知らなかったとしても、その夜彼らは僕を全く別の側面で見た。もっと大人向けの音楽──僕がロックプレイヤーとして育ったけれど、ジャズにもハマりフュージョンを愛するようになって、キャリアが開花し始めたときに色々なことを受け入れるようになったんだ。「全部受け入れれば“イエス”と言える」。例えばカントリーの仕事が来たら「いいよ」って言えるように、必要ならテレキャスターを用意する、みたいなね。
Andy:
サイモンとのチャンスは素晴らしかったし、他のどのギグと同じように真剣に取り組んだ。とにかくできる限り準備して、ベストを尽くして臨んだんだ。
Andy:
それから数年後──さっき言ったように、彼は新しいレコードを作って、長年のメインギタリストがレイ・ラッセルだったんだけど、その人がツアーに出られなくなった。彼は英国ベースの素晴らしいセッションギタリストで、サイモンと多く仕事をしていたんだけれど、個人的な理由でツアーに出られなかったんだ。そこでサイモンは「アンディはどうだ?」と言って、「彼は弾けるし、準備して来る」と。だからサイモンにとって僕を呼ぶのは簡単な決断で、「よし、行こう」となったわけだ。
Andy:
それが教訓なんだよ。あのギグが、最も奇妙な形でオリビア・ニュートン=ジョンの仕事につながった。人は君の仕事ぶりを見て、音楽を敬っているかどうか、ツアーで一緒にやれる普通の人間かどうかを判断する。これも重要だよ。誰だって試されることはある──僕だって天使じゃない──でも、シンプルにやるべきことをやって、人に失礼をしないってことはたやすくできるはずなんだ。そうした小さなことが積み重なってキャリアになる。たとえ地元のパブでの小さなギグでも曲を覚えてベストを尽くすこと、その瞬間が本当に重要なんだ。明日何が起きるか分からないし、昨日やったことは変えられないからね。
Andy:
だから何事も敬意を持って扱うこと。まず自分をがっかりさせたくないんだ。利己的に聞こえるかもしれないけど、「自分が関わるものをどうすれば最高にできるか」を考える。曲を知ることや、弾かない判断をすること、あるいは「今はボリュームつまみが味方だから下げよう」みたいな直感を活かすこと──そういう小さな積み重ねが大きいんだ。サイモンとの関係はその好例で、あの一回のギグが複数のレコードやツアーにつながり、彼がマネージメントに「オリビアがギタリストを探してる、誰がいい?」と訊かれたときにすぐに「アンディに電話しろ」と推薦してくれた。結果的にそれが15年間にわたる僕の主要な収入源になったんだ。
Andy:
それに彼女(オリビア)は仕事しやすい人だった。僕は彼女が好きだし、彼女はちょっとずつ(数週間単位で)仕事するから、僕はサイモンのバンドも続けられたし、自分のキャリアも両立できた。そういうギグは大切にしている。ジャンルも様々で、カントリーだったりポップだったりしたけど、彼女はスタンダードを演るのが好きだった。とにかく楽しいし、一緒にいる人たちも素晴らしかった。だからとても良い関係になったんだ。
Samo:
ところで、サイモンのリズムへの対処ってどうしてたの?ライブで観たとき、君は彼がどんなに複雑な拍子をやっても滑るように乗りこなしていたけど、それは偶然とか運とか?
Andy:
(苦笑)これは引用していいよ。僕は考えるのが好きじゃないんだ。数えたり形式にとらわれたりするのは好まない。感じたいんだ。だから出来るだけ内面化しようとする。だがサイモンの音楽は危険でもある。15や16や11/16みたいなのがあって、時には「シャッフルでやらない?」って場面もある。彼の音楽は三度(thirds)を中心に回っていることが多い。僕の和声の聞き方やメロディの聞き方に関係してるんだ。多くの曲で彼は規則正しいタイムの基盤を壊すし、たとえ15/16であってもフレーズが小節線をまたいで演られる。だから常に注意してないといけないし、和声的にも「このコードで何を弾けばいいのか分からない」って部分もある。でもそれが別の本能を育てるんだ。僕は未知のやり方でナビゲートしなければならない。バンドの中で「自分は他の人よりうまく弾けてないんじゃないか」と感じる瞬間も多かった。でも僕はバンドにある種のロック要素をもたらしていたし、それは有益だったと思う。それが僕のスタイルだし、そういう面も歓迎されたんだ。サイモンとその楽曲には、僕にとって親しみと敬意しかない。普段やらない音楽に挑むことは常に健全だし、彼の音楽は複雑でありながら美しいんだ。彼が書く方法も面白い。彼はキーボードに座って探し求めるフレーズを見つけ、それをプログラムしてメロディを作っていく。僕にはいつもデモMP3やチャートが渡されるから、それを解釈して演るんだ。もちろん解釈の余地はあるけど、素晴らしいメロディがいつもある。キーボード上で書かれるのと、実際に物理的に楽器で書くのとは違うことも多い。時には音程の間隔が難しかったりもする。
Samo:
作曲はどうやってるの?今日も生徒さんと一緒に君の曲を教えていたんだ。Electric Gypsyをやったよ。あの曲の作り方はトリッキーだって聞いてるけど。
Andy:
あの曲は、開頭のリフ、メインテーマがジャムセッションの中から出てきたんだ。僕はDanger Dangerにいた頃ニューヨークに住んでいて、キーシー(キーボード)の実家──彼の育った家──に居候してた。彼の兄カールがそこに住んでいて、すごく良いドラマーだった。時々ジャムをしていて、そのときに僕は『Electric Gypsy』というジミ・ヘンドリックスの本を読んでいたんだ。初期90年代のことで、その本はヘンドリックスの精神をよく捉えている気がして、彼の民族的背景(ネイティブアメリカンの要素)などについても知れて、いろいろと吸収していた。そういう気分のときにあのリフがふっと出てきたんだ。
Andy:
当時はテキサスにもよく帰っていて、バンド(1988年から一緒にやっているメンバー)と録音していた。僕はそのリフを強いと思ったけれど、最初は「ボーカル曲にするかも」と思っていた。マイク(ベース)に聴かせたら「いや、これはこのままでいいよ」と言われたんだ。レコーディングしてみると、最初は単純なギター小品に思えた。でも年を経てYouTubeで色んな人がカバーするのを見て、誰かが僕の曲を学んでくれているという事実がとても謙虚に感じられた。だけど、みんなが完全に理解して演っているわけではないことも見た。自慢するつもりは全くないけど、あの曲は結構手強いんだ。譜面上はシンプルに見えても、ダイナミクスやアーティキュレーション、音符の背後にある感情や意図が重要で、それを表現するのが難しい。自分でも後になって「あ、これにはもっと深みがあったのか」と気づくことがあった。書き方というよりは、リフが現れた瞬間に認識して、それを逃さずに育てるのが大事だと思ってる。多くの曲は、練習してる最中に即興的に出てきた旋律やコードの組み合わせから始まることが多い──脳があまり働く前の瞬間ね。僕はそのプロセスを“melodic muse(メロディック・ミューズ)”というコースにまとめたことがある。曲がどこから来るのかを扱う内容で、結局のところ僕らが生涯で愛して学んできた音楽が基礎になっていると思う。影響を受けたものを吸収しておけば、耳で似たものを聞き取って具現化できる──それが意識的であれ無意識的であれね。ただし盗作には気をつけないといけない。
Andy:
たとえば「あるコードの上である音を聞いたら、次に何を聞きたいか本能的に分かる」──そういう問いと応答の関係があって、時にはそれを避けることもあるし、まっすぐ行くこともある。そういうやり取りがゲームのようで面白い。最近はシンプルなソロ曲をたくさん書いていて、自分を修正しながら進めている。『Here Lies the Heart』みたいな曲はショパンに敬意を表して書いたもので、シンプルなメロディを好むけれど転調を多用したりする。ショパンやジョン・レノンのように「一音のメロディラインを置いて、和音の動きで表情を作る」考え方が好きなんだ(『Lucy in the Sky』とか典型的だね)。作曲者としての声を見つけることと即興奏者としての声を見つけることは、僕にとってほぼ同じことなんだ。
Andy:
ビル・エヴァンスのドキュメンタリーがあって、それでハリー・エヴァンスが兄ビルにジャズと即興のプロセスについてインタビューしている。ビルの言葉で直感的に分かったのは「即興と作曲は同じだ」ということ。僕の解釈では「自分が聴きたいものを演奏・作曲しているだけ」で、それはとても自己中心的な行為でもある。理想は「自分が聴きたいソロを自分が弾いている」ような感じだ。もちろんヒーローたちのように聴こえることはできないけど、そこを目指すんだ。ビルの言葉で面白いのは「ジャズでは1分の音楽は1分で作られるが、作曲では1分の音楽に1年かかることがある」という点だ。偉大な作曲家のいくつかは瞬間的に生まれるものもある。僕も時には一瞬で来るし、時には何度も手を入れて時間をかけることもある。多くの作曲家が言うように、本当に良い曲は自然に湧き出ることが多い。考えすぎる前に、自分は何を聴きたいのかを大事にして、耳を最重要ツールにすること。だから僕はこのプロセスを“oral act(口頭的行為)”と呼んでいる。本能的に出てくるものだ。
Andy:
ポール・マッカートニーはその好例だ。理論を知らなくても大量に曲を覚えていることでメロディを作っていく。彼がスタジオで即興でメロディを口ずさんでそれがそのまま使われることも多い。ビートルズの逸話を追うと、彼らはとにかく貪欲に色んな音楽を吸収していた。ポップだけじゃなくショー・チューンや前衛芸術、ジャズなども聴いていた。そうやって自分が形作られていく。もし一人の作曲家やミュージシャンだけに固執してしまうと、その人に似たものばかりになるけど、それが魂を満たすならそれでいい。僕は常に「他に何を学べるか?」を考えていて、ある時はトム・ペティの番組で50〜60年代のR&Bやブルースを聞き漁ったり、別の時はジャズに戻って深堀りしたりする。今はジョナサン・クライスバーグをよく聴いている。彼は素晴らしいトーンとプレイを持っている。ジョナサンの演奏にはメセニーの影響も感じられるけど、非常に彼自身の音だ。
Samo:
(続けて)彼はとても良い音を出しているね。で、そのレコードの最初のトラックをShazamで調べたら“Juju”って曲だった。ウェイン・ショーターの曲だよね。それから「50 Ways to Leave Your Lover(君を離す50の方法)」の素晴らしいカバーもあって、彼はあのジャズギターで少し歪みを乗せて、僕が“スティールドラム・パッチ”と呼んでいる音色を出していた。多分POG(オクターブ系)に上下のオクターブを混ぜてるんだろうけど、とにかくカッコよかった。僕もいくつかフレーズを拾って「よし、あれを取り入れよう」と思ったんだ。音楽の趣味は常に変わるから、ある時はマディ・ウォーターズで次の日はジョナサンを聴く──どちらにも大きな美しさがある。
Andy:
(WestやBarneyの話へ)もちろん、あの古いスクールの人たちを学んだよ。スイングもできる。ジャズ・ボックスはここにないけどね。子供のころ(5歳くらい)に独学で簡単なことを覚え始めて、16歳のときに最初の先生についた。既にプロで弾いていたから、先生は単音の読み方から教えてくれた。オアフ・ギター・メソッドというちょっと古い教本を使ってね。それで先生は僕がクラブで弾いているのを見て、バーニー・ケッセルみたいに弾いていたからレコードを貸してくれた──Shelly ManneやRay Brownといった連中のレコードをね。Joe PassやHoward Roberts、Oscar Petersonも。そこからコードを覚えたり耳を養ったりしていったんだ。バーニー・ケッセルの弟子に当たるロンサムな人、ロン・プリチェットって先生がいて、今でも80代で元気なんだ。彼は僕の可能性を見て育ててくれた。あれがなかったら70年代のアリーナ・ロックばかりで終わっていたかもしれない。だけどその時に「こういうことができるんだ」と気づいて、もっと学びたくなったんだよ。
Andy:
最近はジョージ・ベンソンとちょくちょく会う機会があって、すごく恵まれたよ。DreamCatcherのギターキャンプがあって、ジョージが初めてそれをやることになったんだ。ポール・ギルバートやスティーヴ・ヴァイ、サトリアーニと一緒にやったこともある会社なんだけど、今回はジョージが主役で、トミー・エマニュエル、リー・リトナー、ジョン・スコフィールド、スタンリー・クラーク、コーリー・ウォン、スティーヴ・ルカサー、アル・ディメオラ……そして僕も参加していた。どうやって僕がそこに混ざれたのか分からないけど、Ibanezを通じてジョージに会う機会があって、彼の『It’s Uptown』って初期の好きなレコードにサインをもらったりして、これまでに7〜8回は会っているけど、今回は彼が実際に僕の演奏を聴きに来てくれた。ジョージは本当に優しくて、一緒に居るのが楽しい人だよ。彼はバーニー・ケッセルの大ファンだって話もしてくれた。もちろんチャーリー・クリスチャンから影響を受けているし、ウエスト(Charlie Christian?あるいはWes Montgomery)もそうだ。
Andy:
ジョージの自伝は読んだ?彼がニューヨークに行って19歳でジャック・マクダフのバンドにいた頃の話とか、本の中で彼の声がそのまま飛び出してくるように書かれていて、本当に良い本だ。マネージャーのステファニー・ゴンザレスは僕のことを気に入ってくれて、今回のキャンプに参加できるようにしてくれた。だからジョージが僕のコンサートを観に来てくれたんだ。会場ではアイザイア・シャーキーって若いプレイヤーもいて、彼はシカゴ出身でジョージ系の要素も持ちつつ自分の道を行っている。彼はフンキーでソウルフルな曲をやっていておすすめだよ。
Andy:
(Georgeについて)ある夜、僕が演奏しているときに彼はシャルドネを飲みながら座ってて、アイザイアと僕と3人で「これ信じられる?」みたいな顔をしてたよ。僕がジョージに聞いたことの一つに「君はあのトラックが好きなんだよね?」ってのがあって、彼は「もちろん好きだよ。あのレコードは一日で作ったんだ」と言ってた。で「リズムギターは誰?」って訊いたら「フィル・アップチャーチだよ」って。ドラムは誰かと思ったら「スティーヴ・ガッド」だって。だからあのアルバムの感触があれほど素晴らしいのも納得だよね。彼のソロは毎回聴くたびに驚かされる。グルーヴ、フィール、タイム感が全部入ってる。僕も彼があのトラックを好きなのを聞いて嬉しかったよ。
Samo:
なるほど。あなたの演奏はサイモン経由でしか聴いたことがないから、こういうジャズの側面があるとは知らなかったよ。
Andy:
ジャズ要素は自分の演奏の中に常にあるよ。変化に対応するための時間感覚や和声のナビゲーションが身についているからね。単に「Aキーで弾き倒す」ってやり方とは全然違う。ロックの多くのプレーヤーはそれで凄く高いレベルで出来るけど、変化がある楽曲を人の間を縫って弾くというのは別物なんだ。251の進行(ツーファイヴワン)をどう扱うか、7度や3度をどう使うかって意識はメロディに大きく影響する。ビートルズの作曲や60年代ポップの基礎に、チャーリー・パーカーやキャノンボールのスイング感やアーティキュレーションが混ざって、自分のフレーズに出るんだ。実際に「オムニブックを弾く」ようなことはしていないけど、あの道筋は通ってきたし、毎日スタンダードを1時間弾くのが僕の日課になっている。iReal Proみたいなアプリを使ってプレイすることもあるよ。いつもボサや色んなスタイルで弾けるプラットフォームを用意しておくんだ。
Andy:
マイク・スターンが出てきたときの衝撃は大きかった。彼やメセニー、ルーサー・ヴァンドロス(?という言い回しのようだが文脈はLuther VandrossやLarry Carltonら)──彼らはロックのエネルギーも持ちながら、クロマチックな要素も入れていた。初めてマイク・スターンを観たのは『We Want Miles』/『Man with the Horn』の頃で、1982年。当時マイクはストラトを弾いていて、雑多なヒッピーみたいな風貌で、でもその「ファットタイム」──マイルスが言った彼のリズムのこと──がすごかった。彼のソロやバラードの美しさには本当に感銘を受けたし、彼は今でも大好きだ。僕は彼とエリック・ジョンソンと一緒にステージに上がったこともある。ある日、彼らのダラス公演に顔を出したら「お前も弾くか?」って言われて、たまたまギターを持っていたからステージに上がって、Red Houseを一緒にやったんだ。客席のビデオを探せば映像が残ってるはずだよ。
(舞台上の様子)アンソン・フィグがドラムで、クリス・マーシュがベース。ステージのギターアンプはトラックから出したフェンダー・ツインみたいな簡素なもの。僕はJHSのATペダルを持っていただけで、エフェクトも少なかった。彼らがグルーヴを始めると、マイクがアンソに耳打ちして戻ってきて「Jean Pierre知ってるか?」って聞かれた。ビデオを見ると僕がほとんど倒れそうになる場面が映っているはずだ──そんな曲を彼と演るなんて信じられなかったからね。『Man with the Horn』の“Fat Time”のリックを解明するのに何週間も費やしたんだよ。クロマチックなフレーズが多くて、でもバラードでの歌心も凄い。彼のナイロン弦でのプレイや最近のアルバムでの深さにも感動した。彼とバークリーで時間を共有したこともあるし、メロディの方向性には共通点を感じる。
Andy:
(続けて)もし僕のメロディ的なアイディアについて話すなら、そこには他の多くの人の影響がある。暖かいネックPUでトーンを落として弾くと、自然と彼らの匂いが出ることがある。それが良い方向に浸透してくれればいいと思っている。とにかく彼らへの愛は尽きないよ。
Samo:
最初のCDについて話そうか。Ear Ecstasyのことや、その中の“No More Goodbyes”って曲は1988年に作ったという話だね。あの時はどんな感じだった?
Andy:
最初のCDの一曲に“No More Goodbyes”があって、あれは1988年に書いた“タイプ曲”への挑戦だった。結果的に僕らはラッシュみたいな感じになってしまったけど(意図した方向とは違った)、エレキのソリッドボディを固体ステートのアンプで鳴らしてたから音色はいまから見ると違う部分もある。でも当時の録音はバンドのサウンドとしては良いものになっているし、リードギターの一部は今ならもっとやれるなと思うところもあるけど、あれは「自分の本質」を表している作品だった。Danger Dangerにいる間もテキサスに戻ってはデモのつもりで録音していた曲があって、それがそのままレコードになった経緯がある。Reb Beach(Winger)とは親しくなって、彼にデモを聴かせたら「これが君のアルバムだ。出せ」と言われたのが後押しになった。
Andy:
Danger Dangerではたくさんシャレッド(速弾き)もやらせてもらった。ソロパートではGrover(?)の引用をやったりして、若いファンがどう思ったかは分からないけど(苦笑)、でもエリック・ジョンソンへの敬意や、カントリー、メセニーの影響も所々出ていた。新しいレコードには少しまたシャレッド寄りのトラックが戻ってくる部分もあるけど、いつもメロディと曲作りの糸は貫いているつもりだよ。
Samo:
ツアーの話に移ろう。2月にイタリア(1公演はオーストリア、残りはイタリア)でツアーが始まるって言ってたよね。その後3月には東南アジア(日本、中国、台湾、タイ)も回るんだよね?
Andy:
そうだよ。ツアーは楽しい。ショウも、人も、食べ物も好きだし、でも家にいるのも好きなんだ。旅暮らしは自然なライフスタイルではないよ。人生の大半はステージ以外の“22時間”の方が大きい。退屈で単調になりがちだし、ドラッグや酒で問題を抱える人もいる。だから僕は適度に分けてやるのがいいと思ってる。演るのは大好きだし、バンドのみんなも優しくて人当たりが良い。イタリアに行ったらコーヒーや食べ物を楽しむのも大きな楽しみだよ。
Andy:
今は61歳で、残りの人生の優先順位は「ミュージシャンとして、作曲家として上達し続けること」だ。もっと作品を残したい。実は新しい曲はたくさん書いているが、自分で完璧だと思えるまで出せないところがある。もっと気前よくリリースしたいんだ。ポール・マッカートニーから電話来たらもちろん出るし、サトリアーニとかがツアーやるなら参加したい。でも単に日々ツアーで消耗するのは今の自分には一番健康的ではない。家族も大事にしたい。妻と20歳の息子がいるからね。
Samo:
ロングツアーでどうやって気持ちを保ってる?僕の最長は17日間で17公演だったけど、10公演目くらいで自分にうんざりしてしまったよ。
Andy:
それは普通のことだよ。疲れて飽きるのは人間として当然だ。解決策は、変化をつけられるバンドメンバーと一緒にいること。僕のバンドも毎晩少しは即興を入れたり変える部分がある。僕が作ったソロの部分は演るのに困らないし、その瞬間に自然に出る。即興の部分は新鮮さを求めるから、たとえば誰かの小さなメロディやリックを学ぶだけでも気分転換になる。僕はジョナサン・クライスバーグのパターンを今日の後で学ぶつもりなんだ。そういうちょっとした新しいものを取り入れると、また気持ちが戻る。あとスライス・オブ・ピザを食べるとかね(笑)。
Samo:
その通りだね。元気でいてくれよ。
Andy:
ありがとう。
Samo:
(挨拶)ありがとう。
アンディ・ティモンズ — 本質的なポイントまとめ
以下はインタビューでアンディが強調していた重要なポイントを抜粋・整理したものです。発言の背景や具体例(Axe Attack、Simon Phillips、George Benson、Mike Stern、曲作りのエピソード等)も併せて示します。
-
準備がすべて
-
いつでも「超準備(Uber prepared)」で臨むことが、思わぬチャンス(Simonとの再会→ツアー、Olivia Newton-Johnの仕事など)につながる。
-
リハできない状況でも曲を把握しておけば対応できる。
-
-
どんな仕事でも“最高を尽くす”
-
小さなローカルのギグでも手を抜かない。その積み重ねが将来の大きな仕事につながる。
-
「自分をがっかりさせたくない」という自己基準で臨む(ある意味“利己的”なモチベーション)。
-
-
多様性を受け入れる(ジャンルの柔軟性)
-
ロック/カントリー/ジャズ/フュージョンなど幅広く「イエスと言える」ようにしておく。必要なら楽器や機材を変える柔軟さも大事。
-
1993年のAxe Attackでの経験が、それまでのイメージを変えた好例。
-
-
仕事の姿勢とプロ意識(スタジオ/ツアーでの振る舞い)
-
スタジオでの段取り、現場での礼儀やチームワークが長期的な信頼を生む。
-
技術だけでなく“人としての付き合いやすさ”もキャリアに直結する。
-
-
サイモン(Simon Phillips)との仕事から学んだこと
-
メソッド的に物事を進める姿勢、ライブとスタジオ両方でのプロフェッショナリズムを学んだ。
-
複雑なリズム/和声に対応する耳と感覚を鍛える経験が得られた。
-
-
フュージョン/ジャズの影響は演奏全体に効いている
-
変化に対応する能力(251進行の扱い、7度・3度の感覚など)がメロディに深みを与える。
-
毎日のスタンダード練習(iReal等で)を日課にしている。
-
-
作曲/即興は同根(“作る=その場で弾きたい音を出す”)
-
インスピレーションは「耳」「記憶」から来ることが多く、理論より先に“聴きたい音”がある。
-
「Melodic Muse」という概念/コースで、曲がどこから来るかを説明している。
-
-
曲は“瞬間に降りてくる”ことがある
-
電車/ジャム/練習中にリフやメロディが生まれることが多い。出てきたものを認識して育てる力が重要。
-
例:「Electric Gypsy」のオープニング・リフはジャム中に生まれた。
-
-
影響を受けたアーティストたち
-
George Benson、Mike Stern、Wes/West系、Barney Kessel、Beatles(Lennon/McCartney)など幅広く吸収。
-
彼らの“耳で学ぶ”姿勢、即興力、メロディの構築が自分の基礎になっている。
-
-
実践的な謙虚さと不安(偉大な人ほど不安を持つ)
-
多くの偉大なプレイヤーは内面に不安を抱えている(例:Holdsworthの話)。だからこそ練習を続けるしかない。
-
50代になってようやく「ベスト・バージョンの自分でいる」ことの重要性を理解した。
-
-
日々の練習と“楽しさ”のバランス
-
毎日のルーティン(スタンダードを弾く、スケール、即興など)を維持しつつ、楽しむことを忘れない。
-
練習が苦痛にならないように“遊び”要素を入れる(練習→即興→作曲の流れ)。
-
-
ツアー/生活のバランス
-
ツアーは楽しいが長期だと疲弊する。家族や健康、制作活動とのバランスを重視している(61歳の現在の優先事項)。
-
適度なツアーは続けるが「ずっとオン・ザ・ロード」は望まない。
-
-
作品をもっと残したいという意欲
-
常に曲を書いているが、納得できるまでは出さないタイプ。もっと気前よくリリースしていきたいという目標を持つ。
-
-
実例で示すメッセージ
-
小さな一回のギグ(Axe Attack)が重要なキャリアの分岐点になり得る。準備・人間性・プロ意識の積み重ねが未来を作る。
-
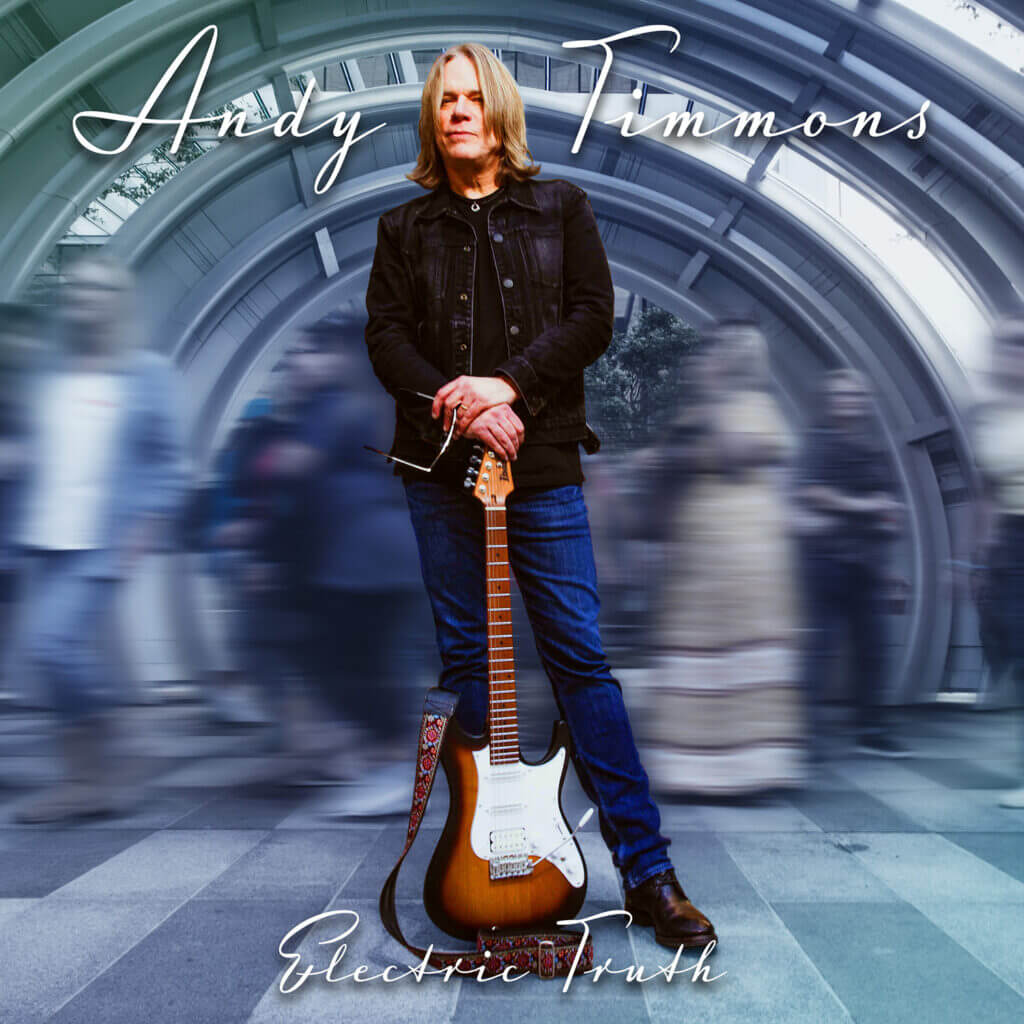

コメント