2024/02/27にYoutubeにアップロードされたアンディとの対談動画を、AIを使って翻訳しました。
アンディのギターを弾くきっかけから、ソロバンドまでの道のり。
ATペダルやBBプリアンプができた裏話。
サイモンフィリップスや、オリヴィアニュートンジョンと仕事を一緒にやるようになった経緯。
最近(2024年2月時点)の最新ペダルボードとペダルの解説。
という、1時間に渡って繰り広げられた対談は、とても濃い内容でこのインタビューだけでも、アンディーのディスゴラフィーから、音楽やギター、バンドに対する考え方、機材へのこだわりなどが聴ける本当にスペシャルな対談です。
ぜひ、読んでみてください!
登場人物は下記の3人です。
●アンディ・ティモンズ
●Grant Klassen (Goodwood Audio)
● Brian Omilion (Omilion Audio) ※いつもアンディのペダルボードのセットアップをしている。
※AIの文字起こしなので、それぞれのトークに分けるのが難しくて、誰がしゃべっているかがわかりづらい点があることをご了承ください。
ところどころで、このポッドキャストのスポンサーの紹介がGrant(グラント)から入ります。
▼アイスブレイク
僕コーヒーがあるから大丈夫、いけるよ。あと、通称“ヴェンティ水”(笑)もある。
ところでアンディ、君って朝型の人? それとも…?
いや、完全に朝型なんだ。マジで朝がいちばん好き。起きてコーヒー飲んで練習して…ていうのがいつものリズムだから、今もちょうどそんな感じだね。
いいね。僕はこのエンバー・カップを使ってて、めっちゃ大事なんだ。コーヒーを温かいままキープできるんだよね。
おお、それいいなあ。僕より妻が必要かも。うちの妻はコーヒーを飲むのに2時間くらいかかるからさ。教えてあげなきゃ。僕
僕そうそう、2時間かけてコーヒー1杯飲む人なんだよ。だからこれ教えなきゃ。
絶対教えたほうがいい。これ、いまポッドキャストでいちばん大事な話題かもしれない(笑)。アプリで温度管理できるコーヒーマグなんだよね。
僕なんてコーヒーいれてギターを手に取って、ふと気づくと30分とか45分とか経ってて、“あれ、これアイスコーヒーになっちゃうじゃん”ってなること多いんだ。でもこのマグのおかげでまだあったかいんだよね。
最高だね。それ以上ないくらいのプレゼントじゃない?
やばい、もう僕の財布が軽くなりそう。まだ本題始まってないのに(笑)。
いや、これほんと大事なんだ。ペダルより大事かもしれない。ここまで話したのも貴重な情報だよね。僕、エンバーのスポンサー獲得しなきゃ(笑)。
そうだよ、エンバーのマグを広めよう。
ちょうどいいから、これを今回の導入にしようかな。“新しいコーヒーラインが始まりました!”みたいな。
コーヒーカップも出したらいいんじゃない?
…さて、おはようございます、こんにちは、こんばんは。世界中どこで聴いててもようこそ“Chairman of the Boards”のエピソードへ。今日はとてもスペシャルなゲストを迎えてるんだけど、僕の親友、アンディ・ティモンズが来てくれてます。
おはよう、ブライアン。いろいろ話していこうと思うよ。で、グラントもいる。来てくれてありがとう。
見てのとおり、今日はメンバーが1人足りないんだけど、まあ大丈夫。アンディが助けてくれる。
メイソンは…
僕は名誉チェアマンって感じだよね。
そうそう、メイソンのキャラをちょっと代わりにやってみる? どう?
どうかな、真似できるかな。まあとにかく彼はいま他所で撮影とかしてる。
そうそう、メイソンはいま別のアーティストと動画を撮ってるんだよね。別の相手がいるってわけか、なるほど。
いらっしゃい、アンディ、嬉しいよ。
こちらこそ。実はね、僕が住んでるところはブライアンのショップ(サンクチュアリ)から車で10分くらいだから、よく顔出してるんだ。頻繁にお邪魔しすぎかもね。でもいつも親切に対応してくれてありがたい。
近いのって、良し悪しあるだろうけど、僕としてはちょっと思いついたときにすぐ行って“このセッティング直して”とか“これ動かないんだけど”とか頼めるし、あるいは“木曜までにペダルボード組み直さないといけないんだ、やろう”みたいな。水曜の夜に言う、みたいな(笑)。
ブライアンは僕にとって最高の“ピットクルー”なんだよね。すごく感謝してる。
サンクチュアリ自体も大好き。スポンサーとしてじゃなくて、本当に近くにあるのはありがたいんだ。
そうだね。サンクチュアリ自体もそうだけど、僕にとって近くにあるのはラッキーなんだ。
さて、アンディのバックグラウンドをちょっと話してもらおうかな。どういう経緯でギター始めたのか、とか。
ああ、うん、いいよ。いつ弾き始めたかって話ね。人によって全然違うよね。5歳でもめっちゃ弾ける子とかいるし。僕も今5歳の子がいるけど、どうやったらそんなことになるのか想像もつかない。
そうそう、若い子でもプロレベルみたいな子がいるから驚くよ。うちの息子はもうすぐ20歳なんだけど、16歳でようやくギター始めた感じ。昔から“息子さんもう弾いてる?”って聞かれてたけど、“いや、つい昨日生まれたばかりだし、ちょっと待ってよ”みたいな(笑)。結局16歳でようやく興味を持ったみたい。パンテラとかスリップノットとか聴こえてきて“おお、そうきたか”って。
僕は5歳くらいから始めたんだ。
もちろん当時はYouTubeで速弾きしてたわけじゃなくて(笑)、プラスチックのオモチャギターでモンキーズの“I’m Not Your Stepping Stone”を1弦だけで弾くみたいな感じ。まだ“Smoke on the Water”が世に出る前だったからね。要するに僕、あの曲が生まれる前からギター触ってるくらい年寄りなんだよ(笑)。
“Smoke on the Water”は初めて覚えた曲だなあ。何回も弾きすぎて曲を焼き尽くした感あるよ。
あの曲ってピアノでいう“チョップスティック(猫ふんじゃった)”みたいなもんだよね。誰でも最初にやるみたいな。
僕でも曲全体弾ける? いや、リフ止まりなんだよ。今弾いたのが全部かと思ったら、実は違うんだね、みたいな(笑)。まあ、そこまでで“ラジオ・エディット”かもね。
もうあのリフをひたすら繰り返す曲なんだよね(笑)。
僕は4人兄弟の末っ子で、兄たちは僕より4歳ずつ上なんだ。いちばん上は12歳上になるから、1963年生まれとか、あとの2人はその中間って感じ。みんな音楽大好きでレコード買いまくってたし、家にはシルバートーンのアコギみたいなのが転がってた。アメリカの60年代の家ならわりとありがちかもね。
で、僕はいつも兄たちが弾くのを見てて真似してたし、母も僕がギター好きなの見てオモチャギター買ってくれたんだ。プラスチックの弦だけどメロディを弾けて、そのうち兄たちに教わったり、彼らがいないときはこっそり部屋に入って練習したりして。
13歳のときにはもう最初のバンドに入ってた。ずっと独学で、70年代のロックを聴きまくって覚えたんだよね。ビートルズも好きだったけど、最初に自分で買ったレコードはKISSの“Alive!”とか。エース・フレーリーから学んだことは大きかったし、彼らが半音下げチューニングだって気づいたときは衝撃だった。それに誰かにバレーコードとペンタトニックだけ教わったら、もう一生分音楽作れそうなくらい世界が広がったんだ。
レコードプレーヤーと耳だけが頼りで、でもギターって見た目もカッコいいし音も最高で、ずっと触ってたいって思ったんだ。今でも変わらないよ。
それが僕のスタート。弾き始めてから止まらない。もしもっと詳しく聞きたいならいくらでも話すけど、ざっくり言うと、16歳のときに初めて先生についたんだ。もうその頃には“音楽で生きてく”って決めてたからね。先生はジャズ系の人で、バーニー・ケッセルみたいなプレイをする人。ジョー・パスとかバーニー・ケッセル、あとピアノのオスカー・ピーターソン(いまオスカー・マイヤーって言いそうになったけど…笑)を教えてくれた。
そうやって耳が育っていって、大学に入る頃になって、地元のエバンズビル大学でクラシックギター専攻があるって知ったんだ。
当時はバンドが地元でうまくいってたから、町を離れるって選択肢はなかったし。クラシックギターなんて何も知らなかったから、とりあえず図書館行ってセゴビアとかジュリアン・ブリームのレコード借りて、いろいろ試してみた。
クラシック用のナイロン弦ギターがなかったから、エレキギターでオーディション受けたんだよ(笑)。でも向こうは“あ、ちゃんと弾けるね”って認めてくれて合格して。そこでクラシック音楽に2年間どっぷり浸かることになった。それまでは何も知らなかった世界だから面白かった。
イタリア出身のレナート・ブトゥーリっていう素晴らしい先生がいて、そこで国際的な刺激も受けつつ、一方でマイアミ大学の話も耳にしてたんだ。そこはDregs(ディキシー・ドレッグス)が結成された場所で、僕が大ファンだったスティーヴ・モーズとか、パット・メセニーも行ってたらしい。メセニーなんか学生の時点で1週間後には教員になってたとか(笑)。
要するに僕はただのロックギタリストで終わりたくなくて、マイク・スターンとかラリー・カールトン、ロビン・フォード、あとルカサーとか聴いて“ロックにすごいトーンとグルーヴがあるのに、ジャズ的なインテリ要素も混ざってる”みたいなのに憧れたんだよね。僕がもともとジャズの基礎をちょっとかじってたのもあって、“もっと知りたい”って思ったんだ。
で、マイアミからどうしてテキサスに来たかというと、そこにスティーヴ・ベイリー(今バークリーでベース科の責任者)とレイ・ブリンカーっていうドラマーがいて、二人ともジャズ畑なんだけどロックバンドやりたいって言うから誘われたんだ。それでデントンに引っ越して、僕は大学には行ってないけどその町でよく過ごして。そこで1988年にアンディ・ティモンズ・バンドを結成したんだ。
そのデモテープが縁でDanger Dangerに入れて、あの業界の一端を知るようになったってわけ。
当時はMTVが音楽流してて、MTVに出ないとラジオで流してもらえないってくらい、ビデオが大きい影響力を持ってた時代なんだよね。僕らはその終わり頃に滑り込みで入った感じで、貴重な経験だったけど、それで気づいたのは“自分が理想としてたものと全然違う”ってこと。僕が好きなのは“ギターを弾くこと”であって、そこに没頭したいのに、あれは企業色が強い世界だったんだ。
Danger Danger自体は要求されたコンセプトに合うバンドで、そこに参加できたのは面白かったし、まさにロックスターの夢が叶った気分だった。実際KISSのオープニングを務めてアリーナを回ったりして、すごい体験だった。だけど自分自身はもっと“自分の音楽を書いて弾きたい”って思いがあったから、そのバンドがひと段落したとき、僕はニューヨークからテキサスに戻ったんだ。うちのバンドは88年から録音もしてたし。
それで、“これはデモテープかな”と思ってたものをまとめたのが“Ear X-tacy”っていう初めてのソロアルバムになって、それが僕のキャリアの新しい段階の始まりだった。“自分って何者なんだろう”って模索する時期だよね。僕はなんでも好きだし、いろんなジャンルをやりたいタイプだから。
世間的にはロックギタリストとして知られてるけど、実はオリビア・ニュートン=ジョンと15年ツアーした人でもある。サイモン・フィリップスとやったときと同じくらい楽しくて、音楽的には全然違うけど、両方とも本気でやればチャレンジングだし、めっちゃ楽しいんだ。
それだけじゃなくてボサノバのアルバムも作ったりして。僕はいろんな音楽が好きだからね。ロックファンからすると“なんでそんな幅広いの?”って思うかもだけど、僕が好きなアーティストって、ファンが何を望んでるかに左右されず、自分のやりたいことをやる人なんだ。
トッド・ラングレンなんかいい例で、往年の曲をライブで弾かなきゃいけない部分もあるけど、その後ものすごく多彩で実験的で挑戦的なことをやってる。全部のアルバムが好きかといえばそうじゃないけど、彼がそれをやる姿勢がすごく好きなんだよ。“今これにハマってるからこれやるよ。みんな気に入るかな?どうかな?でも僕はこれがやりたいんだ”みたいなね。
Danger Dangerの頃から、僕はずっとそうやってキャリアを進めてきたわけ。あの時期を否定する気はないけど、あれは自分のバンドじゃなくて雇われプレイヤーだったし、音楽的にもいわゆる“ヘアメタル”とか“ポップメタル”って感じで、それはそれで楽しかったけど、自分の作りたい音楽を書くほうが性に合ってるんだよね。
(グラントの話をさえぎって)ごめんね、グラント。
オリビア・ニュートン=ジョンとの話だけど、15年一緒にやってたって言ったよね。最初に参加したのって何年ごろ?
うちの両親がオリビア大好きで曲をよく聴いてたから、もしかすると僕は子どもの頃からアンディのギターを耳にしてたかも…って思ったんだけど。
えっとね、彼女のメインのキャリアは70年代初頭から80年代中盤までが一番活躍してた時期で、僕が参加したのは90年代後期だから、かなり後なんだ。でも当時のレコードのギター演奏はホントすごい。主にジョン・ファーラーって人が弾いてて、オリビアのヒット曲の7割くらい書いてるんだよね。
ただのオーストラリア出身の素晴らしいギタリストってだけじゃなくてね、たぶん彼女(オリビア)がヘンク・マーヴィンやシャドウズ界隈で知り合った人だったのかも。あ、いや、待てよ、そもそもジョン・ファーラーはパット・ファーラーと結婚してて、パットはオリビアとオーストラリアで親友みたいな存在だった。で、オリビアが歌のコンテストに優勝したとき、一緒にイギリスに渡って、10代後半から彼女のキャリアが始まったんだ。
そうやってロンドンに行って、最終的にクリフ・リチャードのバックコーラスをやるようになった。まあ、そのへんの詳しい話は彼女のヒストリーを調べればわかるよ。で、僕が彼女とやった仕事はというと、すごい映像がいっぱいあるけど、たとえばシドニーでシドニー交響楽団とやったオペラハウスでのコンサートが録画されてて、あれは本当に最高だった。オリビアと一緒にオーストラリアに行くのは、文字通り王族に付き添うようなもんなんだよ。
でも僕にとっては、あのヒット曲を全部プレイできたのが大きかったし、彼女自身もずっと新しいレコードを作り続けてて、すごく cool な作品をたくさん出してた。その一部には僕も参加したんだけど、やっぱりメインは彼女のレガシーやツアーを支えることで、お客さんにあの音楽を届けるって感じだったね。で、僕はただのギタリストじゃなくて、音楽監督(ミュージック・ディレクター)もやってて、要はバンドをまとめるリーダー役。
それもいいメンバーが集まればそんなに難しいことじゃないし、たまにちょっと合わない人もいたけど、基本的に彼女は素晴らしかった。僕は心から彼女のことを愛してたし、曲の数々も本当に好きだったんだよ。
彼女は本当に、すごい…うーん、過去形を使いたくないんだけど、最初にこういうインタビュー受けるのは初めてだからね。もう亡くなって数年経つけど、とにかく驚くほど素晴らしい人だった。
僕の経験上、オーストラリア出身の人はみんなユーモアがあって知的で優しいところがあるけど、彼女もまさにそういう人だったんだ。
すごく一緒にいて楽しかったし、まったく疲れを見せない働き者で、社会に貢献もたくさんしてた。よく“自分の力を正しいことに使う人”って言ってたんだけど、本当にその通りで、がんに関する啓発活動もずっとやってて、それが結局命を奪った病気なんだけど、最初に乳がんになった90年代初頭からずっと生き延びてきた。
それが僕の命を救ってくれたって話にもなるけど、まぁ長くなるからね。実は10年前に僕もがんを患ったんだ。
もし彼女が“違和感を覚えたら諦めずに医者に行くべき”って言ってなかったら、僕は多分手遅れだったと思う。彼女も最初は3人の医者に“問題ない”って言われたのに、直感で“いや絶対おかしい”って思って、もう一回行ったら“すぐ手術が必要”って言われたらしくて。
同じように、僕も“ここがおかしいな”って鏡を見て思って、月曜に病院行って木曜に手術だった。もし“男だし医者なんか行かない”ってなってたら、めちゃくちゃ進行の早いタイプだから危なかったと思う。
だから今これを聞いてる人にも言いたい。“なんか変だ”と思ったら放置しないように。いろんな人が亡くなってきたけど、男だと前立腺がんが多いし、僕の場合は精巣がんだった。でも若い人がかかることが多い病気だし、ほんとわからないものなんだ。
そういうわけで、僕は他の有名ロックバンドからもツアーとか誘いはあったんだけど、やっぱりオリビアと一緒にやるのを選んだ。
名前は伏せるけど、別に自慢ではなくて、ひととおり考えた結果ね。人生で家を留守にするなら、心から好きな音楽と好きな人たちと一緒にやるべきだと思ったんだよ。若い頃は何でも“イエス”って答えるけど、年を重ねるとそうもいかなくなる。
僕もよくわからないフリーランスの結婚式バンドみたいなのとか、企業パーティーで緑の妖精(レプラコーン)の格好させられたり、いろんなくだらない仕事もしてきた(笑)。
写真がどこかにあるはずなんだよね。ネットに出回ったら困るけどさ。でもそういうのも含め、当時はお金が必要だったし、若いし勢いで全部やってた。でも今はあんまりレプラコーン衣装は着る機会がないかな(笑)。
でもポール・マッカートニーに“緑の妖精の衣装で来てくれ”って言われたら、そりゃ着るけどね。“ポール、呼んでくれ、何でもやるよ”って(笑)。ま、そんな感じ。
話が尽きないね。
いやあ、こっちが申し訳ないくらいだよ。
いやもうアンディは経歴がすごく幅広いから、どこから聞いていいのやら。
もし今16歳くらいの子がこれ聴いてるとして…って考えると、やっぱりアンディがどんな選択をしたか気になるよね、って思うんだ。
そうやって、君は…なんだろうね。
ちょっと流し気味に話したけど、それって大きいことだと思うんだよね。さっきの話で“もう音楽って自分にとって当たり前だ”みたいな感じで言ってたでしょ。それが16歳のときだったのかな? その頃にレッスンを受け始めたって言ってたけど、ある時点で“音楽が自分の道だ”って思ったわけだよね。これは大きな決断だと思うんだ。だって普通、芸術の分野って、生活の糧にするには厳しいことが多い。
アートの世界って、普通の人はキャリアにするのが大変なんだよね。音楽を選ぶって、必ずしもラクな道じゃない。ほんの1%くらいが大成功するか、それより少ないかもしれないし。
“音楽が好きで、あわよくばお金になればいいかな”みたいなのが、たぶん一般的な考え方だと思うんだ。
でも君の場合は“決断”ですらなかったように聞こえる。だからそこが気になるんだ。実際そうだった? それともうひとつ、もし今16歳くらいの子がこれを聞いてるとして、どんなアドバイスをしたい?
“自分がここまで来るうえで本当に役に立ったポイント”って何だと思う? それに、いろんなミュージシャンからも聞くけど、“一緒にツアーを回るとき、いかに人間的に接しやすいか”ってすごく大事なんだよね。どんなにギターが上手くても、ツアーで一緒にいるのが苦痛な人は誰も呼びたくないわけで。
だから、君が“これが大事だった”“これがキャリアにプラスになった”って思うようなポイントって何かある? 今振り返ると“あれが転機だった”とかさ。
そうだね、すごくいい質問だし、さっきの“何か特別な決断があったわけじゃなかった”って言葉はまさにその通りなんだよね。自然に“これしかない”って気持ちが育っていった感じで、“大変そうだな”とか“家族に反対されるかも”とか、そういう意識もあんまりなかったんだ。
母が僕を育ててくれたけど、“ミュージシャンなんてドラッグだの悪い世界かも”って言われる可能性もあっただろうに、なかったんだ。Danger Danger時代でも酷かったのはピザとダイエットコーラくらいだったし(笑)。
つまり、ちょっと無謀と言えば無謀だけど、“自分はこれを続けるんだ”って確信があったんだよね。計画とかそういうのはなくて、とにかく“やりたい”だけ。
まあ途中では“リーディングを学んでスタジオミュージシャンやるかも”みたいな現実的な判断もあったよ。
ギタープレイヤー誌とかでルカサーとかカールトン、トミー・テデスコなんかがスタジオで稼いでるの見て“あ、そういう道もあるんだ”みたいに。
でも全体的には常に流れに乗って生きてきた感じで。“デントンに住んでる、なぜだ? いつのまにかマイアミにもいたぞ”みたいな(笑)。
僕の地元エバンズビル(インディアナ州)はそんな大きくない町だし、視野も狭いところだったけど、そこでテイラー・ベイってバンドに入って、レコードも録って、メジャーから声がかかりそうなところまで行ったんだよ。
音も良かったしオリジナルのバンドだったし。ただ、メンバーの中には家庭を持ち始めてる人もいて、全員が全力で進むって感じでもなくて。
そこに“Bruce”って人がいて、何年も後にまた会ったとき“もしあのときマイアミに行かなかったら、一生後悔してただろうね”って言われたんだ。Danger Dangerに入って成功したあとで改めて言われて、ああそうだなって思った。
僕自身は自信があるタイプじゃなかったし、今でもそんなに自信家ってわけじゃない。だから、誰かの“おまえ、それでいいんだよ”ってひと押しがすごく大きかったんだよね。
だから、タイミングよく誰かにかけてもらった一言が、人生の方向性を決めることもあるんだ。あと、母が僕に対して決して疑わず、“あんたがやりたいことを全力でやりなさい”って思ってくれてたのが本当に大きい。
母は4人の息子をほぼ1人で育てて、本当に自己犠牲的に働いてたんだ。だからこそ、僕らには自分の情熱を見つけて全力でやってほしかったんだと思う。否定されたことは一度もないから、すごく感謝してる。
で、グラントが言ったように、結局“人としてどうか”ってのはすごく大事なんだよね。トップ中のトップなら横柄でも通るかもしれないけど、そんな人はごく少数だし…。あ、ちょっと待って、ここにオクタヴィアがある。(笑)
昨日ずっと探してたんだよ、マイク・デインが持ってったかと思った。あ、やっぱり家にあったんだな。これは昔のロジャー・メイヤーのオクタヴィアで、今レコーディングしてる曲で使おうと思ってて。そう、実はアルバムの制作中なんだ。
でね、“人に親切にしよう”ってわざわざ考えたことはないけど、昔から僕は“みんな気持ちよく過ごせたらいいな”って感覚があって、それが音楽活動でも同じように働いてるってことに、教える立場になってから気づいたんだよね。バンドメンバーとしての役割とかさ。
要は“自分が主役だ!”じゃなくて、全員がどう絡むかを考えて、“自分はここで弾きすぎてないか?”“もうちょっと抑えたほうがいいか?”とか“何が必要で何が不要か?”を意識する。
それって普段の生活でも同じで、道で誰かとすれ違うときに“挨拶してもいいかな”って判断したり、“相手が受け取りそうになければやめとこう”とか、相手がぶつかってこようとしたらこっちがスッと避けるとか。
僕が暮らすスタイルと、音楽での振る舞いって、本当に同じなんだよね。
だからグラントの指摘どおり、ステージ上は90分かもしれないけど、それ以外の22時間半の過ごし方で、“こいつと一緒に居たくねえ”って思われたら、どんなに上手くても次は呼ばれないんだよね。
うちのバンドは基本ファミリー的なコアメンバーがいたけど、誰かツアー出られないときに助っ人を呼ぶこともあって、その人が素晴らしい推薦を持ってても、遅刻ばかりとか曲覚えてないとかだと最悪なんだ。いくらテクニックがあっても続かないんだよね。
あと若いプレイヤーに言いたいのは、僕は今でもそうだけど、どんなギグでも“一生でいちばん大事なステージかもしれない”って気持ちで取り組んでる。
ブライアンなんかは、サンクチュアリで僕がセッティングしてるの見て“いや、アンディ、ちっちゃいワインバーで水曜にやってたライブのほうが機材ゴツかったね(笑)”って言うんだよね。前にアルバートホールでオリビアとやったときよりデカいとか(笑)。
オリビアのときはトランズアトランティックの30Wとか、ちっちゃいAC30みたいなメサ風アンプ使ってたしね。でもまあ、どんなギグだろうが僕は全力で準備するし、曲もちゃんと覚えていくんだ。だって演奏する音楽にも他のメンバーにも敬意を払いたいから。
結局、自分を裏切りたくないんだよね。それがサイモン・フィリップスとの仕事やオリビアの仕事につながったと思う。初めてサイモンと一緒にやったのは、’93年のNAMMで“アックス・アタック”っていうホシノのイベントだったんだけど、アイバニーズとかが主催する大きいショーだった。
そこにヴァイやサッチ、ポール・ギルバート、ショーン・レーン(少しだけアイバニーズの人だった)、アレックス・スコルニック、レブ・ビーチなんかが出るから、バックバンドが必要だったんだ。
で、サイモンが呼ばれて、僕もDanger Dangerにいたけど“あいつなら対応できる”ってことで呼ばれた。ベースは当時ウェザーリポートにいたジェラルド・ビーズリー。このバンドでみんなの伴奏しつつ、サイモンが“自分の曲もやりたい”って言って、めちゃフュージョンな曲を取り上げたんだよ。15/16拍子とか、大人向けコード進行とかね。
だから僕にとっては最高の夜だった。みんなは“Danger Dangerのアンディ”しか知らないから、そこで超絶フュージョンをサイモンと一緒に弾いて、しかも大物ギタリストたちのバックもしたわけで。
で、そのショーのとき、サトリアーニがリハに来れなかったから、僕がサトリアーニの曲もある程度わかってたんで、バンドをまとめることができて。それが4年後、サイモンがツアーをやるときに、普段のギタリストのレイ・ラッセルが出られなかったから“あのアンディって奴、しっかりしてたしあいつならいけるんじゃない?”って呼ばれたんだ。
さらにその後、サイモンとオリビアが同じマネージメントだったから“オリビアがオーストラリアのバンド連れてアメリカに来るんだけど、ギタリストのひとりが無理になった。誰か紹介して”ってなったときも“じゃあアンディがいいよ”ってなって“オリビアとやらない?”って連絡が来て“うん、面白そう”ってなって。その後に僕が全体をまとめるリーダーになって、アメリカ人メンバーでバンドを組もうって話になったわけ。
なるほどね。どんなジャンル、どんなミュージシャンにも通じる話だと思う。真面目に取り組むことは大事だし、僕も最近、教会の礼拝でギターを弾いたりするんだけど、そういうのも“雇われる以上、期待されるレベルがある”っていうのが同じなんだよね。
自分自身の期待値もあるけど、雇う側にも“これくらいはやってほしい”って基準がある。今僕が行ってる教会の音楽ディレクターとドラマーから“君、しっかり弾けてるね、今までの人たちより安定してるよ”とか言われて、そこから別の人に話が広がって…みたいにどんどんチャンスが増える。
アンディがいつも120%の力で取り組んで、自分の役割を責任もってやって、チームとして動くってのは本当に大事で、どのレベルでも同じだと思う。
スポーツに例えると、ホッケーで一人だけ勝手に滑り回っても楽しくないじゃん?やっぱりチームとして成立しないとね。どんなキャリア段階でも“あいつはチームプレーヤーじゃない”って言われたら外されるし。
ブライアンの会社が成長してきたのも同じことで、一つひとつに誇りを持って取り組んでるからなんだよね。
僕たち、ブライアンの動画とか見てても、あのケーブルを通すところまで徹底的にこだわってて、すごく丁寧だなって思うし、“とにかくいいものを作りたい”って気持ちが伝わってくるよね。
もちろん努力してても上手くいかないときはあるけど、そこから学んで前に進む。そしてそれこそが大事だと思うんだ。音楽だけじゃなくて、どんな分野でも“自分のやることに誇りを持ってる”人って本当に違いを生むんだよね。
もし音楽やってる人なら、もうそういう世界観で生きてるだろうから、わざわざ言わなくてもわかると思うけど、こうして言葉にするのも悪くないよね。成功の鍵になることが多いからさ。
で、必ずしも“最高のミュージシャン”とか“最高のアーティスト”じゃなくても、その人が持ってる雰囲気とか姿勢が、組織や会社全体に大きな価値をもたらすんだ。
さて、もう既にめちゃくちゃ充実した話をしてるけど、次に進む前に、グラントのほうからスポンサーさんの紹介をしてもらいたいんだよね。ポッドキャストを支えてくれてる大事な存在だから。
じゃあグラント、よろしく。
了解。まず最初に紹介したいスポンサーは、アンディもブライアンもよく知ってる“the guitar sanctuary”なんだ。ブライアンが今いる場所で、さっき言った通り車で10分の距離にあるやつね。
以前のエピソードでアンディが“the guitar sanctuary”の話をしてたときに、彼が自分の部屋で誰かが弾いてる音を聞いて“あ、あれ僕のフレーズっぽいな。この店にいるのか?”ってすぐわかったって話があったんだよね。そこで“ギアによるのか?プレイヤーによるのか?”って盛り上がって面白かった。
アンディはサンクチュアリにしょっちゅう来てて、まさに今日話してるアンプの壁とかギターの壁とかを使ってるわけ。動画で見てる人はわかるけど、すごいよねっていう。
こういうギアは、ギター・サンクチュアリで手に入るんだよ。
僕ところでアンディ、今さっき指さしてたのは何?
あ、これは新しいSuhrのSL68のMark1なんだ。向こうにMark2もある。どっちも結構使ってるんだよね。基本的には’68年のプレキシみたいな回路で、実際にオリジナルの’68マーシャルも持ってるけど、これもすごくいい感じに迫ってるんだ。
最近のレコーディングでもよく使ってるし、一部のライブでもね。あとは古いメサブギーもいくつか持ってて、サンクチュアリもメサ製品いろいろ扱ってるよ。
で、バレンタインの話なんだけど、ちょっと面白いエピソードがあってさ。
このギターなんだけど、ちょうど昨日で製作されてから30周年だったんだよね。僕それSNSに載せたんだけど。
で、ブライアン・ミーターっていう、僕がいつも頼りにしてるスタッフがいてさ。映画『ピーウィの大冒険』みたいに、ピーウィがマジックショップに入ったら店主が“ピーウィ!新しいオニオンガムがあるぜ!”みたいな感じで、ブライアンは僕にとってそんな感じなんだよね。“アンディ、こんなの入ったよ”っていつも言ってくれる。
それで昨日、ギターの誕生日について僕が投稿したら、彼はさっそく僕のIbanez AT100の1本を誰かに売ったんだって。バレンタインのプレゼントで、女性が旦那さんに買ったらしい。“すごいね、30年経ってもこのギターは生きてるんだなあ”って思った。
でもサンクチュアリは“危険”だよ。クールなギターがありすぎて、つい欲しくなっちゃうんだ。僕もしょっちゅうそこでやらかしてる(笑)。
数ヶ月前にトミー・エマニュエルを見に行ったときの話なんだけど、何年も前から彼とはちょっと知り合いで、僕が今まで見た中で最高のミュージシャンかもしれない。人柄も素晴らしいし、プレイも最高だし。
彼はメイトンのギターを使ってるよね。それで、サンクチュアリに行ったときにメイトンを試奏したらすっかり惚れちゃって、買ったんだ。それを持って行って、ショーの前にトミーと一緒に弾いてみたりして。今はメイトンのアコギが大好きなんだ。だから“メイトン、アイバニーズ、Suhr”とか、いろんなのをサンクチュアリで手に入れられる感じかな。
全部ギターサンクチュアリで買えるよ、みたいな感じだね。
で、僕のペダルボード全体も、たぶんブライアンが写真持ってると思う。ここの番組ってペダルボードの話とかもするのかな?“Chairman of the Boards”だし(笑)。ときどきするんだ?
だいたいコーヒーの話ばっかりなんだろ?(笑)
実は僕、サンクチュアリの“コーヒーボーイ”でもあるんだよ。“いま向かってるよー、コーヒー買ってくけどいる?”って感じで、ブライアン・ミーターには必ずコーヒー買ってくし、ブライアン・オメリアンは“僕は水でいいよ”みたいな。あそこは水も美味しいんだ。
リュシアのダニエルはスタバが嫌いで、Duinoってクラフトコーヒーの店が好きらしくて、そこに行ったりもする。もしギターがダメになったら、僕“Andy Dordashian”って会社作ってコーヒー配達するよ(笑)
だってコーヒー持って行ったら、誰も怒んないでしょ(笑)。まあ、これが僕の“セーフティーネット”かも。60になってやっとバックアッププランができた感じ。
いいねえ。これが最初のスポンサー、“ギターサンクチュアリ”の紹介で、ゲストのアンディ自身が力説してくれて、今までで一番の宣伝になったんじゃない(笑)。
で、次に紹介したいのが“Neural DSP”。僕たちはみんなNeuralをよく知ってるよね。
NAMMでも何か秘密めいたアナウンスがあったらしくて、個人的にめっちゃ楽しみ。最近はMorgan Amp Suiteっていうのをリリースしたよね。リスナーのみんな、Morgan Amps好きな人多いと思うけど、それのプラグインがNeuralで出てるんだ。デスクトップエディターも対応して、Cortex ControlっていってQuad CortexをPCでいじれるようになった。より深い編集ができるようになったんだよ。
それと、リリースされてから90日経過したプラグインが30%オフになるコード“CHAIRMEN”もあるから、70%無料みたいなもんだよね(笑)。Neural DSP、ぜひチェックしてみて。
最後に…
“Sweetwater Gear Exchange”についても話しておきたいんだ。昨日ちょうどそこに自分の製品を1つ出品して売れたところなんだよね。
すぐに発送予定。で、いいのは、手数料ゼロで中古ギアを売れるんだよ。
ReverbやeBayみたいなところは手数料が高くなってるけど、Gear ExchangeはSweetwaterのギフトカードで受け取るなら手数料がかからないんだ。
それで貯まったクレジットでsweetwater.comで何か買えばいい、みたいなね。とりあえず試してみて。
というわけで、これがスポンサー紹介の1つめのパートだよ。ブライアン、返すね。
ありがとう。さて、今度は歴史の話をしようかな。僕、裏話とかドキュメンタリー的な話が大好きなんだよね。さっきまでの内容もすごく面白かったし。
そうそう、これブライアンのドキュメンタリーにも入るんじゃない?(笑)
伝記みたいに(笑)。僕は’93年生まれなんだけど…とか言いつつ。
じゃあ話題をギアのほうに切り替えて、アンディから送ってもらった写真を使って、最新のリグの構成を見せてもらおうかな。グラント、画面共有できる? 僕としてはアンディのリグを見せたいんだ。
まぁアンディのセットアップはしょっちゅう変わると思うけど。
いや、まだ君んとこで作ってもらって以来、何にも動かしてないよ(笑)。
いいね。
じゃあ来週あたりもう一回聞いて、まだ変わってないか確かめるよ(笑)。
ああ、でも実際僕もドライバー持ってロックタイトを剥がし始めると、もう元どおりにならないからね。
前回はNAMMの前に、僕が“ちょっとこの調整だけやりたい”ってブライアンに電話したら、それがなぜかボードを完全にバラして全部組み直すっていう大作業になったし(笑)。僕が“水曜に出発だ”って言ってたら、そのとき木曜か何かで、ブライアンが週4日しか働かないのに“OK、やるよ”って。
結局、いろいろあって全配線やり直して、ギリギリ出発前に完成。僕が何も言わないってことは、大抵うまくいってるってことだから(笑)。
で、アンディに写真送ってもらったんだよね。もしポッドキャスト聞いてる人がいるなら、いま画面共有してるよ。なんでか止まってるけど…あ、戻った。
そうそう、このトーンを出してるのは、実はジョージ・フラー(サンクチュアリのオーナー)が建てた僕の家の2階部分なんだ。ギターサンクチュアリのオーナーであるジョージ・フラーが私の家を建ててくれたんだ。彼のおかげで1997年にマッケニーに引っ越すことができたよ。家の2階を僕がスタジオにしているんだけど、そこにスタジオがあって、防音してある隣の部屋にラウドなキャビネットが置いてあるよ。(動画では写真が見れます。)
その写真に写ってるのがメサのレクチ系2×12キャビが3台で、上2台はVintage30で、下にあるやつにはEVM100を入れてるんだ。あれは“That Pedal Show”でダンが大はしゃぎしたときに使ってて、“これすげー”って思って調達したんだよね。
あのときはトーンが良すぎて収録止めたんだっけ(笑)。
そういうわけで、下のキャビにはEVの高耐久のスピーカーが入ってる。マイキングは基本SM57が多いけど、1つのスピーカーにはメサノビックのリボンマイクを使ってるよ。これはジョシュ・スミスが薦めてくれたやつで、彼が僕の“Electric Truth”のレコーディングをしてくれたんだ。最近またLAで2週間ほど新作のセッションして、それを今まとめてるとこなんだよね。
で、そのマイクの信号は古いNeveの1272プリアンプに入れて…
配信用には、高級…ってほどでもないけどMackieのミキサーにまとめて、ギターチャンネル3つと、あとプレイバック用のトラックと声をステレオでApolloに送ってるんだ。
まあとにかく、写真に見えるボロいAC30は、前日に録音で使ったやつで、’64年製かな? 90年代にTop Boostが後付けされてるけど、すごく特別な回路で音もいいんだ。
で、ペダルの写真を見せられるって言ってたけど、あるよね?
あるある。じゃあこれ見せるよ…いいでしょ?
“ワーシップ”やればやるほどペダルが必要になるってやつ(笑)。
そうそう、指令センターって感じ。
あっ、ミューズドライバーも見えるね。シグネチャーペダルがいくつかあるんだよね。
うん。キャリアを重ねる中で、最初にコラボしたのはxoticだったかな。“BB Preamp”っていうプリアンプペダルがあって、今はボードには載ってないけど、いまだにすごくいいペダルだよ。
で、その次がJHSかな。“AT”っていうペダルを出したんだ。写真右端にある赤いやつ。それと同じ名前のアンプもあるね(JHSのアンプ?)。
これもブライアン・ミーターが教えてくれたんだけど、“Angry Charlie”ってペダルがあって、“アンディ、これ好きじゃないかな”って勧められて、ボードには載せたんだけど実は最初はあんまり使ってなかった。
理由としては、このLone Starアンプを2台ステレオで使ってるんだけど、その歪みチャンネルをメインにしてたからあんまりペダル歪みいらないかなと。…えっと音出していい?
ちょっと聞いていい? ラジオ向けに言っておくけど、今から鳴るギターは僕(司会者)が弾いてるってことにしとこうか(笑)。
そうそう、実はグラントが弾いてるんだ。“7日でギター習得”みたいなプログラムがあって…って冗談冗談(笑)。あと“ウィンキー”のイラストも描けるよ、って誰向けだろうねこのネタ(笑)。
僕そうやって“Angry Charlie”をボードに載せてたんだけど、普段はLone Starのリードチャンネルを使ってBBとかTS808で前をちょっとブーストする程度だった。
でもあるとき、スウィンドン(ダニエル・スタインハートの地元に近い)でギグがあって、彼とXTCのデイブ・グレゴリーが観に来たんだけど、そのときエフェクトループが壊れてて、原因はプリ管だったかもしれないけど、とにかく時間がなくて直せなかったんだ。
だからエフェクトをアンプのフロントに入れるしかなくて、そうなるとアンプの歪みを使うとゴチャゴチャになるから、代わりに“Angry Charlie”でリードを作ったら、めっちゃ良い音でその夜は最高だったんだよ。
“うわ、このペダルいいじゃん”ってなって、アンプのゲインよりも細かくコントロールできるから気に入って、そのうちメインのリードサウンドが“Angry Charlie”になってきたんだ。
それである年のNAMM(2010年代のいつか)に“このJoshって人(JHS創始者)に会ってみたい”と思って探しに行った。
NAMMでJHSのブースを見つけて、“Angry Charlieめっちゃ好きだよ”って言ったら、向こうも“そうなんだ、最近急に売れ出してね。何か変えたい部分ある?”って聞かれたから、“あるある”ってなってコラボしたんだ。それが“ATペダル”になったわけ。今でも僕のメインリードに使ってるよ。
最近のコラボだと“Muse Driver”と“Halo”があって、どっちもRobert Keeleyの会社なんだよね。“Halo”のほうが先に始まったプロジェクトで、また別のNAMMで、僕がダニエル・スタインハートと一緒にいて“ディレイペダルでこういうの作りたいんだけどさ…”って話してた。
僕は長いことMemory Manを2台使って、それをStrymon Timelineで再現しようとしてたけど、Timelineって多機能すぎて自分は1~2個のサウンドしか使わないし、もうちょっと特化したものを作りたかったんだ。
で、ダニエルに聞いたら即答で“ならロバート・キーリーでしょ”って言われてさ。
それでロバートのところに行って、“アンディを紹介するよ”って会わせてくれた。多分2018年とか2019年頃かな。彼も“面白そうだね”って興味持ってくれて。
ロバートはすごくポジティブで明るい人で、初対面ですぐ意気投合しちゃった。そこから、新しいエコー回路をどう作るかとか、新しいデジタルチップをどう使うかとか話し合って、“基盤ができたらアンディ呼んで、実際に合わせてみよう”ってなった。
それで、けっこう時間が空いたんだけど、2020年の頭くらいにようやくキーリーの所へ行けて、いろんな事情があったけどようやく会えたんだ。
僕はEP-3やMemory Man、Strymonとか色々持っていって“こういう音がほしい”って提示して、向こうの作りかけの回路も聴いてみて。多分彼らは“ちょっとイコライジング調整すればできるでしょ”くらいに思ってたみたいだけど、結果的に1年半くらいかかったんだよね(笑)。
でもその過程が本当に最高でね、たまにイライラすることもあったけど、彼らは完全に僕と同じ考え方だった。“どうせ作るなら、今使ってる機材全部に勝たなきゃ意味がない。自分が本当に使うものじゃなきゃ、シグネチャーとして出せない”ってスタンス。
70~80年代なんか、広告で“この人は絶対それ使ってないでしょ”ってのがあったし、金儲けのために名前貸してるだけみたいな。僕はそれをやりたくなかったんだ。
だからこそ時間かけてでも完璧にしたい。結果として、今まで使ってた機材全部に勝るクオリティに仕上がったと思ってる。
今僕が弾いてるこれね、使いすぎなくらいお気に入り(笑)。いつかステレオで届けたいんだけど、ネットだと難しいときもあるんだよね。
今ちょっと卓にリバーブ乗せてるんだけど、普段はかけてないかな。
でも、すごく自己満足なプロジェクトだったと思うよ(笑)。自分が欲しい音のために作って、最高の形にしたんだけど、それを他の人もこんなに気に入ってくれるとは思ってなかった。
実際“Halo”を使ってる人をいっぱい見るし、“こんなにみんなが好きになってくれるんだ”って感動してる。
“Halo”がすごいのは、下手したらリバーブいらないくらい空間を満たしてくれるとこなんだよ。
僕は週4日で3~4台のリグを組むこともあるから、1日に1台は組むってペースだけど、そのとき“Halo”を触り始めると20~30分くらい演奏に没頭しちゃう(笑)。
そうそう、まさに“Halo”がそうで、弾き始めると“あ、ヤバい、もうこんな時間”ってなる。
ホントに音がいいんだ。ショップにはよく“Timelineでアンディみたいなディレイ作るにはどうすれば?”って聞かれるけど、“Halo買いなよ。そこに一発で入ってるよ!”って言ってるんだよね。初期プリセットがまさに僕のサウンドで、サイコーだから。
それがコンセプトだったんだ。Strymonでやってたディープな編集を、一発で出せるようにしたかった。
Haloって、ディレイ同士が重なりあってリバーブっぽくなるんだよね。だから普通のリバーブをあんまり使わないんだ。
あと、エクスプレッションペダルでミックス量をコントロールできるようにしてる。ソロギターやるときはそれが超大事で、ピアノのサスティンペダルみたいに使える。
それでいて主張が強すぎなくて、テープエコーがスッとフェードしていくあの感じがあって、軽いモジュレーションがかかってるからピッチがちょっと揺れて“halo”っぽくなるんだ。元の音はキレイに残って、周りがふわっと揺れるイメージ。
今、いいフレーズ弾こうと思ったけど出てこなかった(笑)。
とにかくこのトーンのもう一つの要素が、Keeleyとの最新コラボである“ミューズ・ドライバー”なんだ。Haloの開発中、僕はずっと昔のKeeley改造版のBlues Driverを使ってて、それがロバートと知り合ったきっかけでもある。
でもアーロン・ピアースとロバート・キーリーと深く話してるうちに“もっとこんな回路にしたい”って思ったんだ。つまりBlues Driverの改造版をさらに改造したいってことで、“AT Super Mod”っていう限定ペダルを1年前くらいに出したんだよね。
ちょうどその時期、Keeleyは自社工場でケースを作れるようになったりして、ラインナップの刷新もしてたみたいで、新しいオーバードライブをいくつか考えてた。それで“じゃああのペダルを続けて作りたいけど、もっと柔軟にやろう”って話になった。
結果として、僕はもっと低域を削りたかったから、何回もセッションしたんだ。いいのは、Keeleyが家から車で3時間のオクラホマシティにあって、僕は北テキサスだから行き来しやすい。実際に同じ部屋で音を出して、“ここもうちょいこうしよう”ってやるのが一番なんだよね。
音に関しては、“もうちょっと空気感欲しいかも”とかテキストでやり取りするだけじゃダメで、やっぱり現場で実際に聴かないとわからないから。
Haloのときもそうだけど、鳥肌が立って“これだ!”ってなる瞬間があるんだ。
Blues Driverのさらなる改良でも、いろいろEQやコンプを試して、“まあまあいいけどもう一歩…”ってなってたら、ロバートが“ゲルマニウムダイオードを試してみよう”ってひらめいて、それがもう瞬時にマジックだったんだよね。だから今、そのペダルは… もともと僕が本当に狙ってた、すごく具体的なサウンドを得るためのもので、さらにゲルマニウムが加わったことで、例えばボリュームを下げたクリーンなブレイクアップっぽい音にもなるし、同時にすごく良いブースターにもなる。
僕はそれをJHSのATペダルのブーストとして使ってるんだ。すごくいい太いリードトーンが出たときに、ありがとうグラント。いや練習してるからね。エース・フレーリーみたいな、キッス魂がちょっと顔を出してるけど(笑)。ともかく、その太いリードトーンにした状態でネックピックアップに切り替えると、僕の場合どうしてもややこもってボワッとした音になりがちなんだ。だけど今やってるのは、JHS ATの前にMuse Driverをゲルマニウム・モードでごく弱めのドライブ設定にして、ちょっとだけ高域を足してやること。そうすると、スポンジ感が出て、でもまだネックピックアップなんだよ。――ちなみに今のフレーズはネックの音ね。
じゃあまずJHSだけの音を出すよ、これはブリッジピックアップ。
(演奏)
そこからネックピックアップにして、さらに前段にゲルマニウムモードのMuse Driverを足すわけだ。
(演奏)僕
これは、すごく長い間探してた音なんだよね。つまり、ハイゲインでネックピックアップ使ってもモコモコしないリードトーンが欲しかったわけ。そこで2つのことが起きてるんだ。ゲルマニウムが低域をある程度削ってくれるから、ブリッジ側がやたらモサモサしがちな状況でも、ネック側のボワっとした感じを抑えられる。さらにEQ回路も、低域を少し狙って削ってくれる。だからもう僕としては大満足でさ、キーリーみたいなチームが僕に付き合ってこれを作ってくれたのが本当に嬉しいし、その過程も最高に面白かった。
しかも彼らはあと1ヶ月かそこらで、新しいドライブペダルを何種類か出すんだけど、それがまたヤバいぐらい面白いんだよ。めっちゃクリエイティブな回路を作ってる。たとえばNoble Screamerみたいな感じで、TS808とNoble系ドライブを足し合わせられたりとか、そういうことをやってるんだ。今回の新しいペダル“Muse Driver”は、ロバート・キーリーが最初に作った改造回路を入れたり、僕のロー削り回路を入れたり、ゲルマニウムとシリコンを切り替えたり、いろいろ組み合わせられるんだよ。だからサウンドバリエーションがすごく幅広くて。
それともうひとつ面白いのは… ちょっと試してみるね。
(演奏音)
これ、“Muse Driver”でドライブを全開、ゲルマニウムモードにしてるだけなんだ。
まずは今の設定ね。普通、Blues Driver系の回路をこんなにドライブを上げると、モッサリしてフワフワして絶対にいい音しないはずなんだよ。でも今みたいにドライブ全開にして…僕はMuse Driverを2台持ってるから、もし通常の使い方に切り替えると――同じペダルだけど――ほら、すごく上品にまとまるんだよ。
“いい音だね”“おお、クラシックっぽい”ってなるでしょ? そうそう、それが僕がボリュームを絞るときに狙ってる感じ。多くのギターにはトレブルブリードを入れてあって、ボリューム下げてもキラッとした煌めきとニュアンスが保てるようにしてあるんだ。だから今言った2台のMuse Driverはボードから外せないね。下手したら3台目が欲しいくらい(笑)。ほんといろんなことができる。
……さて、ちょっと話が脱線しつつあるけど、次の広告紹介までに時間があまりないし、でもせっかくだから言いたいのは、今の話って、動画で見てる人はもちろん、音声だけ聞いてる人にも伝えたいのよ。
そう、たしかに僕はいいペダルを揃えて、トーン作りにかなり時間をかけてきた。でも同時に、ピックアップの選択やボリューム操作、テクニック面でも工夫していて、つまりギアと演奏技術をうまく融合させて、あの美しいトーンを得てるわけ。
でも、どっちかだけじゃダメなんだよね。練習だけじゃ今の音にはなれないし、ギアだけでも無理。結局、両方を一体として考えないとダメなんだ。そのへんの説明がすごくわかりやすくて、自分も勉強になるし、僕自分のボードに落とし込めるかな?僕って考えちゃう。
―まさにその通りだよね。ほんと、こうしたギアがすごく手助けしてくれてるのは間違いない。でも最初はやっぱり“自分の耳”なんだよ。こういう音が欲しいっていうイメージがなきゃ話にならないし、いまだに僕自身、人生の半分以上ギター弾いてきて、もう60だけど、頭の中には自分のヒーローたちの音が全部詰まってる。エリック・ジョンソンとか、ヘンドリックスやスティーヴィ・レイ、ルカサー、それにカールトンとか、大好きな偉大なギタリストのサウンドをずっと頭の中で再生してるんだ。
彼らの音は、僕が吸収してきたものの一部として完全に自分のDNAの一部になってる。たとえばスティーヴィ・レイの演奏を聴けば、アルバート・キングやヘンドリックスの影響が確かに見えるわけで、それはみんな同じなんだよ。僕らのヒーローにも、またそのヒーローがいる。こうして音楽はずっと続いていくんだね。もし僕を“サウンドの影響源”と呼んでくれる人がいるなら、それはもう本当に光栄で、同時に照れくさくもある。だって結局、僕もただ憧れの連中みたいになりたいって頑張ってるだけだからね。けど最終的に出てくる音は、どんなに真似してもやっぱり自分自身のものになる。それが僕らの“アイデアのコレクション”というか、“良い音って何?”というイメージの集合体で、さらにギターとのつながりがより感情的になっていくと、この機材が“インスピレーションを与える”とか“逆に邪魔する”ってことにより敏感になるわけ。
だから、人生のどの時点でも、まさかこんなふうに天才的なギア職人たちが僕と一緒に製作してくれるなんて、想像もしてなかったんだ。正直“こんなのあり得ない”って感じで、何度も“うわ、すげえ”って頭を抱えるよ(笑)。でも、なんて幸運で光栄なんだろうって思う。結局、それは“ずっとやり続けること”の証明なんだよね。こういうのって計画してできるもんじゃないし、僕自身も想像すらしてなかった。でもこれがあるからこそ、僕ら3人がここで話してて、それを観てる・聴いてる人がいるわけでしょ。この熱量と情熱は、世の中の誰にでもあるわけじゃない。趣味を持ってる人は多いけど、この“音楽へのこだわり”とか“特定の音色を手に入れるために使うギアへの想い”ってのは、かなり特別じゃない? これは本当にギフトだと思うし、軽く扱うべきじゃない、とても特別なものだよ。
で、ペダルやギアの話になるともちろん“あの人は何使ってる?”とか“どうやってあのトーン出してるの?”って興味が湧くわけだ。だってそれを手に入れたら少しでも近づけるってわかってるからね。実際そうなんだけど、そのためには時間もかかるし、テクニックを磨く工程も要るし、耳を鍛える必要もある。そして“ギターからどうやってその音を引き出すか”を学ばないといけない。みんな体の作りや弦の触り方が違うから、僕と君、ジェフ、アラン・ホールズワースなんかでは全然違うでしょ。そうなると、まずアンプに繋いでない状態で“どういうトーンが出るんだろう”と考えて、それをスピーカーを通してどう再現するか――そこが挑戦なんだよね。
だけど、その“追い求める”過程って素晴らしいけどイライラもする(笑)。でも、時に最高の瞬間があって、ブライアンが言ってた通りに“気づいたら20分経ってた”なんてこともある。ああいう時間こそが至福なんだよ。なんて最高だろうって思う。まあ他にもちょっと素敵なことはあるけど(笑)、温かいコーヒーとか、愛する家族とかさ。そういえば昨日、うちの息子がバレンタインディナー作ってくれて、彼女と僕ら夫婦のためにね。めちゃくちゃ最高だったよ。
彼はマカロニ&チーズを作ったんだけど、人生で一番うまいマック&チーズだった。僕はクラフトの粉チーズ派だからさ、粉チーズはチーズだろ?みたいなアメリカ中西部魂があるんだけど(笑)、彼はペッパージャックチーズとか使って、あと和牛のストリップステーキも作ってくれて本当に最高だった。ギターも上手くなってるけど、料理はもっと上手いんじゃないかってくらい。
そういうこと全部ひっくるめて、僕らはトーンや音楽や表現を追求して、それが精神面でどれほど救いになるかを知ってる。今こそ大事だと思うよ。
……ところで次のスポンサー紹介に行く前にひとこと言いたいのは、アンディ、君が“アンプに繋がない状態の音でもどう聞こえるか”をちゃんと意識してる点がすごく好きなんだよ。たとえばボリュームを下げて完全にアンプラグド状態で弾いても、もう“アンディ・ティモンズの音”になってるんだよね。そこが本当にいいと思う。
ペダルがどうとかの前に、その音を大事にしてるから。焚き火囲んでアイバニーズを生音で弾いてても、絶対“アンディ”ってわかるじゃん。レプラコーンの衣装着ててもね(笑)。次のアルバムカバーは燃えやすそうなレプラコーン衣装でいこうよ、なんて(笑)。
“エレクトリック・レプラコーン”ってわけだね(笑)。どうにかしてポール・マッカートニーを説得して、その企画やろうよ。そしたらみんなで飛行機乗って集まって、レプラコーンの衣装で焚き火囲みながら、アンプラグドのギター弾いてポッドキャストやろうぜ。
“Light My Fire”的な感じで(笑)。
あ、でも誤解しないで、レプラコーンの衣装に火をつけるのを推奨してるわけじゃないからね! これ大事な注意事項ね。僕はそんなの推奨しないよ。万が一持ってても、絶対に燃やさないで(笑)。
僕んとこは息子のスパイダーマン衣装がたくさんあるけど、それくらいかな。
…そういやNAMMとディズニーランド、どっちに長く居た? 正直に答えて。
まあ、半々だね。
ま、いいじゃん(笑)。ディズニーランドと同じくハッピーな場所ってことで言えば、ここから紹介する最後の3つのスポンサーも音楽業界に大きな喜びをもたらしてる。家で弾く人でもツアーに出る人でも、AからZまで何でもサポートしてくれるようなやつらなんだ。
まずは“Mono Creators”。すごいクオリティのギグバッグやデュアルケースなんかを作ってる。お気に入りのギター2本を一緒に運びたいときとか、アンディ・ティモンズモデルを2本持ち運びたいときにもぴったり。僕もMonoのバッグを最低1つは持ってるね。
“モノ”って名前だけど、複数持っててもいいんだよ(笑)。実際僕もバックパックやらペダルボードケースやらいろいろ使ってる。さらに新しい電源ユニットとか角度付きのペダルボードも出してる。結構手が届く価格で、使う価値ありだと思う。
お得な割引もあって、“CHAIRMEN”ってコードを入れると10%オフになる。サイトは僕monocreators.com僕だ。
次は“Stringjoy”。ミュージシャンなら弦が必要でしょ? 弦なしじゃエアギターだから(笑)。
“stringjoy.com”に行って、コード“BOARDS”を入れると10%オフ。サブスクリプション方式だから、もし弦をめちゃくちゃ消費する人(メイソンみたいに週に何セットも消費する“ストリング・デストロイヤー”)なら、一気にたくさん注文できる。近所にギターショップがない人も月ごとに弦を送ってもらえるし、アコースティックでもエレキでもベースでも、色んな種類がある。ぜひチェックしてみて。
最後は“Bestronics”、btpa.comだ。先週おもしろいスローガンを思いついたんだけど、忘れちゃったんだよな(笑)。
ここはスクエアプラグやMogamiケーブル、ケーブルロームやジャンクションボックス、何でも揃えてる。2.1mmのDCプラグ(僕たちがビルドで使うやつ)もここで買う。対応が速いし、発送メールが来ると“やった、届く!”って感じで嬉しい。
というわけでbtpa.comをチェック。
今回のエピソードをざっくりまとめると…
ひとつ笑えるけど“やり直せたら…”って後悔してる話があるんだよね。人生を戻せるならどこを変えたい?みたいな。
サンクチュアリで働いて6年で、先月がちょうどアニバーサリーだった。最初の年にアンディのボードを作って、アンディの家まで持っていったことがあるんだ。あのとき、アンディの家がこんなに近いなんて知らなくて。
ちょうど妻と娘がそのとき留守でさ、僕はボードを届けに行って雑談してたんだ。そしたらアンディが今夜はどうするの?って聞いてきて。僕はいやー、長い一週間だったし、家族いないから、1人で映画でも観てゆっくりしようかなって答えたんだ。
そしたらアンディがじゃあステーキ焼いてビールでも飲むけど、残る?って誘ってくれて。でも僕僕あー、ありがたいけど疲れたし映画行きたいなみたいに断っちゃった(笑)。
で、あとで同僚のトレイにこういうことがあったと話したら、お前、何してんの!? そんなオファー来たら絶対行くでしょ!って言われてさ(笑)。たぶん僕があのとき疲れてたのもあって断っちゃったんだよね。あれ以来もったいなかったな~って思ってる。
アンディじゃあ今度改めよう。うちのアレックス(息子)は料理うまいし、あのマカロニ&チーズまた作らせようって話になって。それいいねって。ビールじゃなくて水でもいいし(笑)。なんだったかな、たぶんステーキと何かだったと思うけど…いや、記憶が曖昧(笑)。とにかく僕がバカだった。
でも不思議とこういうことって頭にずっと残るんだよね。アンディまあわかるよ、子育てしてると家が静かなのもいいしねって言ってくれて、ちょっと救われたけど。実際、家を空けて映画観るのも悪くないしね(笑)。
で、トワイライト再上映してたから観たんだろう?なんて話になった(笑)。
──そんな感じで今回のエピソードも締めになってきたけど、グラント、最後にアンディに何かある? この後アンディが素敵な曲を弾いてくれるんだよ。アンディ僕じゃあ“Freebird”いこうかな、11分だけど大丈夫?僕みたいに言ってる。
15分バージョンもあるけどねみたいな(笑)。
で最後に聞きたいのはペダルボードのシグナルチェーンってどれくらい重要?
アンディそりゃめちゃ大事だよ。順番はすごく重要。僕はゲインジャンキーだから、ボードがでかいのはゲインを段階的に重ねてるから。あとGigRigのG3使えば順番を自由に入れ替えられて便利。昔BBをコンプの前に置いたりしてたこともあるけど、結構普通じゃない考え方だよね。でも結果よけりゃOK。Muse DriverをJHS ATのブーストに使う場合は間違いなくMuseを先にしたいし、逆にすると悲惨な音になる。
ま、これが深い質問に対する短い回答だけど(笑)。あとは時間系エフェクトはチェーンの最後かエフェクトループに入れるとか。リバーブはペダル使ってないけどHydraをトレモロ目的で使ってて、あとSpiral Array Chorusをちょっと試したりとか、そんな感じ。
もしちょっと音に色味を足したいときは、思い切り回していって、いわゆる速いロータリ/レスリーみたいな感じにすることもあるんだ。古いTCのコーラスには、全部のつまみをフルテンにしてやるとその手の凄いサウンドが出せるモードがあってね。僕の2枚目のアルバム『Ear X-tacy 2』に“Is This What You Want?”って曲があるんだけど、そのソロは全部それで弾いたの。フルテンで回しっぱなし。それがすごくカッコいいトーンなんだよね。実は僕の大のお気に入りのコーラスなんだけど、ちょっとサイズが大きいんだ(笑)。まあでも、ギアって空間を取るし、サイズは大事ってことだよね、グラント。
で、最近僕のボードの写真を見た人がメールをくれて、僕ミニ・チューブスクリーマー載せてるの見てがっかりした僕みたいに言われてさ。僕が改造したTS808を送るから!みたいな(笑)。でもいやいや、このミニでも結構いい音出るんだよ。でもあんまり使わないからさって答えたら、すごく落胆してたよね。僕も古いTS808は持ってるし、めちゃめちゃいい音だけど、時と場合なんだよね。
そういや、君の“ペダル部屋”も見たことあるよ。あれはまあ…ちょっとしたギターショップのペダルコーナーみたいな感じで(笑)。しかも同じペダルが8~9台あるとか。君このスイッチの感触が気に入ってるんだとか言ってたっけ。そういうの面白いと思うよ。
実はね、エクゾティックの“AT シグネチャー B.B.”ペダルの後期バージョンを作るとき、試作機を2種類送ってもらってさ。昔の初期型の“奇跡的にいい音のB.B.”に近づこうと色々試行錯誤してくれたんだけど、どうにも同じにならなかった。ペイントの仕方とかいろんな手を尽くしてくれて、もう大変だったんだよ。で、最終的に送られてきた2台のプロトタイプのうち、「あ、これだ、まさにこの音だよ!」ってやつがあって、彼らは「やっぱりそっちか…実はそれ、すごく微妙なスイッチ使ってて…」と困った顔してた(笑)。本当にマジックペダルって感じだったね。
いや、これはほんとにしょぼいスイッチなんだ。すぐ壊れそうだけど、とにかくこの音が欲しくてさ。だから僕はあえてその“イマイチなスイッチ”を選んだんだよ。するとトップエンドの開放感がびっくりするほど変わったんだ。単に“もっと信頼性の高いスイッチにしましょうか”みたいな話じゃなくて、いやいや、こっちのほうがやばい音がするぞって。そういう、くだらないって言えばくだらない自己追及をしちゃうわけ。でも実際、いろんな細かい要素が積み重なって、最終的なトーンに影響するからね。たとえばエリック・ジョンソンがやってきたことを見れば分かると思うけど、彼はほんと真剣に突き詰めて、あのレベルのトーンに到達してるんだ。
彼は遊び半分じゃなくて、本気で追い込んでたし、“ペダルの角度がどう”とか、いろんな逸話があるんだよ。実際、裏付けとなる話がいろいろあって、いつか別の回で語りたいぐらい。
まあでも僕はエリックのことを本当にリスペクトしてる。彼は並外れて突き詰める覚悟があって、普通の人よりずっと先まで行った。でも彼だって僕いや、結局ギターを弾かなきゃダメでしょ僕と思ってるはず。要はバランスで、“あれこれ深掘りしすぎて結局弾いてない”みたいなのは避けないと、という話だよね。
僕ら、もう1時間以上しゃべってるけど、この話が誰かの役に立てば嬉しい。でも最終的にはやっぱり弾くしかないんだよ(笑)。テクニックや知識を深めるのはいいけど、“演奏しない”んじゃ意味ないから。そこも忘れないでほしい。
だから“追い求めること”の楽しさ、面白さ、イライラも含めてバランスをとりつつ、ずっと弾き続けることが大事。僕ソニック・イクエーション(音の方程式)僕で自分の役割をちゃんと果たす、みたいなね。今うまいこと言ったけど、何言ったっけ(笑)? “あ、それちょっと良かったな”ぐらいに思ってる。
グラントが言った通り、他人の演奏を見るのも同じぐらいの喜びだと思うんだ。特にギター弾き続けてると人によっては飽きるかもしれないけど、僕はジョー・ボナマッサのコンサートに行って、君と奥さんに会ったりしたでしょ。あれ最高だった。ステージ見ながら振り返ると、君が子どもみたいな顔してニコニコ見てるんだもん。アンディ・ティモンズが客席からジョーの超絶プレイを観て喜んでる!みたいな。
僕もライブ行くときは100%没頭するタイプだけど、ジョーを生で見るとやっぱすごい。あの人はトーンマイスターでもあると思う。人生で聴いた中でもトップクラスのライブトーンで、機材やフロント・オブ・ハウスの調整が完璧なんだよ。終演後に「どのギター弾いても耳に痛い音がまったくなくて、エスクワイヤー、ストラト、レスポール、どれもすべて完璧だった」って話したぐらい。演奏もヤバいぐらい上手いし、セットの作り方や曲の多様さも刺激的。それでいて謙虚な気持ちにもなる。
で、2週間ぐらい前に僕はLAでジョシュと録音してたんだけど、ちょうどジョシュとジョーがサンセットサウンドで録音してて、「日曜にジョー呼んで曲に参加してもらう?」って話になって。「いいね!」ってなったけど、いざ来るとなるとちょっとビビるじゃん(笑)。しかも前のアルバムで録り損ねたスローブルースの曲“Ray”をやることになって、まさにジョーのお家芸。ソロを交互に弾いたんだけど、もう完膚なきまでにやられたね(笑)。24時間ぐらい「うわ…負けた…」って凹んでた。
でもあとで聴き返したら自分の音はちゃんと自分だし、まあOKと思えたけどね。ジョーは59年製のレスポール(棚から適当に引っぱり出したやつ!)を持ってきて、ジョシュのリグに挿しただけで完全にジョーの音。すごく謙虚にさせられるし、同時にインスピレーションにもなる。つまり「もっと頑張ろう」ってね。あとでジョシュがインスタに一部アップしたら、ギターチャンネルが一気に取り上げて「うわ、マジか…」って(笑)。ジョーは本当に凄かったよ。
だからもしまだジョー見たことない人がいたら、ぜひ行ってみてほしい。彼今年もツアー多いしね。僕は「大物のライブは観るべき」と常に言ってる。めちゃくちゃ刺激を受けるし、「ああ、こういう音はこうやって出すんだ」って学べるから。
僕は彼やジョシュみたいなブルースは弾けないけど、まぁそこそこトライはする(笑)。演奏聞いて“ダメだ”って凹む瞬間もあるけど、最終的には別にジョー・ボナマッサになる必要はない、自分の道を行けばいいって思えるようになった。昔は落ち込んでたけど、50過ぎてようやく「ああ、僕は僕でいいんだ」って心底思えるようになったんだよね。でもその分、若い頃はマジで落ち込むことも多かったから、気をつけなきゃね。
でも最後は「スティーヴ・ヴァイとかサトリアーニ観て“できるかは別として、これが可能なんだ”って分かって、頑張ろうって思う」みたいに結びつくんだ。そこが健全なスタンスだし、僕はライブ会場で“ああ、この音楽を体験できるって生きてて最高じゃん!”って思ってるから、君が振り返って僕を見たときに子供みたいな顔で喜んでたんだと思うよ。あれって結構長く心に残るんだ。
いやあ、ありがとう。すごくいい回だったし、この1時間半は楽しかった。
グラント何か最後に言いたいことある? 僕は「フリーバードを弾いて締める!」とか言ってるけど(笑)。
よし、じゃあこれからアンディにバラード曲“On Your Way Sweet Souls”を弾いてもらおう。リクエスト多かった曲で、僕もバラード好きなんだよね。で、ここはギアの話もしてるから、Muse Driverをふんだんに使う。メインはMuseで、ハイゲインに切り替えるときはJHS-ATにもう1台のMuse(ゲルマニウムモード)をブーストとして使って、Haloディレイもどーんと派手にかける。じゃあちょっと音源用意したから流すね…(演奏)
いやー最高。じゃあ2小節目でパンチインしてもらおうかな、実はちょっと修正したい(笑)。冗談だけど、録音ものじゃないって証明のためのわざとしたミスだよ(笑)。
でもアンディ、ミスってもニコニコしてるよね。自分を責める感じじゃなくて自然に笑っちゃうというか。そこがいいんだよ。“生なんだし、しょうがないじゃん”みたいな。
あの曲は毎回アレンジ変えて弾くから、ある意味自分で自分を追い詰めてるんだ。コーラス部分はちゃんとメロディ守ってるけど、ヴァースはオリジナル通りに弾かなくなってきて、その場でフレーズ考える。上手くいくときもあれば空振りのときもあるけど、そのスリルが好きなんだよね。とにかく楽しかった。ありがとう、アンディ。
こっちこそありがと。君んとこ10分だから、外出たら音聞こえるんじゃない(笑)?…まあ近所迷惑だな(笑)。
じゃあ僕たちは“トーンの街”に向かってマツダ・ミアータに乗り込み、温かいコーヒーと氷の溶けた水を手に帰るよ(笑)。今回も聞いてくれてありがとう。
次回また話そう。僕はちょっとボードを直したいとこあるから、また店寄るわ。
じゃあまた! ありがとう。
(以上。BGM)僕
※このサイトは、アンディ・ティモンズのファンサイトです。公式ではありませんが、アンディはこの存在を知っています笑
このサイトは収益化などは一切していなく、純粋にアンディ・ティモンズを応援し、アンディの良さを多くの人と共感したいという目的で運営しています。
2025年の3月の来日がより楽しくなるとよいなと思い、僕自身も楽しみながら記事にしています。
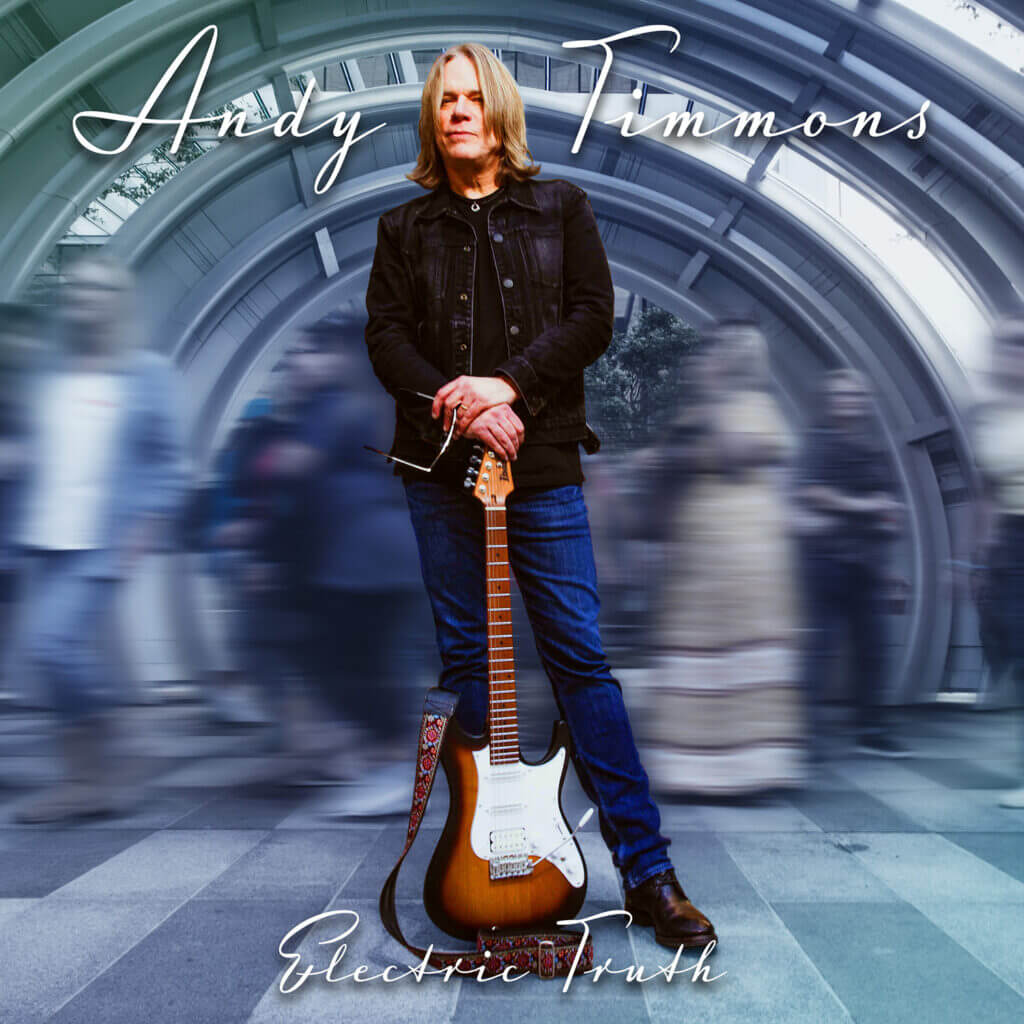

コメント