2025年4月にアップロードされた、ピックアップメーカー「Dimarzio」の創設者ラリー・ディマジオとの対談をAIを使って日本語翻訳しました。
元記事はこちら
https://www.dimarzio.com/stories/andy-timmons-conversation-larry-dimarzio
翻訳内容
ラリー・ディマジオ:
会えて嬉しいよ、アンディ。ちょっと気になったんだけど——その後ろの壁に並んでるアンプ全部って、ここは君のレコーディングルームなの?
アンディ・ティモンズ:
やあラリー!基本的にはそうだね。使ってるアンプヘッドはほとんどここにあって、キャビネットは別の部屋に置いてあるんだ。じゃないと、ここがちょっとうるさくなっちゃうからね。でも、まあ、ここが僕のスタジオって感じだよ。パンデミックの間は、ここからたくさん配信もしてたよ。ライブストリーミングのギグとか、いろいろね。
ラリー:
うん、他のビデオでも君の後ろにアンプがたくさんあるのを見たよ。あれはすごいコレクションだよね。そこが君のスペースなのか、それとも誰か他のスタジオを使ってるのか気になってたんだ。
アンディ:
うちはね、もう28年住んでるんだ。だからまあ、それなりに時間も経ってて、物も溜まるよね。僕はちょっと物をためこむ性格なんだけど、実はもうすぐ「ガレージセール」をやるんだ。Guitar Sanctuaryが、いろいろ持ち込んで売っていいって言ってくれて。だから、もう使わないものは手放そうと思ってる。もしこの部屋の散らかりようを見たら驚くと思うよ(笑)。
そろそろいろんな物を手放す時なんだ。ふと「俺、何やってるんだろう?」って思ってね。最近は物が増えすぎて、創作の妨げになり始めてた。前向きにするどころか、逆に足を引っ張るようになってたんだよね。まあ、恵まれてることには違いない。ほんとにありがたいことなんだけど、やっぱり手放す時期だなって。必要としてくれる誰かが使ってくれるかもしれないし、その人にとって意味のあるものになるかもしれない。で、自分は本当に必要な物だけを残して、それをもっと使っていこうっていう考えなんだ。
ラリー:
うん、僕もいろいろ減らしてるところ。何が本当に必要かって考えてね。ルールを作ったんだ。新しい物は、それを買う分だけ何かを売った時にしか買わないって。それが新しい指針になってる。この前、新しいLynx Hilo IIを買ったんだけど、すごく良いよ。
アンディ:
ああ、その言い訳、僕も前に使ったことある(笑)。でもね、結局買ってばっかりで、手放すのを忘れちゃうんだよね。「ちゃんとした意図」はあったんだけどさ。うん、でも今は違う。今回は本当に手放す気になってる。すごく気分がいいんだ。いい「断捨離」になると思うよ。
ラリー:
この前、屋根裏部屋にしまってあったネックやボディ、ギターをたくさん見直したんだ。30年くらい誰にも見られてなかったやつら(笑)。それで、そのパーツのいくつかでベースを一本組んだんだ。いい感じだったよ。いろいろ物を見てると、「なんでこれ持ってるんだろう?」って思うんだよね。でも、これって他の誰かにとってはすごく楽しいものになるかもしれないって思ったんだ。
アンディ:
うん、本当にそうだよね。
ラリー:
もう、物は増やさない。床に物があるのもイヤなんだ。Mark LevinsonのML 2パワーアンプ(重さ70ポンドのモノブロック)を4台売ったんだけど、急に床のスペースがめっちゃ空いてね。ほんと、それだけで気分がすごく良くなった。
アンディ:
それがまさに今、僕がやってる「断捨離」の大きな理由なんだ。実は数週間前と比べて、この部屋、ずいぶん片付いてるんだよ。だから、もうすでに空間が良くなってる。気分もいいしね。僕ら、ちゃんと正しい道を進んでると思うよ。
ラリー:
君のコレクションは素晴らしいよ。そして、「間引き」すれば、もっと素晴らしくなるね。
レコーディング用の作業をするときはいつも、隣の部屋に置いてあるMesa Boogieの212キャビネットを2台使ってるんだ。どちらも常にマイクを立ててあって、Vintage 30のCelestionスピーカーを搭載してるよ。最初はLone Star(アンプ)から始めることもあるけど、試せるものはいろいろ揃ってるんだ。見ての通り、SuhrのSL68はすごくいいアンプだよ。MarshallのPlexiを本当によく再現してくれていて、ここ(自分の肩越し)にある本物のPlexiも持ってるけど、もしあの“Marshallらしい前に出る音”が欲しい時には、いつでもそっちを使えるようにしてるんだ。
アンディ:
うん、まさにそう。今ちょうど、キャビネットとアンプヘッドを自由に組み合わせられる、かなり賢いやつを注文したところなんだ。どんな組み合わせでもミックス&マッチできるんだよ。
ラリー:
おぉ、それはワクワクするね!君の空間、かなりいい感じにチューニングされてるよね。ギターをレコーディングする時って、基本的にどんなセッティング?DIで直接コンピューターに入れて、後からいじるの?それともアンプ→マイク→プリアンプっていう流れ?
アンディ:
うん、ほとんどいつもアンプとキャビネットからだね。普段の練習はオフィスでやってるんだけど、そこには今はもう廃盤になってるMesa BoogieのLone Starヘッドが2台あって、それをSuhrのIRスピーカー(キャビネット・シミュレーター)と組み合わせて、コンピューターに通して使ってる。それも結構いい音なんだ。
でも、本気でレコーディングするような作業のときは、隣の部屋にあるMesa Boogieの212キャビネットを使ってる。常にマイクが立ててあって、Vintage 30のCelestionスピーカーが入ってる。最初はLone Starで始めることもあるけど、他にもいろいろ試せる選択肢はそろってるよ。見てもらえば分かると思うけど、SuhrのSL68は本当に素晴らしいアンプで、MarshallのPlexiを見事に再現してる。ちなみに、本物のPlexiもここ(肩越し)にあるよ。だから、あの「Marshallっぽい押し出し感」が欲しいときは、そっちに切り替えられる。
マイクに関しては、基本はSM57からスタート。場合によってはリボンマイクも足すよ。最近よく使ってるのはMesanovicっていうリボンマイクで、以前Josh Smithと一緒に仕事したときに初めて使ったんだ。でもやっぱりSM57は安定してる。自分の耳が求めてる音なんだよね。長年スタジオでトーンを作ってきたけど、ずっとこれがベースになってる。それから、Neveの1272プリアンプも持ってるよ。
ラリー:
古い1272?それとも新しいやつ?
アンディ:
古いやつ。初期のBrent Averillラック仕様で、昔のコンソールからのものなんだ。
ラリー:
僕もBAEの機材は大好きだよ。あそこは人も素晴らしくて、仕事しやすいんだよね。聞いた理由なんだけど、僕もギターを録るときはSM57と、Beyer DynamicのM160リボンマイクを組み合わせて使ってるんだ。Eddie Kramerに感謝だね(笑)。君のやってることと、かなり近いと思うよ。
アンディ:
うん、僕もそれ系のマイク持ってる。1273っぽいやつで、独立した筐体に電源が内蔵されてるやつ。Brent Averillのやつは電源が別だったけどね。
BAEの機材は本当に音がいいよね。それに、リボンマイクはSM57にはない暖かみを加えてくれるんだ。だから、もうちょっとふくよかさとか低域が欲しい時に重宝するし、SM57のちょっとしたキツさを和らげてくれるんだ。でも、結局のところ、マイキングの位置が一番大事なんだよね。
その“スイートスポット”にピタッとハマったときの楽しさって、ほんと格別だよ。
ラリー:
これはきっと気に入ると思うよ。ニューヨークの屋根裏部屋を整理してたら、なんとオリジナルのG12M25 Celestionスピーカーが3つ出てきたんだ。しかも、コーンまでオリジナル。いやあ、あのスピーカーは本当に大好きなんだよ。
アンディ:
うわぁ、すごいね。
ラリー:
ブラックバックが2つに、グリーンバックが1つ。
アンディ:
うわ、うわ、うわ、うわ。いいなあ。それって、何年製だと思う?ラリー。
ラリー:
買ったのは1970年代中頃だよ。当時はフルタイムで演奏してて、まとめていくつか手に入れたんだ。誰かがアンプを改造してほしいって持ってきたときには、必ずそのCelestionスピーカーに交換してた。ギターにとって、あのスピーカーの音のほうがずっと良いって思ってたからさ。
アンディ:
うん、もう実績が物語ってるよね。あの音って、まさに“あの音”だもん。
ラリー:
まさにそれ。で、音の話つながりで言うとさ、君がアビイ・ロードであの2曲を録音しに行ったの、ほんとにクールだったよ。
アンディ:
ありがとう。本当に“バケットリスト”のひとつだったよ。特に僕らみたいな世代にとってはね。ビートルズは、僕たちの人生のサウンドトラックみたいなものだったし、その音楽は今でも多くの世代をインスパイアし続けてるし、愛されてる。それはずっとやりたかったことの一つだったし、他にもビートルズ巡礼をしたがっていた友人が何人かいてね。
長年イギリスをツアーで回ってきたけど、実は観光ってあまりしてなかったんだ。アビイ・ロードには一度だけ、観光で行ったことがあって、その時はBrian Kehew(ギア関連の歴史家)がやってた講義に参加できたんだ。彼はビートルズのスタジオ機材、特にアビイ・ロードのスタジオ2について書いた素晴らしい本も出してる。
でも今回は、アビイ・ロードのスタジオ2で1日だけレコーディング時間を確保するっていうのを中心に旅を組み立てたんだ。もちろん、スタジオはレンタル可能なんだけど、簡単ではないし、ちょっと高くつく。でも、何人かで費用を分担すれば何とかなる。運よく、ロンドンからそう遠くないスウィンドンにいる親友のダニエル・スタインハートが、僕が普段使ってるMesa Boogieの機材を持ってきてくれたんだ。それに加えて、彼自身の61年製Vox AC-30トップブーストもね。
僕も’65年製のストラトを持っていったよ。ビートルズのトラックで演奏してる、ジョン・レノンの「I’m In Love」って曲では、そのギターを使ってる。’64〜’65年のビートルズのトーンを狙ってたんだ。「Nowhere Man」のギターサウンドって、僕にとっては本当に好きな音のひとつでさ。すごく明るくてクリアなのに、耳障りじゃない。
ジョンとジョージのストラトは’63年か’64年製で、色違いじゃなくて、ソニックブルーでお揃いだったって言われてるよね。で、神話では、2人が同じVoxアンプに同時に繋いで、ユニゾンでギターを弾いたっていう話がある。真偽はともかく、確実にダブルトラックではあるし、2本のストラトが同じパートを演奏してるのは間違いない。それに、AC-30トップブーストってすごく明るいアンプだし、レコーディングのときにミキサーで高音域を目いっぱい上げてたらしい。コンプレッションも強めにかかってるけど、ほんとに美しいトーンなんだよね。で、僕もかなり近い音を出せたと思うよ。
ありがたいことに、事前に連絡を取り合っていたエンジニアが、セッションの前に「どんな音を目指してる?」って聞いてくれてさ。「モダン・ヴィンテージって感じかな」と答えたんだ。あと、「これは’63年にジョン・レノンが書いた曲で、ビートルズ自身は録音してないんだけど、イメージとしては’64年のビートルズの感じだよ」って伝えたんだ。
で、実際に現地に行ったら、彼がオリジナルのマイクを全部用意してくれてて。つまり、ビートルズが実際に使っていたマイクだよ。あそこは、今でも世界屈指のマイクコレクションを持ってるんだ。
ラリー:
マイクロッカー(マイク収納室)を紹介する動画を何本か見たことがあるんだけど、すごいよね。
アンディ:
うん、本当にすごいよ。Neumannのマイクが全部揃ってて、ドラムにも当時と同じマイクが使われてた。Ludwig(ラディック)のドラムセットも用意してくれてて、僕も少しだけ叩いたよ。あまり上手くはないけど(笑)、リンゴ・スターは僕のヒーローなんだ。それからボビー・グレアムも。彼についてはまた別の話だけど、イギリスのドラマーね。
で、全部オリジナルのマイクがあの部屋にあるんだ。ソロでやった曲のひとつ、“Truth”っていう僕のエレキギターのオリジナル曲があるんだけど、それをあのスタジオで弾いたんだ。
もしビデオを見てもらえたら分かるけど、あれはMesa Boogieのステレオ・リグと、KeeleyのHalo Echoを使ってる。でも、僕がヘッドホンをつけてないのが見えると思う。通常だったら、自分の音を確認して、録音される音をちゃんと聴きたいところなんだけど、あの部屋の響きがあまりに素晴らしかったから、ヘッドホンは不要だった。もう、ただ弾きたくなってしまったんだ。エンジニアがU67を2本立ててくれて、さらにルームマイクも立ててくれた。それがそのまま、あのサウンドなんだよね。何も足す必要がなかった。
もちろん自分のエコーをかけながら演奏してるけど、あれがそのまま部屋の音。スネアドラムを叩いたときでさえ、そのまま“聴こえる”んだ。
ラリー:
部屋自体に個性があるよね。君の声を聴いたときも、あの部屋の響きが感じられたと思ったよ。
アンディ:
ああ、それは間違いないよ。あのときも、あのスタジオのマイクで歌ってたんだけど——たしかM50だったかな、M49だったかな。正確には覚えてないけど、とにかく彼ら(ビートルズ)が実際に立って歌ったその場所で僕も歌ってたんだ。しかも、2テイクだけで済んで、それが良い出来だったから、テキサスに戻って録り直す必要もなかった。時間の関係でその日はベースが録れなかったから、ベースだけはこっちのテキサスで録ったけど、他は全部あそこで完成できたんだ。
ラリー:
いや、それは本当にすごいことだよ。スタジオを“見学”するだけでもすごいのに、実際に“録音”までできたなんて……ワオだよ。
アンディ:
まさにその通りだよ。
ラリー:
僕も10年くらい前に、ジョー・サトリアーニと一緒にL.A.のEast Westスタジオ(昔のWestern Recorders)でレコーディングしたことがあるんだ。DiMarzioのプロモーションビデオの撮影でね。
アンディ:
ああ、あのビデオ見たことあるよ。
ラリー:
僕らが使ったのはスタジオ3でね。ママス&パパスが「California Dreamin’」を録音した部屋なんだ。ジョー(サトリアーニ)との録音は最高だったよ。あそこでのレコーディングは本当に楽しかった。すべてがトップクラスだった。
アンディ:
うわぁ、すごいなあ。
ラリー:
そのときは「ここにいるだけでカッコいい気分だ」って思ったよ。
アンディ:
「California Dreamin’」は僕の人生で一番好きな音のレコードの一つだよ。なんというか……あの曲って、すごく“心に残る”作品だよね。アレンジも録音も美しくて……あのヴォーカルの感じ……ほんとに、すごい。
ラリー:
伝説的なスタジオに入って、自分なりの“歴史の一片”に触れられるって、面白い感覚だよね。アビイ・ロードで録音する前に、何かイメージしてたことはあった? 実際に行ってみて、思ってたのと違った部分とかはあった?
アンディ:
まず最初に感じたのは、やっぱり中に入った瞬間の圧倒されるような感覚だったね。というのも、あそこは本当に、見た目が60年代にビートルズがレコーディングしていた当時とほとんど変わってないんだ。外観も含めて、本当にそのまま残してある感じだったよ。そして、あの“音”だよね。あの空間に入ると、やっぱり心が震えるんだ。
それでエンジニアの人たちが教えてくれるんだよ。「ここがポールが“Blackbird”を演奏した場所です」とか、「あの椅子がたぶん彼が座ってた椅子です」って。いまだに当時の赤いスタッキングチェア(重ねられる椅子)がそのまま残ってるんだ。
でもね、一緒に行った友達2人が最初にちょっと演奏と録音をしたいって言ってたから、最初の1時間くらいは彼らに任せたんだ。そのあとで、僕は「残り9時間ある……よし、働こう!」って(笑)。「本気出すぞ」って気持ちだった。
よく「その場所に立つと圧倒されるんじゃない?」って聞かれるんだけど、全然そんなことなかった。むしろ、人生ずっと観てきた映画の中に、自分がそのまま入ったような感覚だったんだ。
ラリー:
うわぁ、それはすごい。
アンディ:
本当に……今思い出しても鳥肌が立つよ。すごく“帰ってきた”って感じがした。僕はこれまでにたくさん録音してきたけど、あの空間の歴史を知ったうえでそこに立つと、普通はちょっと圧倒されてもおかしくない。でも、実際はすごく自然体でいられた。自分ができる限り最高の時間の使い方をしようって思っただけだったよ。
僕はセッションの回し方も分かってるから、「できることを全部やろう」って感じで臨んだんだ。
ラリー:
ベースを除いて2曲を9時間で録り終えたって、すごいことだよ。
アンディ:
実は他にもいくつか録ったんだよ。アコースティックギターと歌だけのソロ曲も録ったし、それに、ジャム・トラックみたいなものもあって、それには友達全員で参加してもらった。あの日は結構詰め込んで、やることいっぱいだったよ。というのも、僕だけのための時間じゃなかったからね。一緒に来た友達たちもこの時間に出資してくれてたから、みんながそれぞれの時間を持てるようにしたかったんだ。
で、その友達の一人、デニス・ポゲンバーグっていうんだけど、彼は本当に素晴らしいギタリストなんだ。でも、彼にとってはその日が“人生初”のレコーディングセッションだったんだよ。それも、60代にして初めて、しかも場所はアビイ・ロードのスタジオ2(笑)。
ラリー:
わお!
アンディ:
ねえ、どこからキャリア始めたの?って聞かれて「最初のセッションはアビイ・ロードだったんだよ」って(笑)。彼もすごく楽しんでた。本当にいい時間だったよ。
ラリー:
それでさ、あのJ160はどこから来たの?
アンディ:
ああ、それはこのプロジェクトとは関係ないんだ。
ラリー:
なるほどね。
アンディ:
あれは少し前に録った別のトラックなんだ。Valve Studiosでミックスしたやつ。アコースティックで録音していて、使ったのは僕の1963年製のJ160さ。アビイ・ロードにもギブソンのアコースティックが置いてあって、それも使ってみたんだけど、やっぱり1963年にジョン・レノンが書いた曲には、あの音じゃなかったんだよね。
そのJ160は、ベースを録ったテキサスのスタジオ――Casey Di Iorioのところで弾いたんだ。彼がその曲のミックスもしてくれたんだけど、ものすごく素晴らしい仕上がりだった。あのアビイ・ロードのプロジェクトは、自分のキャリアの中でも本当に誇りに思っている作品の一つだよ。
ラリー:
面白いものを見せるよ。(ギターの写真を見せる)
アンディ:
えっ、何これ!?
ラリー:
そうなんだよ。
アンディ:
なんてこった……すごく美しいじゃないか。サイドは何の木材?
ラリー:
ブラジリアンローズウッド(ハカランダ)だよ、バックとサイドに使ってる。
アンディ:
わぁ、本当に見事だね。
ラリー:
トップはアディロンダックスプルースで、ブリッジも指板もブラジリアン。
アンディ:
いいねぇ。
ラリー:
しかも、壁から下ろしてもチューニングばっちり。
アンディ:
最高だね。
ラリー:
あとは、これが勝手に弾いてくれたらな(笑)
アンディ:
はは、言おうとしてたんだけど……“ちょっと作業が必要”ってね。でも本当に素晴らしい仕事だよ。いやあ、すごい。
ラリー:
これは親友のケビン・コップと一緒に作ったんだ。昔からJ-45のファンでね。これはほぼ160の仕様だけど、オリジナルはソリッドウッドだったんだ。ギブソンがフィードバックを抑えるために合板(ラミネート)に切り替えたんだけど、僕はJ-45のボディサイズで音をもっと良くできるという自分の理論を試してみたかった。
最初に試作したときは、当時持ってたオリジナルの1960年製J-45と比べて、全ての面で自作の方が良かったから、1週間以内にギブソンは売っちゃったんだ。
J-45のボディサイズはもっと引き出せるものがあると思ってた。最近のモデルでは、スケールを25.5インチにして、ナット幅を広くし、スキャロップド・ブレイシングを入れて、’30年代風の“カウボーイ・ピックガード”も採用してる。これでJ-45タイプを作るのは4本目なんだけど、毎回改良を重ねてるよ。
ギブソンの大型アコースティックの音って昔から好きじゃなかったんだ。J-200は特にひどい。見た目は最高なんだけど、ギブソンはボディ内部の空気量の設計に失敗してるんだ。
その理由がはっきり分かったのは、自分でバスレフ型(ポート付き)のスピーカーキャビネットを作り始めたときだった。スピーカードライバーって、キャビネットの内部空間のボリュームに合ってないといけない。ちゃんと合えば効率も上がるし、歪みも減る。でもJ-200は、ボディサイズとサウンドホール、ブリッジの重さ、ブレイシングの配置など、あらゆる部分の設計ミスで音がダメになってるんだよ。(※ギターを弾く)
アンディ:
ほんとに美しいよ、マジで。
ラリー:
まぁ、“ギークになる”のも僕の仕事の大部分なんだよ(笑)
アンディ:
ああ、まさにそうだよ。でもこれは、かなり“高レベルなギーク”だよね。まさにマスタリー(熟練)の域だよ。
ラリー:
僕はギターのリペアマンだし、今でもそれが自分の本質だと思ってる。仕事としてもね……僕の目的は常に「音をよくすること」なんだ。ギターのフレットを打ち直そうが、ピックアップの配線を改造しようが、何をしようが、それで音が良くなるなら何でもやるよ。さて、アビイ・ロードの話に戻ろうか(笑)。僕のJ160話で話が逸れちゃったね。
アンディ:
いや、むしろ大歓迎だよ。
ラリー:
で、マイクロッカーはやっぱりすごかったわけだけど、他にも驚いたことってあった? ミキシングコンソールとか、アウトボード機材とかさ。
アンディ:
ああ、あったよ。「聖杯」みたいな機材が2つ、2階に置いてあった。あの有名な階段を上がっていくと、コントロールルームがあるんだけど、ジョージ・マーティンやジェフ・エメリック、それにノーマン・スミスがいた場所だよね。そこからは、下のスタジオ、つまりビートルズが実際に演奏していた場所を見下ろせるんだ。
僕のインストゥルメンタルソロの最後の映像にもそのシーンがあるよ。演奏の最後、僕が上を見上げてるんだけど、それはエンジニアのリアクションを見るためなんだ。「今のどうだった?」「うまくいったかな?」ってね。
で、階段を上がっていくと、コントロールルームがあって、見たらすごく現代的になってた。でっかい最新のNeveコンソールが置いてあって、その上にはたくさんのラックマウント機材が積まれてたんだけど、その中に黒い大きなボックスが2台あったんだ。それを見て、「ああああああ……」ってなったよ(笑)
それは……Fairchild 660だったんだ。あの伝説的なコンプレッサー/リミッターで、ビートルズのあらゆるレコードに使われていたやつだよ。しかも、それはまさに“本物”で、あのベースとドラムのサウンドを作っていたやつ。マッカートニーは今でもそれを使っているらしいしね。あれを見た瞬間は……うん、あれもまた、あの歴史的サウンドの一部だったよ。
あのスタジオで、あのマイクを使って、ビートルズが実際に使っていた機材で音を処理する――それはもう、本当に信じられない体験だったよ。
でも最終的には、あれはジョン・レノンが書いた“良い曲”に過ぎなくて、僕のやるべきことは、それをできる限り良い演奏で届けることだったんだ。
当時も何人かのアーティストがあの曲をレコーディングしていて、最終的にはThe Foremostという、ブライアン・エプスタインが手がけてた別のバンドに渡されたんだけど……彼らの演奏はまあまあだった。でも正直、あの曲のポテンシャルには達してなかったと思う。僕は個人的に、あれは“失われたビートルズの曲”だと思ってる。だって、彼ら自身が録るべきだったと本気で思ってるからね。
そういう意味で、これは「愛情を込めたプロジェクト」だった。あのスタジオにいて、「よし、時間がある……自分の曲を一つ録って、あとはビートルズに関連する何かをやろう」と思ったんだ。で、その曲(“I’m in Love”)が一番しっくりきた。知ってる人が少ない曲だからこそ、スポットライトを当てる価値があると思ったんだ。
ラリー:
まったくその通りだよ。あの曲、すごく“ビートルズっぽい”サウンドになってたもん。
アンディ:
ありがとう。
ラリー:
本当に、あの演奏はビートルズを体現してる感じがしたよ。
アンディ:
それはものすごく光栄な言葉だよ。本当に大きな褒め言葉。でも、それはもう僕のDNAなんだ。僕は’63年生まれで、まさにあのムーブメントが始まった年。しかも、当時12歳年上の兄がいて、リアルタイムでビートルズのレコードを全部買ってたんだ。だから、僕にとっての最初の音楽的記憶って、「I Saw Her Standing There」のギターソロなんだよ。そのリバーブがかったギターの音を今でもはっきり覚えてる。それ以来、僕が“ウェットなギターサウンド”を愛してやまない理由もそこにあるんだ。もう……完全に刷り込まれてる(笑)。
あの音楽は、僕の人生にずっと寄り添ってきたんだ。それなしの人生なんて考えられない。ジョンの歌い方、リンゴのドラミング、ジョージのギター……もう一生ものの情熱なんだよ。だから、もし誰かが僕の演奏を“あのサウンドに近い”って言ってくれるなら、それは本当に名誉なことなんだ。
ラリー:
君も言ってたけど、本当に「バケットリスト」にふさわしい体験だったよね。今度また行くときは、声かけてよ、ハハ。
アンディ:
ぜひ来てよ! こういうのって、実現できることなんだよ。もちろん簡単ではないけどね。
彼らも、ある程度“ふるい”にはかけてると思う。けど、最終的には、僕たちがちゃんとスタジオ料金を払う意思があって、真剣に作品を作るつもりだっていうのを分かってくれればOKだった。条件としては、予約の確定が1か月前くらいになるってことぐらいかな。というのも、例えばRadioheadみたいな大物がその週を使いたいってなれば、当然そっちが優先されるからね。それはまったく理解できる話。
でも、最終的には“GOサイン”が出て、実現したんだよ。本当にすごい旅だった。最初の数日はロンドンにいて、その後リバプールにも行ったし。あと、僕のペダルショー仲間のダンとミックと一緒に、The Cavern(ビートルズゆかりのクラブ)でギグもやったんだ。
ラリー:
面白いな(笑)
アンディ:
“ビートルズ巡礼”としては、ほぼ完璧なルートだったと思うよ。
ラリー:
うわぁ。
アンディ:
最高の旅だったよ。
ラリー:
だからさ、今度またやるときは絶対教えてね。
アンディ:
また行けたらいいなあ。
ラリー:
僕がマイク立てるよ。
アンディ:
ぜひ来てよ、エンジニア・ラリー(笑)
ラリー:
じゃあ白衣を着て、“本場の紅茶の淹れ方”を覚えて、イギリスの組合カードも取らないといけないな(笑)
アンディ:
当時はそれがルールだったからね。みんな白衣を着てて、アーティストは機材に触っちゃいけなかった。全部エンジニアがやるって決まりだった。でも、ジェフ・エメリックが入ってきた頃には、少しずつ緩くなり始めてたんだ。
ラリー:
僕が本格的にレコーディングにハマったのは、ビデオ撮影を始めたのがきっかけだったんだよ。最初に読んだ本は、ジョージ・マーティンの『All You Need is Ears(耳こそすべて)』だった。
ラリー:
君が今、新しいアイバニーズのギターを開発中なのは知ってるよ。それで、シングルコイル・ピックアップのサンプルをいくつか送ったけど、もう試してみた?
アンディ:
正直に言うと……まだなんだ。いろいろ忙しすぎてね。ちゃんと向き合う時間を取りたいんだよ。今はレコードの仕上げに集中していて、本当にがっつり取り組んでるところだから。だからこそ、あのピックアップについても、ちゃんと時間をかけて向き合って、ラリー、君と一緒にちゃんとやりとりを重ねながら「これだ!」っていうところまで持っていきたいと思ってる。それだけ特別なことになりそうだし、もっと本物っぽいヴィンテージ・トーンを追求する機会になるからね。
言うまでもなく、僕はずっとCruiserを使ってきてる。1994年からだからね。最初のプロトタイプ……後ろに見える、もう30年間弾き続けてるあのギター。それがずっと僕の“ネック・ピックアップの音”だったんだ。
ラリー:
DiMarzio AT-1™(DP224)も使ってるよね。
アンディ:
そうそう。考えてみると、今やそれも「ヴィンテージ」って言われる時代なんだよね。あのギターなんて、もうフレットを8回も打ち直してるんだけど、それでもまだしっかりしてる。あれはブリッジ用のCruiserがネックに入ってるんだ。なんでそうなったのか正確には覚えてないけど、たぶんオリジナルのハムバッカーに合うように、ビル・カミスキー(DiMarzioのスタッフ)が提案してくれたんだと思う。
でも今では、もちろんAT-1™を君たちが僕のために作ってくれてるよね。
ラリー:
うん。
アンディ:
あれは本当に素晴らしい。ハムバッキングでノイズもないし、最初はIbanezの仲間の勧めで何気なくCruiserを試してみたんだけど、そこからずっと僕のサウンドの一部になっちゃったんだよね。まさに“偶然の幸運”というか、自分の理想にぴったりハマったピックアップだった。シングルコイルのような音色だけど、実はハムバッキングで、僕にとっては理想的だった。
だから、例えば「Electric Gypsy」みたいな曲を聴いた人が「あの音!」って感じるなら、それはまさにこのギターで出した音なんだ。あれは1994年のことで、その曲ももう同じく30年前の作品になっちゃった。
ラリー:
Spotifyで何百万回も再生されてるしね。
アンディ:
あぁ、誰かが気に入ってくれてるみたいだね(笑)。たぶん聴いてるのは2人くらいしかいないけど、その2人がめちゃくちゃ聴いてるんだよ(笑)。でも、ほんと驚きだよね。どの曲が誰かに刺さるかなんて、絶対に予測できない。作ってる時は「届けばいいな」って願うしかない。
で、あの曲は、クイーンズに住んでた「Danger Danger時代」に、ルームメイトとジャムってる時に即興で生まれたんだ。カール・シュミットっていう僕のルームメイトがドラムを叩いてて、一緒にジャムしてた時に出てきた。
当時ちょうど、ジミ・ヘンドリックスの伝記『Electric Gypsy』っていうすごく面白い自伝を読んでてね。だから、完全にタイトルはそこからそのまま取ったんだよ。明らかにヘンドリックスにインスパイアされたリフだったしね。
で、その曲を書いて、テキサスに戻って、このギターを作って、それが今もずっと僕のメインギターなんだ。30年間、信じられないよね。
ラリー:
君って、ただの素晴らしいギタリストってだけじゃなくて、“トーンの人”でもあるんだよね。演奏だけじゃなく、手や頭の使い方、機材との向き合い方、その全部を含めて。
アンディ:
はは、それ全部ってなると、かなりの要素だね(笑)
ラリー:
よく「このピックアップとあのピックアップの違いは?」とか、「オールドのレスポールと今のとでは何が違うの?」って聞かれるけど、そういう人たちは“全体のパッケージ”ってものを忘れてるんだよ。ピックアップやギター単体の話じゃなくて、全部が合わさっての音なんだ。
もちろんピックアップは大事な要素だけど、それって「僕がマイクに向かって歌う」のと「アデルがマイクで歌う」くらいの違いがあるわけで……そりゃ、同じにはならない(笑)
アンディ:
ああ、それは良い例えだね。完璧な“対比”だ(笑)
ラリー:
その間には、すごくいろんな要素が詰まってるよね?
アンディ:
もちろんさ。君が“手”と“耳”の話をしてくれるのがすごく嬉しい。みんな“手”の話はするけど、実は“耳”から始まると思ってる。さらに言えば、“想像”から始まるんじゃないかな。自分が頭の中に持っている「理想のトーン」のイメージ。それって、たいてい自分のヒーローから影響を受けてると思うんだ。
誰しも「あの音に近づけたら……」って思うものがあって、でも実際にはなかなかそこまで行けない。それでも、そこに向かって進んでいく中で、自分自身の“声”や“サウンド”が見つかっていく。そんな感じなんだよね。
自分が「どんな音を出したいか」っていうビジョンがあって初めて、それを“手”に指示して、今持っている機材からそれを引き出そうとできるわけで。もちろん、良いアンプ、良いピックアップ、良い弦、良いピック……そういうのが揃ってるに越したことはないけど、最終的には、自分の頭の中にある“音の記憶”を、どれだけ引き出せるかにかかってるんだと思う。
僕はそれを“auralect(オーラレクト)”って呼んでるんだ。造語だけどね。
つまり、「自分の中にある音や音楽の記憶の集積体」から、いかにして今ある機材でそれを具現化するか。それが鍵なんだ。
よく言われるのが「デヴィッド・ギルモアなら、ピグノーズ(小型アンプ)につないでも、彼の音になる」っていう話だけど、昔の僕も「うん、自分もどこでも自分の音が出せるんじゃないかな」って思ってたんだ。
でもある日、親友のラリー・ミッチェルに呼ばれて、NAMMショーの関連イベントかなんかで、バーでジャムに参加したんだよ。「遊びに来なよ、セッションしよう」って。ラリーとは何度もジャムしてるし、NY時代の仲間で本当に素晴らしい人なんだけど、そのときは他のギタリストの機材を借りて演奏したんだ。
で、もう……何をやってもダメ(笑)。何をどうしても全然良くならなくて、「あ、この“どこでも自分の音が出せる”っていう神話はウソだな」って思った(笑)
すごく謙虚にならされた瞬間だったよ。「ありがとう、じゃあおやすみ」って感じで(笑)
ラリー:
それ、よく分かるよ。僕らDiMarzioがやってることも、まさに“微調整”なんだよね。最後のタッチを加えて、バグを取り除く。だから、ギタリストは自分のギターを手に取って、そこそこのアンプにつないで、1200個のプルダウンメニューなんか開かずに「自分の音」が出せる状態じゃないとダメなんだ。
1年前に新しいカメラを買ったとき、販売員が全部の設定メニューを丁寧に説明してくれたんだけど、説明が終わったあとにふと思ったんだよ。「うん、これ全部すごいけど、たぶん一生使わないな」って(笑)。
僕の中では、そういうのって全部“頭の中”でやることなんだよね。
アンディ:
わかるよ。たぶん世代的な違いもあると思うけど、僕は「触って感じる」タイプなんだ。フェーダーを直接動かしたり、ノブを回したりしたい。スクロールして設定を探すんじゃなくてね。でも、まあ、選択肢が増えたってことだよね。
ラリー:
少し前にティム・ヘンソンと仕事したことがあるんだけど、彼は完全にその逆。「イン・ザ・ボックス(すべてをPC内で完結)」の人間だね。
アンディ:
ああ、そうそうそう、彼、僕の家から10分くらいのところに住んでるよ。
ラリー:
おお、それは面白いね。
アンディ:
本当に、めちゃくちゃ良い人なんだよ。
ラリー:
彼の考え方は、そのままPolyphiaの音楽にも表れてるよね。
アンディ:
だから、これからちょっと一緒に時間を過ごす予定なんだ。お互いのスタジオを行き来して、どうやって音を作っているのか、お互いのやり方を理解し合えたらいいなと思ってる。そこから何か学べるかもしれないしね。
僕も少しは最新のテクノロジーに向き合わなきゃなって思ってるんだ。今まではちょっと距離を取ってきたんだけど、今のやり方がすごく気に入ってるから。でも、技術はどんどん進化してるしね。
とはいえ、まだ僕の後ろにある本物のアンプに匹敵するプロファイルやIR(インパルスレスポンス)の音は、正直まだ聴いたことがないんだよね。
ラリー:
僕は「両方の世界をできる限り理解する」っていうスタンスなんだ。昔はフィルム写真から始めて、それがデジタル、さらに映像へと変わっていった。正直に言うと、フィルムを手放すのはあまり嬉しくなかったよ。だって、フィルムでは自分の理想の画をどうやって作るか分かってたから。でも、デジタルはとにかく速い。
ギターの世界でも、プラグイン系は“煙と鏡”みたいな部分もあるけど、本当にクールなものもある。ティムとの作業はきっと楽しいと思うよ。
アンディ:
ほんと、僕が今使えている技術っていうのは、全部誰かが家に来て教えてくれたからなんだ。そういう人たちが「ここまではできるよ」って助けてくれたからこそ、ようやく扱えるようになった。僕の脳は、そういう仕組みを理解するのに向いてないんだよね。まあ、それが僕なんだけど(笑)でも、それでいいんだよ。だからこそ、自分にないものを補ってくれる人たちと繋がるのが大事なんだ。
ラリー:
最近、DiMarzioに送られてくる新しいアーティストのデモを聴いてると、ちょっと気になることがあってね。ギターの音が“シュワシュワ(fizzy)”しすぎてるんだよ。多段階のプリアンプ・ディストーションや、何層にも重なったプラグインのせいで、ギターのインパクトが失われてるんだ。
でも君の音は、常にライブでもレコーディングでも、しっかりと存在感がある。いわゆる「イン・ザ・ボックス」で作られた音って、どこか“寄せ集めのコラージュ”みたいになってることがあるんだよね。既存の素材を何層も重ねたり、断片をつなぎ合わせたり……もちろん、それがうまくいくこともある。でも、それを本当に成立させるには、“ジョージ・マーティン的”な発想を持った誰かが必要なんだ。
アンディ:
もちろん。
ラリー:
結局は、「自分が何を求めているか」ってことだよね。
アンディ:
うん、本当にその通り。
ラリー:
それをちゃんと理解できていれば、自分の“絵の具箱”にもっと多くの色が加わるんだよ。それを僕は“レイヤリング(重ねること)”って呼びたい。ティムはそれを見事にやってる。
アンディ:
間違いないね。初めて一緒に会ったとき、僕は正直に言ったんだ。「Polyphiaの音源、ちゃんと聴いたことがなかったんだけど、本当に感銘を受けたよ」って。そしてすごく楽しめたしね。君が言ってたように、ラップの影響や、現代的な要素が彼の録音やプロデュースのアプローチに反映されてるのを聴いて「おお!」って思った。
だからこれから、彼らのバンドと、ティムやスコットのことをもっと知っていくのはきっと楽しい時間になると思うし、彼らから吸収できることがあれば嬉しいなって思ってる。それが自分にどんな影響を与えるかは分からないけど、どんな形であれきっと刺激になるはずだよ。
ラリー:
ティムは“デジタル的直感”の持ち主なんだよ(笑)
僕なんて真逆で、アコースティックギターの力木(ブレース)を、音が良くなるまで一つひとつ手で削るタイプだけど……でも、新しいアプローチは大好きさ。
アンディ:
はは、まさにそれだよ。僕なんかいつも思い出すのが、フィル・ハートマンがやってた古いキャラクターでさ。「俺は原始人だ……」ってやつ(笑)
僕らには“自分のやり方”があるんだよね。それが美しいことなんだ。育ってきた環境や、自分が理想とする音にどうたどり着くか、それぞれ違うだけ。
だから、現代のテクノロジーを取り入れることって、“原始人”にとっても悪いことじゃないと思うよ(笑)
ラリー:
1960年代のビートルズを見てみなよ。あれはもう、当時としては超前衛的で実験的だった。最初はハンブルクのバーでアメリカンミュージックを演奏してたのに、数年後には“ミュジーク・コンクレート”(具体音楽)を取り入れて、テープを切り貼りして逆再生してポップソングにしてたんだから。あれも全部、同じ“表現”なんだよ。
アンディ:
はは、僕がいつも言いたくなるのが、「Love Me Do」が1962年で、「Tomorrow Never Knows」みたいにテープループを使った曲がもう1966年。たった4年で、だよ!?「Strawberry Fields」だって’66年に書かれて、録音はその年の終わりから翌年の初め。信じられる? あの進化と爆発的成長! 彼らはとんでもない勢いで吸収してたんだよ。
ラリー:
本当にそうだよ。
アンディ:
マジで信じられない。
ラリー:
あの時代って、ファッションも映画も音楽も、いろんなものが一斉に影響し合ってた。最近観た『Catching Fire: The Story of Anita Pallenberg』っていうドキュメンタリーも、いろんな“点と点を結びつけてくれる”すごく良い作品だったよ。
アンディ:
うんうん、そういうのは大事だよね。
ラリー:
あの時代には“ルール”なんてなかった。
アンディ:
音楽にルールなんて要らない。自由であるべきだよね。
ラリー:
たしかクインシー・ジョーンズが言ってたと思うんだけど、「音楽には2種類しかない。良い音楽と悪い音楽」ってね。
アンディ:
はは、それも結局は“好み”の問題だよね。
ラリー:
でも、クインシーにはその視点があった。フランク・シナトラからマイケル・ジャクソンまで手がけて、他にもたくさんのアーティストとヒット曲を生み出してきたから。
それはそうと……君のギターの話に戻ろう。ローステッド・メイプルのネックを使い始めたのって、いつから?
アンディ:
えっとね、アイバニーズがAZシリーズを出した頃からかな。だから、はっきりとは覚えてないけど。このネック自体はローステッド(熱処理)されたものじゃなくて、自然にエイジングされたものなんだ。元々は未塗装で、今は汚れてるだけ(笑)
このギターの元になったのは、クレイマーが倒産する前に作ってくれたストラト風のパーツギターだったんだ。もしかするとパーツはシェクター製だったかもしれないけど、はっきりは分からない。とにかく、ヴィンテージ・フェンダー風のナロウショルダー(細い肩)のネックで、未塗装だったんだ。
アイバニーズにロースト処理が一般化する前に、最初のプロトタイプを作ってもらっててさ。新品のメイプルネックって真っ白すぎて、僕が長年使ってきたものと比べると違和感があったんだよね。だから「なんとかしてこれを少し色味を落ち着かせてくれない?」ってお願いした。
だから、いつからロースト仕様に移行したのか、正確なタイムラインは覚えてないけど、その方向性になったときには大歓迎だったよ。僕の愛用してるヴィンテージ風フェンダータイプのギターにはすごく合ってたからね。
ラリー:
当時はみんな試行錯誤してたよね。だって、フェンダーもギブソンも、僕たちが欲しいようなギターを作ってくれなかったから、ギタリスト自身が“いじる”ようになったんだ。
アンディ:
そうだよね。
ラリー:
CBSがフェンダーを買収したあたりから、方向性がズレ始めた。企業の経理担当みたいな人間が全てを決めるようになって、音も感触もどんどん悪くなっていった。1950年代のフェンダーやギブソンには良い個体がたくさんあるけど、1965年になると、サウンドもフィーリングも失われて、新しいこともやってなかった。
だから僕は、すべてを比較して試してたんだよ。たとえば、ストラトのブリッジピックアップと、レスポールJrのブリッジに載ってるP-90を比べてみたりね。P-90には温かみとスイートさがあって、ストラトのブリッジピックアップなんて太刀打ちできなかった。
だから自分でストラトのピックアップを改造し始めたんだ。低音域を太くして、高音域の角を丸くして、出力も3割くらい増やした。あと、自分の設計ポリシーとしては「ギターをいつでも元の純正状態に戻せること」。だからサイズも純正に収まるように作ってた。
フェンダーはもっとギタリストの声を聞くべきだったと思う。僕は各ポジション(ブリッジ・ミドル・ネック)に合わせて別々のピックアップを作ったけど、ヴィンテージストラトのネックピックアップはR&Bやバッキングにはすごく良かった。でも他のポジションは僕には合わなかったんだ。
アンディ:
うん、分かるよ。
ラリー:
(笑)ブリッジポジションにくると、もう“使い物にならない”か、アンプの設定を全部変えなきゃいけなくてね。でもそれって、なんか違うじゃないかと思ってたんだ。
アンディ:
うん、それこそがギタリストの“永遠の悩み”だよね。
ラリー:
そう、それで僕はストラトのブリッジ・ピックアップに厚みを加えて、求めていたトーンを手に入れた。それが最終的に**Super Distortion®**の開発へとつながったんだ。
ギブソンとフェンダーが企業に買収されたことで、音づくりにも変化が起きたことは誰もが知ってるよね。要するに「コスト削減」がすべての判断基準になってしまった。ストラトのブリッジは鋳造になり、塗装は分厚いポリウレタン仕上げ。ギブソンは端材を全部接着してボディに使ってた。そういうのが全部、トーンを壊していったんだ。
当時、僕は1950年代のギブソンやフェンダーを売ったり買ったりしていたけど、それらは本当にインスピレーションをくれる存在だった。今みたいに、やたら頑張ってようやく“まあまあの音”を引き出す必要なんてなかったからね。
アンディ:
はは、それって「音を無理やり叩き出す」って感じだね。
ラリー:
まさにその通り。
アンディ:
そして、良い音を出すために苦労しなきゃいけなくなる。
ラリー:
うん。でもさ、ライブで演奏しに来てるのに、ギターと闘う必要なんてないじゃない?
70年代を振り返ってみると、ギブソンとフェンダーの“失敗”が、実は70年代の新興ギターメーカーの誕生を生んだんだよ。いわば、ギターにおける4つの思想的な“学派”が現れた。サンフランシスコ、ニューヨーク、ロサンゼルス、そしてシカゴ。それぞれが独自のアプローチでギターづくりに取り組んでいて、どれも“プレイヤー主導”だった。
たとえばサンフランシスコではAlembicが内蔵エレクトロニクスを搭載したギターを作ってたし、Stars Guitarsは真鍮パーツを使っていた。ロサンゼルス周辺からは**Neil Moser(BC Rich)**によるホットロッド化された“スーパー・ストラト”や完全に近未来的なボディデザインが生まれた。
DeanやHamerは、Vシェイプやエクスプローラーの再発明に取り組み、ニューヨークには僕がいた。ピックアップ中心の設計や、Guitar Lab、他の小さなビルダーたちも加わっていたよ。後にはSpectorやSteinbergerが全く新しいボディシェイプで登場した。どこもこぞってDiMarzioのピックアップを使って、“新しい音”を目指していたんだ。
スーパー・ストラトの誕生地は、南カリフォルニアのWayne Charvelのショップを中心に形成された。Wayneがボディを作って、DiMarzioがピックアップを提供。1976年にはFloyd Roseがロック式ブリッジを開発して登場した。
すべては、ストラトのボディに適合するように設計されていて、組み合わせて“より良いギター”を作るためにあった。
アンディ:
まさにその通りだね。
ラリー:
当時、僕ら全員が同じことを考えてたよ。ストラトのボディに、トレモロユニット、そしてブリッジポジションにハムバッカーを搭載する。
スーパー・ストラトは、フェンダーが発明したものじゃない。プレイヤーたちが、より良いギターを作るために、パーツへのアクセスを活かして生み出したんだ。
Phil Collenが教えてくれたんだけど、彼がEddie Van Halenとギター談義してたときに、エディが言ったそうなんだ。「俺のトーンの秘密のひとつは、ストラトのブリッジにハムバッカーを入れることだ」ってね。
アンディ:
ああ、なるほど。まさにそれだね。
ラリー:
君のギターを見てみてよ。
アンディ:
でさ、その「ストラトのブリッジ・ピックアップを引っこ抜いてハムバッカーを入れた」最初の人って、はっきり誰か分かってるの?最初にやった人は誰なんだろう?
ラリー:
僕はカール・サンドヴァルに聞いたんだよ(彼は当時ウェイン・シャーベルのショップで働いてたんだけど)、「最初にスーパー・ストラトを作ったのは誰?」ってね。彼も確信は持てないって言ってたけど、ジョージ・リンチ、エディ(ヴァン・ヘイレン)、ランディ・ローズ……そういう南カリフォルニアのギタリストたちが、互いに影響し合ってたって。
個人的には、エディ・ヴァン・ヘイレンがあの改造スタイルを世に広めた張本人だと思ってる。みんな「彼の音が欲しい」って思ってたからね。
アンディ:
まさにその通りだよ。君がジョージ・リンチの名前を出したのも興味深いね。僕もDokkenはよく知ってたし、彼のプレイの大ファンなんだ。実際に何度か一緒に過ごしたこともある。
何年か前にポール・ギルバートがやったギターキャンプがあって、僕とジョージ、グレッグ・ハウとか、ほんと素晴らしい面々が講師陣として参加してたんだ。
で、ジョージは機材一式を自前で持ち込んでたよ。古いマーシャルに、あとは適当に床に置かれたペダル類(笑)。それがすごく印象的だったんだ。
彼はエディと同じ時代を生きてたけど、プレイスタイルは全然違った。でも同じ“原動力”を感じたよね。彼の演奏って、本当にリアルで、生々しくて、その時代そのものだった。
“これがあの時代のサウンドか”っていう、本物の音だったんだ。いつもとは違う文脈で彼の音を聴けたのも新鮮だったし、他のプレイヤーとのジャムの中で、それが際立っていて、とても美しかった。
あの場にいられて本当に良かったよ。「ああ、これがカリフォルニアの流れなんだな」って、まさに君が言ってた“あのショップに集まって試行錯誤してた男たち”のことを体現してた。ジョージはまさに次のサウンド革新の創始者の一人だったんだ。
ラリー:
その通り。スパンデックスに変な形のギターっていう時代(笑)
DiMarzioとCharvelはその「ギターパーツ革命」の真ん中にいた。みんなが**“現実離れしたサウンド”を追い求めてたんだ。僕はニューヨーク出身だからちょっと違ってて、影響を受けたのはレスリー・ウェスト**だったけどね。60年代後半の話だよ。
アンディ:
うわあ、そうだったんだ。
ラリー:
80年代には、レスリーと一緒に過ごす機会もあったんだ。
アンディ:
すごいね、それはヤバい。
ラリー:
ああ。
アンディ:
あの音……信じられない。彼ってやっぱりP90メインだったよね? レスポール・ジュニアに載ってるP90が彼の定番だったはず。
ラリー:
そうそう。Mountain時代はレスポール・ジュニアがメインだった。でもね、彼が何を弾いても**“レスリーの音”**になっちゃうんだよ。
アンディ:
ああ、やっぱりね(笑)
ラリー:
でも、彼が弾いてたテレキャスターを僕が試奏してみると、ちゃんとテレキャスターの音がするんだよね(笑)
アンディ:
ああ、それは絶対すごい光景だっただろうなぁ。
ラリー:
本当にそう。多くの人が頭の中に理想の音を持ってて、それを**“どうやって外に出すか”**が勝負なんだ。
1985年頃かな、レスリーをフランクフルト・ミュージックメッセ(ヨーロッパ版のNAMM)に招待して、DiMarzioブースでデモをやってもらったんだ。
会場には“サウンドルーム”を作ってて、休憩中、レスリーは小さなキッチンでダイエットコーク飲みながらくつろいでた(笑)
僕はブース前でお客さんと話してたら、肩をトントンと叩かれたんだ。振り返ると、スコットランド訛りの男性がいて「レスリーはここにいるかい?」って聞いてきた。
僕はとっさに警備モードになって、「どちら様とお伝えすれば?」って聞いたら……
**「ジャック・ブルースだと伝えてくれ」**って(笑)
その瞬間、頭の中で**”Tales of Brave Ulysses”**が流れ始めたよ(笑)
アンディ:
うわぁ……すごいね。
ラリー:
でさ、僕は心の中で「マジかよ、ジャック・ブルースだ!」って思ったよ(笑)……「はい、すぐにレスリーを呼んできます!」ってね。
アンディ:
それはもう、“歴史的瞬間”だね。
ラリー:
あとで分かったんだけど、ジャックとレスリーは、West, Bruce & Laingが解散して以来、一度も会ってなかったらしいんだ。でも、その再会はすぐに笑顔とハグの嵐になったよ。(写真もあるんだ)
アンディ:
うわ……まじか。
ラリー:
で、レスリーが僕をジャックに紹介してくれて、「ちょっと一緒に1~2曲やろうよ」って、DiMarzioのサウンドルームで演奏することになったんだ。
あの部屋は立ち見で60人くらいが限界の小さなスペースで、まさかベースプレイヤーやボーカルが来るとは思ってなかったから、準備もしてなかった。
慌ててジャック用のアンプをどこかから借りてきて、レスリーはもう一台のアンプに繋いだ。マイクはなし。
そしたらレスリーがジャックに言うんだよ——
**「お客さんが来る前に、1〜2曲やっとこうか」**って。
で、そこにいたのは僕とジャックとレスリーだけ。そして彼らが演奏し始めたのが——
**「Theme from an Imaginary Western」**だったんだ。
アンディ:
うわっ、それ、僕が彼の曲の中で一番好きな曲だよ。
ラリー:
しかも、マイクなしで、だよ。
アンディ:
うわぁ……でもあの曲って、過小評価されてたよね。あまり注目されなかった。
ラリー:
あれは僕も大好きな曲で……本当に泣きそうになったよ。それくらい素晴らしかった。
アンディ:
それはもう……奇跡の瞬間だね。ほんとにヤバい。
ラリー:
まさに、“音”を持ってる人たちの演奏だった。
アンディ:
もちろん。僕も彼を一度だけ観ることができたんだ。
サトリアーニのツアーのオープニングで、ダラスに来たときだった。ドラムはコーキー・ラングで、ベースは若手のプレイヤーだったけど、あれが彼を生で観られた唯一の機会だったから、すごく嬉しかったよ。
ラリー:
レスリーって、スタンダップコメディアンとしてもいけたと思うよ。何を口にするか予測できない(笑)完全にアドリブだったし、彼とコーキーが一緒にいると、まるでサボって遊んでる高校生みたいだった。
僕とレスリーが一緒に出てる動画があるから、ぜひ観てみてよ。
レスリーが僕にちょっかい出してくるんだけど、あのユーモアのセンスがよくわかるはずだから。
アンディ:
あれはまさに「ロングアイランド的おふざけ」って感じで、全部がそれだった。でもすごく楽しかったよ。本当に最高だった。
ラリー:
うん、めっちゃ「ニューヨーク」って感じだったよね。
アンディ:
完全にそう。それがまさに雰囲気だった。ああいうのを目撃できるって本当に嬉しいことだよ、間違いない。
ラリー:
それで、君の新しいギターの話に戻るけど、今進めてるIbanezの新モデルは、よりヴィンテージなストラトトーンを目指してるよね……でももっと多機能にしたい。いわば「ハイパーキャスター」!
アンディ:
そう、その通り。それがゴールなんだ。どれだけヴィンテージっぽいトーンが出せるかを探りつつ、僕が必要とする弾き心地と安定性をちゃんと備えたギターにしたい。
ありがたいことに、何本かのオールド・ストラトを持ってて、それを参考にできるんだけど、音は素晴らしくても、丸1本のライブを通して使うのは無理なんだ。信頼性がないし、僕が必要とするすべてをこなすのは難しい。
だから……全部欲しいんだよ、ラリー。全部もらえる?
ラリー:
「エブリシング・キャスター」だね(笑)
新しいサウンドと、君がいつも使ってるオリジナルがあれば、どんなシーンにも対応できるよ。
それに、君はエフェクターの開発にも関わってるよね?いくつぐらい作ってきた?
アンディ:
今のところ3つかな。Keeley(キーリー)とはエコーが2種類あって、もう1つがドライブペダル。
一番有名なのはHalo(ヘイロー)で、それが一番売れてるね。
それから2024年11月に、機能を絞ったHalo Coreっていうライト版も出した。
それと、Keeleyには僕専用のドライブペダルMK3があるよ。
ラリー:
ああ、あのドライブペダルは覚えてるよ。
アンディ:
そう、Blues Driverをベースにした大幅改造版だよ。今のMK3が3代目で、かなり好評なんだ。
それからJHS Pedalsにも僕のリードトーンを再現したペダルがあって、それが**AT+(@)**っていうモデル。ロゴも「@」マークになってる、ちょっと洒落が効いてるやつ(笑)それが主なモデルたちだね。
あと昔はCarl Martinって会社とコンプレッサーを出してたけど、品質面で問題が出てきて、再設計が必要になってしまって……僕はもう関与しなくなった。残念だけど、終了するしかなかった。
ロバート・キーリーは本当に好きなコラボ相手の一人で、彼らは僕の住んでるところから車で3時間、オクラホマシティにいるんだ。
だからHalo Echoの開発では、お互いのスタジオを何度も行き来して、1年半かけて理想の音を追い求めたんだよ。
最終的に完成した時には本当に嬉しかった。価値あるプロセスだった。
まあ正直に言えば、あれはかなり“自己中心的”な開発だったと思う(笑)
「僕がこういう音が欲しい」ってだけで始めたんだけど、予想以上に多くの人に受け入れられて、その年はキーリーにとっても大きなビジネスになった。
ラリー:
君のあのリバーブ/エコー/ディレイの音は、本当にギターに完璧に合ってると思う。
アンディ:
ありがとう、本当に嬉しいよ。
元になっているのは、僕が大好きなEP-3テープエコー、**Memory Man(エレクトロ・ハーモニクス)**とかね。
みんな似た方向性を目指してる機材なんだけど、それらの良いところを全部まとめて、1つのペダルで再現しようとしたんだ。で、Keeleyが完璧にやり遂げてくれたんだよ。
Strymon(ストライモン)も使ってたんだけど、あれはあれで良かった。90%くらいまでいってた。
でも、1000個の機能はいらなかった(笑)
僕が使うのは1~2つの音だけだったから、だったらその音を最高のクオリティで出せるようにしようって。
最初、Keeleyの人たちは「ECCOSっていう新しいチップを使った機種があるから、それをちょっとモディファイすればいけるかも?」って思ってたらしいんだけど、いざ一緒に部屋で音を出してみると、「いや、これは思った以上に遠いぞ」ってなって(笑)
でも、彼らがそのプロセスを楽しんでくれてるのが分かったから、作業を進めるのがすごく楽だった。
音楽スタジオでも同じだよね。「このエンジニア、どこまで付き合ってくれるんだろう?」って考えることあるけど、ちゃんと一緒に“音を追い詰めてくれる余白”があるなら、もう限界はない。時間なんて気にしない。
もちろん、僕らはビジネスの世界にいるから、いつかはお金の話をしないといけないけど、このプロジェクトではそういうことを一切考えずにやれた。
それこそが素晴らしかった。
で、思い返すと、Danger Danger時代にいろんな素晴らしい経験をさせてもらえたのも、ある意味「そこそこの成功」だったからこそなんだよね。めちゃくちゃ売れたわけじゃなかったけど、すごく楽しいツアーをたくさんできたし、まあ当然バンドらしく莫大な借金も背負ったけど(笑)
でもあの頃の**メジャーレーベルの“企業的なやり方”**を見て、「あ、これは僕がやりたかった音楽とは違うな」って気づかされたんだよね。
ラリー:
そうだね。
アンディ:
バンドで活動して、メジャーレーベルに所属することが、まるで“聖杯”のように思ってた時期があった。でもその渦の中心に実際に飛び込んで、その裏側の仕組みを目の当たりにしたときに気づいたんだ。
「アーティストもアートも、ここでは実はそんなに重要視されてない……いや、まったく重要じゃないのかもしれない」って。
最終的に思ったのは、**「自分の作りたい音楽を、自分のために作りたい」**ってことだった。自分が好きなことをやりたい。
うまくいけば、それはそれで素晴らしいし、ただ自分自身が上達することに集中したいと思ったんだ。
そしてそれ以降は、その考え方をキャリアの中心に据えて進んできた。
いわば、業界の常識とは逆の道を選んだんだよ。
「とにかくツアーを回って、これだけ稼いで、ひたすら売りまくれ」っていうのが定番のやり方かもしれない。
実際、それをやってる友人もたくさんいる。
でも、それだけが方法じゃないんだ。
僕はいまもこうしてここにいて、心から作りたい音楽を作れている。
同じ価値観を持つ素晴らしい人たち、素晴らしい企業と一緒に仕事ができている。
いつも「利益優先」というわけじゃなくて、君がさっき言ってたような「会計士的な発想」ばかりじゃない。
今でも“誠実さ”を大切にしてる人たちがちゃんと存在してる。
僕はそういう人たちに囲まれていることに本当に感謝してるし、君もその“輪”の一員だよ、ラリー。
君が僕と一緒に仕事をしてくれること、そしてスティーブ・ブルッカーやDiMarzioチームのみんなが、
「君が探してるその音って、一体なんなんだ?」って一緒に追求してくれることを、僕は軽く受け止めてなんかいない。
だって、それって言葉で説明できない音の世界を一緒に探していくプロセスだから。
細かい調整や微妙な違いを、僕らみたいな人間は知ってるし、その“わずかな差”がどれだけ大きいかを理解してる。
ラリー:
君が時間をかけてまで新しいギターを改善したいと思ってること、サウンドを磨き続けたいって思ってくれてることが本当に嬉しいよ。
その旅の一部になれて誇りに思うし、僕と一緒に取り組んでくれてることが光栄だよ。
アンディ:
本当に素晴らしいことだよ。
それって、“音を探す旅”の中でとても価値のある瞬間だと思う。
僕も地元でそういう人たちに恵まれてきたからよく分かる。
ニューヨークで、まだそんなことが当たり前じゃなかった時代に、ギターのピックアップを巻き直したり、配線をいじったりしてくれる人がいたことって本当に貴重だよね。
常に「もうちょっとだけ、良くならないか?」って音を追い求める姿勢が大切なんだよね。
ラリー:
うん、まさに。
アンディ:
だからこそ、僕らはいまこうして何年経っても、この話にワクワクできるんだ。
なぜって、それはいつだって改善の余地があるって知ってるから。
ミュージシャンとして、クラフトマンとして、技術者として――何であれ、“情熱”を突き動かしてくれるものがある限り、進化し続けられるんだよ。
「今日もうまくいかなかった。でも明日また試せばいい」
そう思えるのって、なんて素晴らしいことなんだろう。
学びたい、成長したいって思い続けられる。
ラリー:
僕もまったく同じ気持ちだよ。
アンディ:
あれ?何を熱く語ってたんだっけ?コーヒー飲みすぎたかも(笑)
ラリー:
僕もコーヒー大好き(笑)
アンディ:
だよね(笑)最高の飲み物だよ。
ラリー:
で、アンディ・ティモンズがギターを弾く理由って、何なんだい?
アンディ:
これは深い質問だね。だって、ギターは僕の人生そのものだったから。
一番幼い頃の記憶からあるのは、ただただギターの音に魅了されていたってこと。
それに、ギターの見た目にも惹かれてた。兄が60年代のポップやロックのレコードをよく買ってて、ブリティッシュ・インヴェイジョン系のものばかりだった。
たとえば、ハーマンズ・ハーミッツが持ってるギターをジャケットで見たり、ビートルズのアルバムの見開きや、デイヴ・クラーク・ファイヴのジャケットとか――あのフェンダーのストラトやベースを見てただけでワクワクしてた。
人生を通してギターを愛して、弾き続けてきたわけだけど、僕にとってギターは感情の避難所でもあったんだ。
僕は子どもの頃、すごく内気だった。両親は僕が幼い頃に離婚して、家では一人で過ごす時間が多かった。母は働いてたし、僕の楽しみは兄たちのお下がりのレコードコレクションだった。
13歳で初めてバイトして、ゴールドマンの質屋で12ドル99セントのエレキギターを買ったよ。
それまでは、当時の家庭によくあった政府支給のシルバートーン・アコースティックギターを弾いてた。
でもギターは、自分の感情を表現する場所になったんだ。
さっき言ったように、僕はシャイだったし、人付き合いは普通にあったけど、どこか内にこもるタイプでね。
ギターを通じてだけは、自分の中の何かを解放できたんだ。
そして、やればやるほど、「これは自分の一部なんだな」ってどんどん実感するようになった。
それくらい、音楽と深くつながってるんだよ。
ラリー:
それはね、なぜだか分かるかい?
アンディ:
うーん、たぶんだけど……兄たちが僕にとって“男のロールモデル”で、ヒーローだったからかもしれない。
みんな音楽に夢中で、ちょっとずつギターにも触れててね。
たぶん僕がギターをやりたいと思ったのは、「兄たちに認められたい」とか、「彼らが“カッコいい”と思ってるものに近づきたかった」って気持ちがどこかにあったんじゃないかな。
でも、今の僕は61歳になって、あらためて思うんだ。
ギターって、喜びも、悲しみも、あらゆる感情を感じるための場所なんだよね。
演奏を通して、それを表現する手段なんだ。
それでね、たとえばジェフ・ベックのことを思い出す。彼はキャリアの中でずっと進化を続けて、どんどん深いレベルでの表現を追求していた。
だから、僕は「彼はあと20年はやるだろうな」って思ってた。本当にそう思ってたんだ。
だから、彼をあの年齢で亡くしたのは本当に悲しい。
でも、僕はギターと音楽が人生にあったことに、心から感謝してる。
何度も僕を救ってくれたし、今も救ってくれてる。
だから、もし誰かが僕の音楽に共鳴してくれるなら、それって僕にとってこの上ない感謝の気持ちなんだ。
それはつまり、音楽が僕にくれたものを、誰かに返してるってことだから。
誰のためであれ、それってすごく謙虚にならざるを得ないけど、同時にすごく嬉しいことなんだ。
ラリー:
僕は音楽に出会ったのが早かったんだ。ヒッピーの大学生だったから、**「音楽と若者の力が世界を変える」**って本気で信じてたよ。
アンディ:
うん。
ラリー:
僕は伝統的なイタリア系アメリカ人の家庭で育ったんだけど、その文化とヒッピー文化の間でいつも葛藤してた……で、全てに対して反抗してたね。
学校ではまともに音楽を教えてくれなかったし、ベトナム戦争は真っ最中だったし……「今こそ、考え方を変えなきゃいけない」って時代だった。
アンディ:
うん、うん、うん、本当にそうだね。
ラリー:
アーティストやミュージシャンこそ、僕にとっての“仲間”なんだ。
当時、みんな**「新しいアメリカ」を探し求めていたと思うし、君と僕にはそういう共通体験がたくさんあると思う。
そして、こうして今も自分たちの好きなことを続けられてるっていうのは、本当に恵まれてる**よね。
僕の場合は、音楽とギターがあったから、ニューヨークからモンタナまで辿り着けた。
そして、君みたいな人がうちの会社をサポートしてくれてることが、さらにそれを特別なものにしてくれてるんだ。
さて、もう一つ質問があるんだけど。
アンディ:
もちろん!
ラリー:
日々の音楽的なルーティンってどんな感じ?
1日にどれくらい練習してるの?
アンディ:
それがね……面白い話なんだけど。
これはギタリストなら誰でもよく聞かれる質問で、「その人の成長の道のりを知りたい」って気持ちから来てると思うんだけど……
実は僕、あんまり“練習熱心”なタイプじゃなかったんだ。でも、いつもギターを弾いてた。
この2つは似てるようで違うんだけど、ある意味、プレイすること自体が練習になってたとも言えるかもしれない。
僕はずっと、レコードと一緒にギターを弾いて育った。
コードをちょっと教えてもらって、それをいろんなキーで動かして弾くとか、そんな感じ。
それでロックンロールができちゃうからね(笑)
つまり、理論的に disciplined に練習するというよりは、プレイしながら覚えていく感じだったんだ。
でも、13〜14歳の頃からプロとしてバンドで演奏し始めて、「あ、これは僕の人生だな」って実感するようになった。
16歳のとき、インディアナ州エバンズビルで地元の先生に習い始めたんだ。
当時すでにロックは弾けたけど、彼は譜面の読み方やジャズを教えてくれた。
バーニー・ケッセルやジョー・パスみたいなギタリストが彼のお気に入りでね。
レッスンでは課題をちゃんとこなせるくらいには頑張ってたけど、やっぱりロックじゃなかったから、あまり練習は好きじゃなかったな(笑)
それから、地元のエバンズビル大学で2年間クラシック・ギター専攻だったんだけど、やっぱり**「クラシックはロックじゃない」**っていうのがあって、そこでも「ギリギリこなす」レベルだった。
その後、マイアミ大学でジャズ・ギター専攻になって、ようやく理論的なことを本格的に学ぶようになった。
コードスケールの勉強とか、そこではちゃんと**「練習」**として取り組むことが多かったね。
でも、大学を出て、音楽キャリアが本格化してくると……
もう毎日規則的に練習するっていう習慣は完全になくなったんだ。
人生って、そうやって流れていくものでしょ。
でね、何年か経ってからの話なんだけど、これは何度か話したことがあるけど、本当に大きな出来事だった。
パット・メセニーがギターキャンプをやるって話を聞いたんだ。15年くらい前かな。
もちろん、僕もそれまでにジャズは結構学んでたし、演奏もしてた。
それは僕の音楽スタイル全体に深く影響を与えてる。
たとえば僕のロックのプレイを聴いても、「ただのロックギタリスト」には聴こえないのは、ジャズからの影響があるからなんだ。
ジャズって、コードチェンジの乗り越え方を教えてくれるし、**ヴォイス・リーディング(和音内の音の動き)**についても学べる。
で、そのパット・メセニーのキャンプの話に戻るけど、参加費がすごく高かったんだ。
だから、「自分のマスタークラスをやるっていう条件で、参加させてもらえないかな?」って主催者に提案してみたら、
「いいよ。来てよ」って言ってくれて。
もう嬉しさと同時に、めちゃくちゃ怖かったよ(笑)
「うわ、パット・メセニーの前で演奏するんだ。ヤバい、ヘタなプレイはできないぞ……!」って。
ラリー:
ハハハ!
アンディ:
彼(※パット・メセニー)は多くのギタリストに感銘を受けるタイプじゃないと思うから、僕は「よし、ちゃんと練習しよう」って思ったんだ。
それで決めたのは、「毎朝、起きたらまずジャズ・スタンダードを1時間練習する」ってことだった。
でもねラリー、それが本当に大変だったんだよ。
なぜって、昔はある程度弾けていたはずのことが、今は全然できなくなってて、自分の“ヘタさ”を毎朝聴くことになるから。
ラリー:
わかるよ。
アンディ:
でも、ジャズってそういうものなんだ。
筋トレと同じで、定期的にやってないと感覚が鈍るし、元のレベルに戻すまでに時間がかかる。
それで毎日プレイするようになった。
それから、近くに住んでる友人と週に数回集まって、**「スタンダード・ウィーク・クラブ」**を始めたんだ。
毎週1曲ジャズ・スタンダードを選んで、できるだけ多くのバージョンを聴いて学ぶっていう。
キャンプまでは9ヶ月あったから、最初の数週間は「まあまあかな」って感じだったけど、2ヶ月、3ヶ月と続けていくうちに、変化が現れ始めたんだ。
ラリー:
うん。
アンディ:
なんというか、学生だった頃の気持ちに戻った感じだった。
マイアミ大学にいた頃、素晴らしい先生たちのクラスを受けて、空き時間には友人と「1時間空いてるから、ちょっと一緒に弾こう」ってやってた。
それに、当時は週6日、トップ40のカバーバンドで演奏してたんだけど、その中でマドンナの曲にチャーリー・パーカーのフレーズを混ぜて弾いてたんだ(笑)
そんな風に続けてるうちに、「あ、これは自分の本質なんだな」って感じ始めた。
向上心を持って何かに取り組むことこそ、僕の人生の中心なんだって。
で、面白いことに、そのキャンプ自体は結局中止になっちゃったんだ。
たしか、資金繰りとかでダメになったんだと思う。結局、開催されなかった。
ラリー:
パットが君が練習してるって聞いたんだな(笑)
アンディ:
ハハハ!いやいや、聞いてないよ(笑)
もし聞いてたら、「お、頑張ってるな、でもまぁ…まだまだだね」って言われただろうな(笑)
結局そのキャンプは実現しなかったけど、そのおかげで僕の中にはもう“キャンプの恩恵”が残ったんだ。
「もし、憧れの人の前で演奏するとしたら?」って考えただけで、人生が変わった。
ちょっと長い答えになっちゃったけど、この話は伝えたいと思ってるんだ。
実際には何も起きてない。でも“想像しただけ”で、自分の人生が変わることもある。
その思考が、僕をもっと努力させてくれた。
もともとプレイもしてたし、録音もしてたし、自分の活動はしてたよ。それはそれで問題なかった。
でも、「自分は“生徒”である」って意識を持ち始めたとき、人間としても音楽家としても、すごく軽やかになった。
それは、きっと自分に与えられた“ギフト”を大切にしようと思えたからだと思う。
たとえ“才能”があったとしても、なかったとしても、「ギターを弾ける」ということはギフトそのものなんだ。
それを大切に扱わなきゃって思った。
みんなが僕を信頼してくれてるからこそ、僕は今もこうして音楽を続けられている。
ギグでも、レコーディングでも、機材開発でも、それは全部“信頼の結果”だと思ってる。
だからこそ、もっと上手くなろう、もっと良くなろう、もっと深く音楽と向き合おうとすることに意味があるんだよね。
そうしてるうちに、人としても軽やかに、幸せになっていった。
……だからこの話、自分で言いながらも「ああ、やっぱりこれって大事なことだったな」って思うんだ。
で、短い答えを言えば、
**「毎朝、少なくとも1時間は練習してます」**ってこと(笑)
今でも毎朝やってるよ。コーヒーを淹れてから、iRealっていうアプリを使ってスタンダードを流して、それに合わせて1時間アドリブで弾く。
その中で、気になったラインがあれば耳でコピーして書き起こしたりもする。
こういう耳のトレーニング(イヤートレーニング)もすごく大事。
今日はウェス・モンゴメリーをテーマにして、彼のラインを何個か耳コピしてみたんだ。
必要があればスロー再生もできるし、こういう小さな積み重ねが大きな違いを生むんだよね。
つまり、大事なのは、継続すること。
“努力を続けること”をちゃんと習慣化することが、全てなんだ。
そのあと1日中ギターを弾く日もあれば、全然弾かない日もあるけど、
**「毎朝、少なくとも1時間は“自分に戻る”時間」**なんだ。
ラリー:
うん。
アンディ:
なんだかんだ言って、日々やってることって全部、僕の活動に関わってるんだよね。
だから僕のお気に入りのチャーリー・ワッツの名言があって。
あるとき誰かがチャーリー・ワッツに、「あなたって、普段1日中なにをしてるんですか?」って聞いたら、
「何をしてるかはよく分からないけど、1日中かかるんだよね」って答えたらしい(笑)
ラリー:
ハハハ。
アンディ:
でも本当に、そんな感じかもね。でも絶対に音楽には関係してるんだ。
キャリアの一部だったり、何かしら音楽にまつわることをしてると思う。
よく「趣味は何ですか?」って聞かれるけど、結局コンサート行ったり、レコード集めたりで全部音楽中心。
まあ、散歩とかハイキングも好きだけど、結局はギターにつながってるよね。
でも毎朝の1時間をちゃんとこなせたら、もうそれだけで満足。
ラリー:
この質問を君に聞いたら面白いと思ってたんだよ。
というのも、僕はコロナの間にまたギターの練習を始めたんだ。
アンディ:
おお、いいね!
ラリー:
最後にライブをやったのは1975年でね。
バンドがいないとやっぱり感覚が違うし、ライブが恋しかったんだよね。
このことは、しばらく思い出すこともなかったけどさ。
アンディ:
いやいや、遅すぎるなんてことはないよ、兄弟!
いけるって!
ラリー:
ハハハ。
アンディ:
でもね、あの時期は本当に特別だったよ。もちろんひどいこともたくさんあったけど、
多くの人にとっては価値観の再調整ができる時間だったと思う。
ラリーみたいに、音楽から離れていた人がまたギターを手に取ったって話もたくさん聞いた。
で、どうだった? まだ弾いてるの?
ラリー:
うーん、最近はちょっと練習のペースは落ちたかな。
ポストコロナの時代にDiMarzioを運営するって、それだけで時間が吸い取られるんだよね。
でも、また時間を作らなきゃなって思ってるよ。指のタコもなくなっちゃうし(笑)
今はちょっと左脳と右脳が引っ張り合ってる感じだよ。
アンディ:
ああ、それはわかるよ。
ラリー:
モンタナから工場を管理するって、子猫をまとめて抱えるようなもんだよ(笑)
アンディ:
まさに(笑)よくわかる。
ラリー:
まあ、うまくいくこともあるし、うまくいかないこともあるよね。
でも、やっぱりまたギターを弾きたいんだ。
で、練習をしてると、昔の音楽に自然と戻っちゃうんだよ。
いいことなのか悪いことなのかは分からないけどさ。
「やっぱり『Sunshine of Your Love』を、クラプトンがやったとおりにちゃんと弾けるようにならないと」って思ったり。
(まあ、クラプトン自身も毎回違う弾き方してたけどね)
それとか、「Wind Cries Maryを、ジミ・ヘンドリックスみたいに弾いてみたい」とかさ。
アンディ:
それこそが“ジュース”だよね。
僕もまずはヴィンテージの音楽から始めて、どんどん過去にさかのぼっていく。
インスピレーションになるものなら、なんでもいいと思う。
今週はウェス・モンゴメリーを耳コピしてるんだけど、
確かにもっとモダンなプレイヤーもいるけど、僕はやっぱりあの時代の音が好きなんだ。
ちょっとでも吸収できたら、他のことへのインスピレーションが一気に湧いてくるんだよね。
ラリー:
僕が初めてオクターブ奏法を聴いたのがウェス・モンゴメリーだったんだ。
それから、ヘンドリックスの曲にもその影響を感じるようになった。
すべてが、すべてに影響を与えてたんだよね。
ジャズの要素って、どんなジャンルにも重ねられる。
アンディ:
本当にそう。どんな音楽にも溶け込める。素晴らしいことだよ。
でもさ、今度会ったときには「Sunshine of Your Love」のテストをするからね(笑)
どこまで弾けるようになったか、見せてもらうよ。
ラリー:
はは、そうだね(笑)
じゃあ、あといくつか質問させて。
アンディ:
OK! でもそろそろ荷造りもしなきゃ(笑)
ラリー:
あちゃー(笑)
アンディ:
今からペルーのリマに向かうんだ。おお、神よ。
ラリー:
ちなみに、面白い話があるよ。
ジョン・ペトルーシとジョン・ミョングは、お互いに1日5時間の練習を課してたんだって。
アンディ:
マジで!? うわぁ。
ラリー:
で、もし5時間練習しなかったら、お互いに責め合うんだ。
「おい、Dream Theaterとしてのポテンシャルに見合ってないぞ」って(笑)
アンディ:
ははは、それ面白いけど、素晴らしいのは、みんな自分の道を持ってるってことだよね。
自分に合った方法を見つけるしかないんだ。
でも僕は、そういうタイプじゃなかったな。
スティーヴ・ヴァイが有名な1日10時間の練習メニューをやってたよね。
まあ、今話してるようなギタリストたちの成果を見れば、その努力は明らかだけど、
僕は自分のやり方を見つけないといけないって思ってる。
人それぞれに合ったライフスタイルがあるし、それでいい。
それが美しいことなんだよ。
……でも、正直言うと、僕は一度も10時間練習したことないと思う。さすがに多すぎる(笑)
ラリー:
最後の質問なんだけど、君っていつもすごくメロディアスだよね。
フレーズを弾いて、「あ、今ので終わったな」って思ったら、
そこからまた何かが始まる感じがあってさ。
アンディ:
それが僕の**“モードゥス・オペランディ(やり方)”なんだ。
演奏するとき、意識的に“呼吸する”ようにしてるんだよ。
ダラダラと続く文章(ランオンセンテンス)みたいに弾きたくないからね。
まあ、時にはそうなっちゃうこともあるけど(笑)
でも僕はやっぱり良いメロディ**が好きなんだ。
要するに、ギターがスピード競争みたいになるのは本意じゃない。
いや、もちろんテクニカルな速弾きも楽しいし、聴いてても面白いよ。
でも、ずっとそれだけだと飽きちゃうじゃない?
だから、僕がこれまでずっと聴いてきた音楽って、
インストゥルメンタルでもポップスでも、良いメロディがある曲なんだ。
サトリアーニや、その前のジェフ・ベックが成功した理由もそこだと思う。
どちらも**“ちゃんとした曲”があるし、魅力的なメロディがある**。
ジョー(サトリアーニ)は、ギターマニアに刺さるサウンドを持ちつつ、
一般的な音楽リスナーにも届く魅力があるんだよね。
それって、今の僕も目指してるところ。
曲を書くプロセスがすごく好きなんだ。
ソロは作曲することもあるし、インプロ(即興)でやることもある。
即興でうまくいけばそのまま使うし、気に入るものが出てこなければ、時間をかけて作る。
以前聴いた、ジャズ・ピアニストのビル・エヴァンスの名言があって、
「The Universal Mind of Bill Evans」っていう短いドキュメンタリーで語ってたんだけど、
司会はコメディアンのスティーヴ・アレンだったかな。1950〜60年代の番組。
で、その中でビル・エヴァンスの弟ハリー(バトンルージュのジャズ教育者)がインタビューしてて、
話題は**「即興と作曲の違い」**。
ビルはこう言ってた:
「即興は、1分間の音楽を1分で演奏すること。すごくフレッシュで、その瞬間そのもの」
「でも作曲は、1分間の音楽を作るのに1年かかることもある」
僕は、それって結局は同じことだと思ってる。
即興で演奏するってのは、結局“本当に聴きたい音”をその場で追いかけてることなんだ。
ラリー:
なるほど。
アンディ:
でもそれが速弾きの瞬間であれ、メロディアスな瞬間であれ、
僕たちはただ単に、「自分が本当に好きなもの」、「本当に聴きたい音」を
外に出そうとしてるだけなんだよね。
ある意味、最初はとても利己的な動機なんだ。
「今この瞬間に、自分をワクワクさせるのは何か?」
「何がベストな表現なのか?」ってことを、ひたすら探してる。
曲作りもまったく同じで、
「どうやったら、この感情を最も強く伝えられるか?」
それを表現するために、100通り、200通りと試すこともある。
一方で、即興なら、その**“瞬間”にすべてを込めなきゃならない**。
でも、時にはそれが完璧にハマる瞬間がある。
そういうときは本当に美しい。
結局は同じことなんだよ。
さっき話した**“auralect(オーラレクト)”、つまり、
自分の音楽的記憶の中に蓄積されたものたち。
それを即興の瞬間にも、作曲のプロセスにも使ってる**んだ。
僕にとっては、どっちも同じようなもの。
少なくとも、その根底にある「美しいものを形にしたい」っていう願いは同じなんだよ。
その瞬間にふさわしいエネルギーを、音にするだけ。
ラリー:
君とポール・ギルバートが一緒にジャムしてる、素晴らしい動画があるよね。
アンディ:
あれってSweetwaterのセッションのやつ?
ラリー:
そう、それ。まさに君が今話してたことがリアルタイムで映像に表れてたよね。
アンディ:
その話を出してくれて本当に嬉しいよ。
あのセッションはすごく楽しかったし、彼と僕は好きなものがすごく似てるんだよね。
それに、ポールは人としても本当に最高なんだ。
実は、あの動画には裏話があるんだよ。
僕がフォートウェインに着いたばかりで、Keeleyのプロモーションをする予定だったんだ。
空港に着いて、車の中で電話がかかってきてさ。
「アンディ、ポールが来てるよ。今ちょうどMr. Bigの新しいアルバムを録り終えたばかりで、
もう機材はセットしてあるし、**一緒にジャムしたいって言ってる。**準備できてる?」って。
こっちは朝6時のフライトでようやく到着したところだよ(笑)
それでそのまま現場に行って、ポールはすでにセッティング完了、
僕は自分のアンプに真空管を差してるような状態で、
「よしやろう!」って座って弾き始めたんだ。
そしたら、すごいセッションになって。完璧な流れで、魔法みたいな時間だった。
……でも、そのとき録画してなかったんだよ!!
で、セッションが終わったあとにスタッフが、
「じゃあ、そろそろ録画始めますか」って言ってきたとき、
「えっ!?今の録ってなかったの!?」ってなった。
あれ、映像で流れてるのはテイク2なんだよ(笑)
で、セッション終わったあとにポールに言ったんだ。
「信じられないよ、録画してなかったなんて」って。
そしたらポールは、「まあいいじゃん、俺たちがどれだけ良かったかは、俺たちが知ってるさ。」って。
ラリー:
うん、それいかにもポールらしいな。
アンディ:
だよね(笑)
ラリー:
僕の主義なんだけど、録っておけばいつでも捨てられるけど、録ってなかったらもう終わりなんだよね。
アンディ:
本当にその通り。
そのときその場にいた人たちは、何が起きたかをちゃんと感じ取ってたんだ。
それが録音されてなかったってのが、もう…。
だから、セッションの最後に丁寧かつ控えめにだけど、はっきりと伝えたんだ。
「これからは全部録音しておいた方がいいよ。何が起きるかわからないからね」って。
今どきテープ代がかかるわけじゃないし、ストレージなんていくらでもあるんだから。
でもまあ、あれは良い教訓になったと思うよ。
それでもセッション自体は楽しかったし、今でもいい思い出になってる。
——それがあの動画の裏話さ。
おお、もう荷造りしなきゃ…!
ラリー:
じゃあ、あとはいくつかメールで送るね。
今回はいい内容がたくさん取れたよ。
アンディ:
ありがとう、本当に。
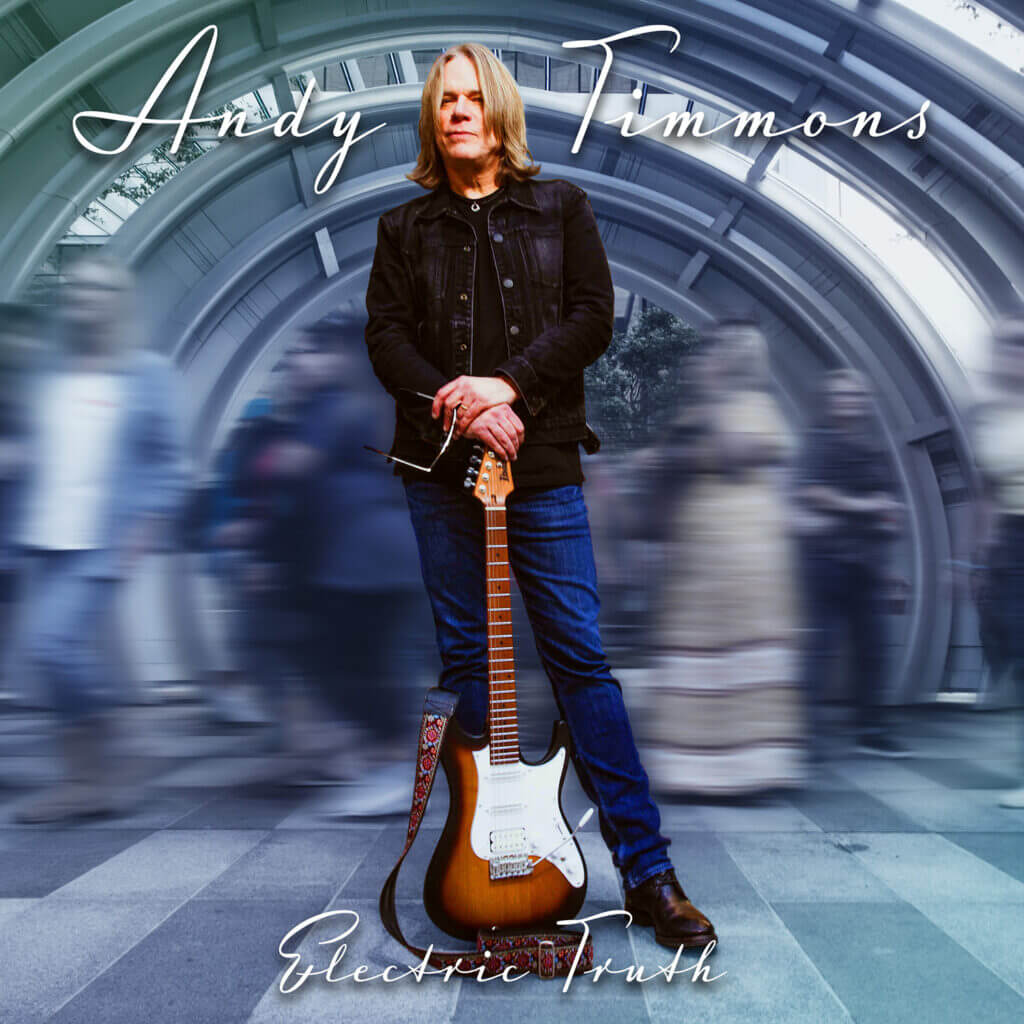

コメント